|
||||||
|
(since 17 AUG 2005) |
|
自動着陸への道-パイロット編

PAXによる、極めて大雑把な航空教室が続きます。
前回の大雑把教室では、悪天候下で自動着陸が許される条件のうちの“運航に供される機材”を題材にして「自動着陸」について少しだけ詳しく説明をしました。
今回は、悪天候下で自動着陸におけるもう一つの条件となる“運航にあたる乗務員の資格”に関する説明です。
これは、端的に言ってしまえば“機長の資格”となります。
エアラインの機長までの道のりは長く険しく、その上、めでたく航空局と社内の両方の審査に合格、機長として発令後も、半年毎の技量審査と第一種航空身体検査に合格し続けなければ、機長として乗務ができません。
さて、本題の ILS CAT III で「自動着陸」を実施できる“機長としての資格”ですが、最近の規制緩和の一環なのか、機長飛行時間300時間になれば CAT III の資格取得にチャレンジ出来るようになりました。
ざっと計算すると、機長の乗務時間の上限は確か月間80時間(それ以上は飛びたくても飛べない)だったと思いますから、上限ギリギリ飛びまくったとして、最短で約4ヶ月。
普通はそこ(上限ギリギリ)まで乗務しないでしょうから、機長に昇格してから半年~1年後になるでしょう。
実際の資格取得に際してどのような訓練が必要なのかは、PAXである私にはその詳細がわかりません。申し訳ありません。
これは想像の域を出ませんが、多分、
-「自動着陸」システムに関する座学とそれに対応する筆記または口頭試問
-SIM: Simulator による訓練と審査
-実機における「自動着陸」経験(勿論、CAT IIIではない気象条件下で回数を積む)
といったところだと思います。
航空機の性能と信頼性が向上し、地上航法支援施設の整備とも相まって CAT III の「自動着陸」が可能にはなりましたが、「自動着陸装置」も機械である以上、絶対に故障しないとは限りません。
「自動着陸装置」が何らかの変調をきたした場合には、躊躇することなく「自動操縦」を Take Over (自動操縦を解除しパイロットが操縦)する必要があります。
ILS CAT III の気象条件下では、「自動着陸」による接地の瞬間まで滑走路は見えませんから、「自動着陸装置のメッセージがおかしい」「機体の動きが変だ」ということになれば、即座に Take Over して Go Around (着陸復航)することになります。
万一の場合には“いつでも取って代われるぞ”という心構えと、そうなったときの操作は、CAT I よりも CAT II、CAT II よりも CAT III の方が時間的余裕が少なくクリティカルであり、より高度な技量が求められるのです。
CAT I の気象条件下で「自動着陸」を実施している場合では、地上から60mの地点まで降りれば雲の下に出る訳ですし、視程・滑走路視程距離も相応に遠くまで見えているので、Take Over しても Visual Reference を見つつパイロットがそのまま安全に接地操作を行なえる可能性もあります。
一方、CAT III の気象条件下での Take Over では、「おかしい」と感じたら即 Go Around (着陸復航)となるでしょう。
ともすると、『経験が乏しいパイロットを助けるのが「自動着陸」だ』と考えてしまいがちですが、全天候下で「自動着陸」を行なえるのは、逆に機長としての経験を積み、対応する訓練を受け資格を有するパイロットだけなのです。
ちなみに、「自動着陸装置」が変調をきたす機上の原因として最も有力視されているのが、人工的な電波による“計器着陸装置の誘導電波”の撹乱(かくらん)や操縦制御信号系統へのノイズ混入です。
ぶちあけた話、携帯電話の電源が入っていたり(地上が近いので、携帯電話くんも盛んに地上基地局を拾おう=圏外からアンテナ3本立てようと、質問電波を発射するのです)、電波を発する電子機器の電源が入っていたりが危険因子となるのです。
“計器着陸装置の誘導電波”は精度が高い(飛行機を自動でぴたりと接地点にまで誘導する程ですから…)と共に非常に敏感でもあるのです。
『離着陸時は全ての電子機器の電源を~;機内では電波を発する機器は常に~』の理由がここにもあるという訳です。
さて、話題が少しそれますが、航空局と会社の審査に合格して、はれて機長の辞令を手にしても、いきなり困難な気象条件下で機長としての乗務はできません。CAT III 取得資格の要件が「機長飛行時間300時間」と述べましたが、それ以前に「機長飛行時間100時間」の要件を満たした段階で CAT I の資格をとる必要があります。
CAT I, CAT II, CAT III と順を追ってそれぞれの資格を取得することになります。
ちなみに、CAT I の資格を有していないと、雲低高度が 200feet (約60m)かつ滑走路視程距離が600mよりも良好な気象条件下でないと、着陸進入を開始することすら出来ません。
機長の辞令をもらい、機長としての初フライトが始まった瞬間から、より質の良い安全で快適な運航へ向けての新たな試練が始まるといっても良いでしょう。

※最低気象条件 Weather Minimum は飛行場、滑走路によって異なる場合があります。(実際、地上の一時的な障害物(クレーンなどの建設機材)に起因して Weather Minimum が変更された旨のチャート差替えが多くて....毎週大変です)

今回は肝要な資格取得への訓練内容についてわからないので「まとめ」は無しです。
【本日の余談】
「機長飛行時間300時間」の要件を満たせば、CAT III (キャット・スリーと発音します)の資格取得へチャレンジ出来るのだから、ベテランの機長は皆 CAT III の資格を持っているのだろうと言うと、そうとは限りません。
例えば、どう頑張ったところで、在来型ジャンボのキャプテンは、航空機の制限によりCAT III運航が許されません。よって、CAT III の資格を持っていても、何の役にも立ちません。
俺は定年までずっと在来型ジャンボでゆくから「そんな資格要らんよ」というベテランの機長もいる訳です。
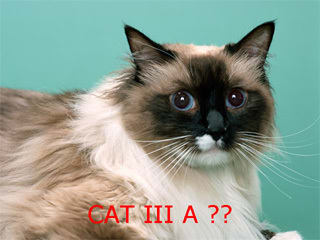
....回を重ねる度に内容希薄になっておりますが懲りずに次回[最終回-運用編]へと続く(予定)
前回の大雑把教室では、悪天候下で自動着陸が許される条件のうちの“運航に供される機材”を題材にして「自動着陸」について少しだけ詳しく説明をしました。
今回は、悪天候下で自動着陸におけるもう一つの条件となる“運航にあたる乗務員の資格”に関する説明です。
これは、端的に言ってしまえば“機長の資格”となります。
エアラインの機長までの道のりは長く険しく、その上、めでたく航空局と社内の両方の審査に合格、機長として発令後も、半年毎の技量審査と第一種航空身体検査に合格し続けなければ、機長として乗務ができません。
さて、本題の ILS CAT III で「自動着陸」を実施できる“機長としての資格”ですが、最近の規制緩和の一環なのか、機長飛行時間300時間になれば CAT III の資格取得にチャレンジ出来るようになりました。
ざっと計算すると、機長の乗務時間の上限は確か月間80時間(それ以上は飛びたくても飛べない)だったと思いますから、上限ギリギリ飛びまくったとして、最短で約4ヶ月。
普通はそこ(上限ギリギリ)まで乗務しないでしょうから、機長に昇格してから半年~1年後になるでしょう。
実際の資格取得に際してどのような訓練が必要なのかは、PAXである私にはその詳細がわかりません。申し訳ありません。
これは想像の域を出ませんが、多分、
-「自動着陸」システムに関する座学とそれに対応する筆記または口頭試問
-SIM: Simulator による訓練と審査
-実機における「自動着陸」経験(勿論、CAT IIIではない気象条件下で回数を積む)
といったところだと思います。
航空機の性能と信頼性が向上し、地上航法支援施設の整備とも相まって CAT III の「自動着陸」が可能にはなりましたが、「自動着陸装置」も機械である以上、絶対に故障しないとは限りません。
「自動着陸装置」が何らかの変調をきたした場合には、躊躇することなく「自動操縦」を Take Over (自動操縦を解除しパイロットが操縦)する必要があります。
ILS CAT III の気象条件下では、「自動着陸」による接地の瞬間まで滑走路は見えませんから、「自動着陸装置のメッセージがおかしい」「機体の動きが変だ」ということになれば、即座に Take Over して Go Around (着陸復航)することになります。
万一の場合には“いつでも取って代われるぞ”という心構えと、そうなったときの操作は、CAT I よりも CAT II、CAT II よりも CAT III の方が時間的余裕が少なくクリティカルであり、より高度な技量が求められるのです。
CAT I の気象条件下で「自動着陸」を実施している場合では、地上から60mの地点まで降りれば雲の下に出る訳ですし、視程・滑走路視程距離も相応に遠くまで見えているので、Take Over しても Visual Reference を見つつパイロットがそのまま安全に接地操作を行なえる可能性もあります。
一方、CAT III の気象条件下での Take Over では、「おかしい」と感じたら即 Go Around (着陸復航)となるでしょう。
ともすると、『経験が乏しいパイロットを助けるのが「自動着陸」だ』と考えてしまいがちですが、全天候下で「自動着陸」を行なえるのは、逆に機長としての経験を積み、対応する訓練を受け資格を有するパイロットだけなのです。
ちなみに、「自動着陸装置」が変調をきたす機上の原因として最も有力視されているのが、人工的な電波による“計器着陸装置の誘導電波”の撹乱(かくらん)や操縦制御信号系統へのノイズ混入です。
ぶちあけた話、携帯電話の電源が入っていたり(地上が近いので、携帯電話くんも盛んに地上基地局を拾おう=圏外からアンテナ3本立てようと、質問電波を発射するのです)、電波を発する電子機器の電源が入っていたりが危険因子となるのです。
“計器着陸装置の誘導電波”は精度が高い(飛行機を自動でぴたりと接地点にまで誘導する程ですから…)と共に非常に敏感でもあるのです。
『離着陸時は全ての電子機器の電源を~;機内では電波を発する機器は常に~』の理由がここにもあるという訳です。
さて、話題が少しそれますが、航空局と会社の審査に合格して、はれて機長の辞令を手にしても、いきなり困難な気象条件下で機長としての乗務はできません。CAT III 取得資格の要件が「機長飛行時間300時間」と述べましたが、それ以前に「機長飛行時間100時間」の要件を満たした段階で CAT I の資格をとる必要があります。
CAT I, CAT II, CAT III と順を追ってそれぞれの資格を取得することになります。
ちなみに、CAT I の資格を有していないと、雲低高度が 200feet (約60m)かつ滑走路視程距離が600mよりも良好な気象条件下でないと、着陸進入を開始することすら出来ません。
機長の辞令をもらい、機長としての初フライトが始まった瞬間から、より質の良い安全で快適な運航へ向けての新たな試練が始まるといっても良いでしょう。

※最低気象条件 Weather Minimum は飛行場、滑走路によって異なる場合があります。(実際、地上の一時的な障害物(クレーンなどの建設機材)に起因して Weather Minimum が変更された旨のチャート差替えが多くて....毎週大変です)

今回は肝要な資格取得への訓練内容についてわからないので「まとめ」は無しです。
【本日の余談】
「機長飛行時間300時間」の要件を満たせば、CAT III (キャット・スリーと発音します)の資格取得へチャレンジ出来るのだから、ベテランの機長は皆 CAT III の資格を持っているのだろうと言うと、そうとは限りません。
例えば、どう頑張ったところで、在来型ジャンボのキャプテンは、航空機の制限によりCAT III運航が許されません。よって、CAT III の資格を持っていても、何の役にも立ちません。
俺は定年までずっと在来型ジャンボでゆくから「そんな資格要らんよ」というベテランの機長もいる訳です。
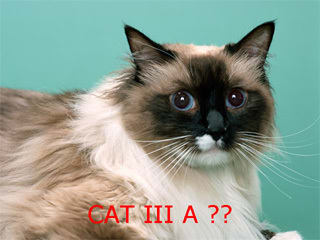
....回を重ねる度に内容希薄になっておりますが懲りずに次回[最終回-運用編]へと続く(予定)
Comment ( 0 ) | Trackback ( 0 )
| « 自動着陸への... | 自動着陸への... » |
| コメント |
| コメントはありません。 |
| コメントを投稿する |