朝日新聞で面白い記事を見つけました。
皆さんは「どどめ色」聞いたことありますか?
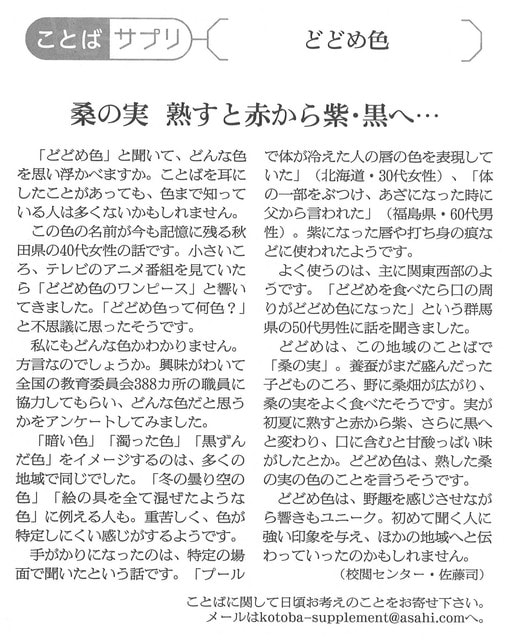
自分ではほとんど使いませんが、体が冷え唇が紫色になった様子を、実家の母はどどめ色と言っていたことを思い出しました。
この「どどめ色」が桑の実からきていることを知ってなるほど~と思いました。
私の趣味で撮っている植物図鑑に、桑の実の画像がありました。

桑の実は赤色から、熟すと紫色そして黒へと変わります。
残念ながら熟した画像はありませんが、桑の葉はカイコのエサです。
養蚕が盛んだった群馬県では「どどめ色」は熟した桑の実の色のことを言ったそうなんです。
実家のある鉾田市でも、私の小さい頃は桑畑がありました。
母がこの桑の実との関係を知っているかは聞いていませんが、甘酸っぱいという熟した桑の実を食して、どどめ色の唇を試してみようかな(笑)
皆さんは「どどめ色」聞いたことありますか?
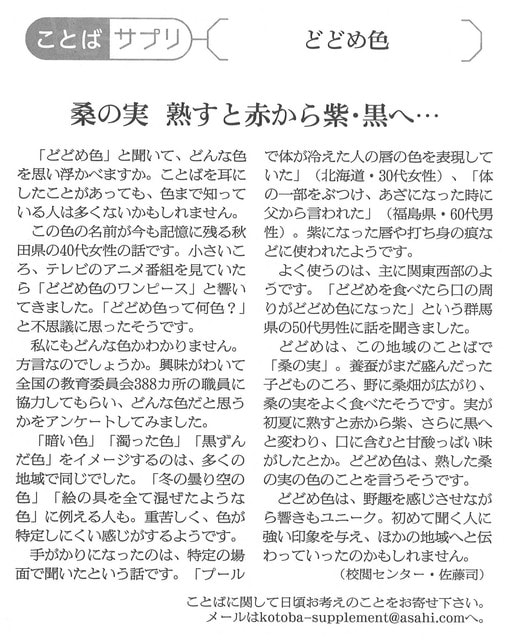
自分ではほとんど使いませんが、体が冷え唇が紫色になった様子を、実家の母はどどめ色と言っていたことを思い出しました。
この「どどめ色」が桑の実からきていることを知ってなるほど~と思いました。
私の趣味で撮っている植物図鑑に、桑の実の画像がありました。

桑の実は赤色から、熟すと紫色そして黒へと変わります。
残念ながら熟した画像はありませんが、桑の葉はカイコのエサです。
養蚕が盛んだった群馬県では「どどめ色」は熟した桑の実の色のことを言ったそうなんです。
実家のある鉾田市でも、私の小さい頃は桑畑がありました。
母がこの桑の実との関係を知っているかは聞いていませんが、甘酸っぱいという熟した桑の実を食して、どどめ色の唇を試してみようかな(笑)
























