餃子も食べるしピアノも弾くという会で、shigさんにミニレッスンをお願いしたのは、たった二段の曲、通称「太田胃散」。
 ←妙に緊張する曲です。
←妙に緊張する曲です。
確かに、胃がスーッと楽になりそうな(^^;; いい曲なんですが、これ人前で弾く勇気あります?? ないよね、ってわけで、この知られすぎた曲をいつかの発表会で弾くってのが、なんだか今の目標になっております。
内藤先生のレクチャー・コンサート後の懇親会のとき、shigさんが内藤先生に「こんど餃子の会でミニレッスンやるんですけど、アンダンテさんたら太田胃散がいいっていうんですよ~(意外とやっかいな曲ですよね的なニュアンスで)」とかいったら、内藤先生は、箸を置いてぴゅーとピアノのところに行って、「ペダルの使い方」が要注意であることを実演してみせてくださいました。
つまり、

スラーがかかってる「ミード#レシシシー」のところ、この楽譜(ヘンレ版)では「ド#」以降ひとつながりのペダルを踏むように書いてありますが、小節線のところでペダルを踏み変えてしまう人が、まま、いる。「ド#レシシ」「シー」というふうに。そうすると響きが台無しに…
という話だったんだけれど。私はむしろ、踏み変えるということを思いついてなくて、というか、楽譜でも踏みっぱなしだし、私が何枚も持っているCDでは、そんなところであからさまに踏み変えてるものはないし。
なのでちょっと、ピンと来てなかったんだけど、shigさんのミニレッスンではもっと詳しく聞けたのでよくわかった。
ペダルを踏み始めた瞬間の「ド#」は和音にない音なので、そこから踏みっぱなしにすると濁る。それを嫌って、踏み換えを指示した楽譜も出回っているのだ(shigさんが実物を見せてくれた)。なるほど。というか、濁ることを気にせず踏みっぱなししてた私ってのは、要するになーんにも考えないで弾いてたって話なんだけど(^^;;
それで、踏みっぱなしだと濁る、ぶちっと踏みかえると残念な演奏の出来上がり、ってことになると、どうするか。
ひとつは、左ペダルを踏んでおく、という案…濁りが気にならなくなる。けど、もっとクリアな音がいいなと思ったら(好みの問題かもしれないが)、どうしたらいいか。
もうひとつの案が、ペダルを細かく薄く、ちょい離す。うまく表現できないけど、踏んでるか踏まないかぎりぎりのところで、ゆらゆらゆらっと、濁りをゆすって飛ばすような雰囲気で。
「いろいろ試してみて」ということで、ペダル変えてみたらば。
あ、ちょっといいみたい♪ いい感じになった、と、聞いてる人も思ってるような気がする。
そのほかには、拍子感のこと(というのかな)。これ、三拍子の曲だけど、一拍目が強いのか? 三拍目が強いのか?
手がかりはいろいろある。あるけどこの場合どっちの手がかりもあって決まらないので(笑)
…はい実験。
一拍目強いバージョンと、三拍目強いバージョンで弾くように言われる。この曲、短いからいろんな実験やり放題である。
急にやろうとしても、ちょっと大げさで不自然になってしまう。自分で納得いってないというか。でも、その不自然な中でもその違いに耳を傾けてみると…
意外なことに、自分で「より」納得がいかず、「より」不自然に弾けたと思う三拍目強いバージョンのほうが、多数決では評判よかった。
なかなかおもしろい…
そういえば、自分で一番気になってるのは、スラーごとを1つの部分として、その複数の部分がつながっていく流れがいまいち悪いような、曲としてまとまって流れていないようなところ。今回のミニレッスンではそこまで話がいかなかったので、またの機会に。
にほんブログ村 ピアノ ←ぽちっと応援お願いします
にほんブログ村 ヴァイオリン ←こちらでも
にほんブログ村 中高一貫教育
確かに、胃がスーッと楽になりそうな(^^;; いい曲なんですが、これ人前で弾く勇気あります?? ないよね、ってわけで、この知られすぎた曲をいつかの発表会で弾くってのが、なんだか今の目標になっております。
内藤先生のレクチャー・コンサート後の懇親会のとき、shigさんが内藤先生に「こんど餃子の会でミニレッスンやるんですけど、アンダンテさんたら太田胃散がいいっていうんですよ~(意外とやっかいな曲ですよね的なニュアンスで)」とかいったら、内藤先生は、箸を置いてぴゅーとピアノのところに行って、「ペダルの使い方」が要注意であることを実演してみせてくださいました。
つまり、

スラーがかかってる「ミード#レシシシー」のところ、この楽譜(ヘンレ版)では「ド#」以降ひとつながりのペダルを踏むように書いてありますが、小節線のところでペダルを踏み変えてしまう人が、まま、いる。「ド#レシシ」「シー」というふうに。そうすると響きが台無しに…
という話だったんだけれど。私はむしろ、踏み変えるということを思いついてなくて、というか、楽譜でも踏みっぱなしだし、私が何枚も持っているCDでは、そんなところであからさまに踏み変えてるものはないし。
なのでちょっと、ピンと来てなかったんだけど、shigさんのミニレッスンではもっと詳しく聞けたのでよくわかった。
ペダルを踏み始めた瞬間の「ド#」は和音にない音なので、そこから踏みっぱなしにすると濁る。それを嫌って、踏み換えを指示した楽譜も出回っているのだ(shigさんが実物を見せてくれた)。なるほど。というか、濁ることを気にせず踏みっぱなししてた私ってのは、要するになーんにも考えないで弾いてたって話なんだけど(^^;;
それで、踏みっぱなしだと濁る、ぶちっと踏みかえると残念な演奏の出来上がり、ってことになると、どうするか。
ひとつは、左ペダルを踏んでおく、という案…濁りが気にならなくなる。けど、もっとクリアな音がいいなと思ったら(好みの問題かもしれないが)、どうしたらいいか。
もうひとつの案が、ペダルを細かく薄く、ちょい離す。うまく表現できないけど、踏んでるか踏まないかぎりぎりのところで、ゆらゆらゆらっと、濁りをゆすって飛ばすような雰囲気で。
「いろいろ試してみて」ということで、ペダル変えてみたらば。
あ、ちょっといいみたい♪ いい感じになった、と、聞いてる人も思ってるような気がする。
そのほかには、拍子感のこと(というのかな)。これ、三拍子の曲だけど、一拍目が強いのか? 三拍目が強いのか?
手がかりはいろいろある。あるけどこの場合どっちの手がかりもあって決まらないので(笑)
…はい実験。
一拍目強いバージョンと、三拍目強いバージョンで弾くように言われる。この曲、短いからいろんな実験やり放題である。
急にやろうとしても、ちょっと大げさで不自然になってしまう。自分で納得いってないというか。でも、その不自然な中でもその違いに耳を傾けてみると…
意外なことに、自分で「より」納得がいかず、「より」不自然に弾けたと思う三拍目強いバージョンのほうが、多数決では評判よかった。
なかなかおもしろい…
そういえば、自分で一番気になってるのは、スラーごとを1つの部分として、その複数の部分がつながっていく流れがいまいち悪いような、曲としてまとまって流れていないようなところ。今回のミニレッスンではそこまで話がいかなかったので、またの機会に。
にほんブログ村 ピアノ ←ぽちっと応援お願いします
にほんブログ村 ヴァイオリン ←こちらでも
にほんブログ村 中高一貫教育










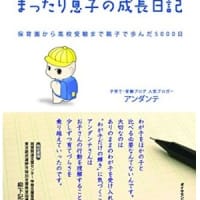











なんだ言ってくれればよかったのに^^;
もうひとつ、話そうと思っててすっかり忘れてた題材もあったりしますのでまたの機会に是非。
そりゃそうですよね。
なんかテンパッててそれどころじゃなく(何)
またの機会にぜひ。
今習っているのがショパンのノクターン(No.2)(^^ゞ
自分が選んだのだけど、有名過ぎて譜読み段階が恥ずかしいのなんのって!また譜読み遅いのがさらにツライ…(T_T)
太田胃散を衆人の前で披露できるアンダンテさんに拍手!!です (^^)/
> 有名過ぎて譜読み段階が恥ずかしいのなんのって!
いやいやいや(^^;;
ここはぐっと開き直って。
有名曲って、ぶっちゃけよくできてる曲なので、楽しめますよね。
> 太田胃散を衆人の前で披露できるアンダンテさんに拍手!!です (^^)/
いや披露するのを目指してるんです…
今回はほんのミニレッスン。