ショパンマズルカのコピー譜を作り直すにあたって、改めて譜面をよく見てみると、自分がふだんいかにいい加減に譜読みしてるかってことがよくわかるんだけど…
 ←見始めるときりがないからほどほどに
←見始めるときりがないからほどほどに
ピアノ弾いてるときは、弾くことに必死。
ピアノが目の前にないときは、楽譜も開かない。
ってわけで、しっかり見ることが案外少ない(爆)もので、いろいろと見落としてます。コピー譜を作る都合で、ピアノ弾いてないときにも楽譜を見るってのは、悪くないかもしれません。
モツソナの「原典版」とかだと、強弱とかペダルとかそういう記入がなくてすっからかんだけど、
ショパンの楽譜はいろいろとたくさんの情報が盛り込まれています。
ショパンさんは、当たり前だけどパソコン上で楽譜を書いてコピペが使えたりしたわけじゃないので、
それこそペンにインクをつけていっこずつ記入するしかない。
それだけ盛り盛りするにあたっては、それぞれイイタイコトがあって書き入れたはず。
ペダルの指示とかも、むっちゃ気合いが入ってたって話は聞くので、できることならば意を汲んでさしあげたいとは思うんだけれど、「ショパンの楽譜のとおりに踏む」ってことは存外難しいものです。
(ダンパー)ペダルの記号には、ペダルを踏む記号と、離す記号の二種類があるけど、
ありていにいって、すべてをショパンが書いたこの記号のとおりに(だけ)踏んでいるピアニストはいないと思われます。
まずひとつには、ペダルの記号がないまま続くゾーンも、まるごとペダル活用なしがいいとは考えられないので、個々人の裁量によって足しているということ。べたーっとは踏まないところで、細かすぎるところはわざわざ書かないとか。あるいは、わかりきってるから書かないとか、そんな感じで。
それはまぁ、アマプロ問わずみんなやってると思うし、そもそもショパンさんだって踏んだだろうよね。とはいえ、どのくらい踏むかは、人によってずいぶん違うだろうけど。
もっと謎なのが、ペダルを離す記号。離すほうの記号は、書かない派の作曲家さんもけっこういるけど、ショパンはとにかく律儀にこの記号を書きます。書いてはあるけど、「ほんとにここでペダル離しちゃうの?」というところも多い。
ペダルを離す記号が、次のペダルの記号にものすごく近い場合は、今でいうシンコペーション・ペダルというか、瞬間的に離して踏む感じで納得しやすいと思いますが、
ペダルを離す記号が、次のペダルの記号までまだ間があるところに書いてあるときは、不安になると思います…
「ショパンの音楽記号 -その意味と解釈-(セイモア・バーンスタイン)」の中では、本の半分以上に渡ってこれに関連する考察をえんえんと展開してあって、もう読めば読むほどわからなくなるんですけど、結局のところ、譜例を子細に検討したあげく、アスタリスク(ペダル離す記号)を無視して踏んでおき、次のペダル記号が来たら踏みかえるようにすべきという結論になっているものが多いんです。
そして、締めくくりには
「私の意見として述べれば、ペダル記号については細心の注意を払うべきであり、大部分のアスタリスクについてはそうする必要がない。」
となっています。つまり、ペダル踏む記号にはショパンの強い意志が含まれていてそれには(ほぼ)そのまま従うべきであり、一方、ペダル離す記号の大部分にはあんまり意味がない。
…ほんとなんでしょうか? そんなに意味ないものをわざわざこんなに書きますかね??
私が今、弾いているマズルカOp56-3では、とりわけ、ペダル離す記号から次のペダル踏む記号までに間があることが多いんですが、そのそれぞれ、たとえば休符を休符として聞かせたいとか、なんらかの意思が感じられるようなところが多いんですよ。(よくわかんないこともあるけど)
ひとまずはペダル離す記号にも意味があると思っておいたほうがよさそうに見えるんです。
それでうまくいかなければ、いったん離したあと、次のペダル記号までにまた目立たないペダルを使ったりすることを考え、
それでもうまくいかなければ、アスタリスクでペダルを離さないことを考える(セイモアさん式)、
って順番でどうかなぁ??
…ショパンさんがそんなに無意味なインク(と時間)を使ったというのはね…どうも納得できないんだけど。
にほんブログ村 ピアノ ←ぽちっと応援お願いします
にほんブログ村 ヴァイオリン ←こちらでも
にほんブログ村 中高一貫教育

「はじめての中学受験 第一志望合格のためにやってよかった5つのこと~アンダンテのだんだんと中受日記完結編」ダイヤモンド社 ←またろうがイラストを描いた本(^^)
←またろうがイラストを描いた本(^^)

「発達障害グレーゾーン まったり息子の成長日記」ダイヤモンド社
(今回もイラストはまたろう)
ピアノ弾いてるときは、弾くことに必死。
ピアノが目の前にないときは、楽譜も開かない。
ってわけで、しっかり見ることが案外少ない(爆)もので、いろいろと見落としてます。コピー譜を作る都合で、ピアノ弾いてないときにも楽譜を見るってのは、悪くないかもしれません。
モツソナの「原典版」とかだと、強弱とかペダルとかそういう記入がなくてすっからかんだけど、
ショパンの楽譜はいろいろとたくさんの情報が盛り込まれています。
ショパンさんは、当たり前だけどパソコン上で楽譜を書いてコピペが使えたりしたわけじゃないので、
それこそペンにインクをつけていっこずつ記入するしかない。
それだけ盛り盛りするにあたっては、それぞれイイタイコトがあって書き入れたはず。
ペダルの指示とかも、むっちゃ気合いが入ってたって話は聞くので、できることならば意を汲んでさしあげたいとは思うんだけれど、「ショパンの楽譜のとおりに踏む」ってことは存外難しいものです。
(ダンパー)ペダルの記号には、ペダルを踏む記号と、離す記号の二種類があるけど、
ありていにいって、すべてをショパンが書いたこの記号のとおりに(だけ)踏んでいるピアニストはいないと思われます。
まずひとつには、ペダルの記号がないまま続くゾーンも、まるごとペダル活用なしがいいとは考えられないので、個々人の裁量によって足しているということ。べたーっとは踏まないところで、細かすぎるところはわざわざ書かないとか。あるいは、わかりきってるから書かないとか、そんな感じで。
それはまぁ、アマプロ問わずみんなやってると思うし、そもそもショパンさんだって踏んだだろうよね。とはいえ、どのくらい踏むかは、人によってずいぶん違うだろうけど。
もっと謎なのが、ペダルを離す記号。離すほうの記号は、書かない派の作曲家さんもけっこういるけど、ショパンはとにかく律儀にこの記号を書きます。書いてはあるけど、「ほんとにここでペダル離しちゃうの?」というところも多い。
ペダルを離す記号が、次のペダルの記号にものすごく近い場合は、今でいうシンコペーション・ペダルというか、瞬間的に離して踏む感じで納得しやすいと思いますが、
ペダルを離す記号が、次のペダルの記号までまだ間があるところに書いてあるときは、不安になると思います…
「ショパンの音楽記号 -その意味と解釈-(セイモア・バーンスタイン)」の中では、本の半分以上に渡ってこれに関連する考察をえんえんと展開してあって、もう読めば読むほどわからなくなるんですけど、結局のところ、譜例を子細に検討したあげく、アスタリスク(ペダル離す記号)を無視して踏んでおき、次のペダル記号が来たら踏みかえるようにすべきという結論になっているものが多いんです。
そして、締めくくりには
「私の意見として述べれば、ペダル記号については細心の注意を払うべきであり、大部分のアスタリスクについてはそうする必要がない。」
となっています。つまり、ペダル踏む記号にはショパンの強い意志が含まれていてそれには(ほぼ)そのまま従うべきであり、一方、ペダル離す記号の大部分にはあんまり意味がない。
…ほんとなんでしょうか? そんなに意味ないものをわざわざこんなに書きますかね??
私が今、弾いているマズルカOp56-3では、とりわけ、ペダル離す記号から次のペダル踏む記号までに間があることが多いんですが、そのそれぞれ、たとえば休符を休符として聞かせたいとか、なんらかの意思が感じられるようなところが多いんですよ。(よくわかんないこともあるけど)
ひとまずはペダル離す記号にも意味があると思っておいたほうがよさそうに見えるんです。
それでうまくいかなければ、いったん離したあと、次のペダル記号までにまた目立たないペダルを使ったりすることを考え、
それでもうまくいかなければ、アスタリスクでペダルを離さないことを考える(セイモアさん式)、
って順番でどうかなぁ??
…ショパンさんがそんなに無意味なインク(と時間)を使ったというのはね…どうも納得できないんだけど。
にほんブログ村 ピアノ ←ぽちっと応援お願いします
にほんブログ村 ヴァイオリン ←こちらでも
にほんブログ村 中高一貫教育

「はじめての中学受験 第一志望合格のためにやってよかった5つのこと~アンダンテのだんだんと中受日記完結編」ダイヤモンド社

「発達障害グレーゾーン まったり息子の成長日記」ダイヤモンド社
(今回もイラストはまたろう)










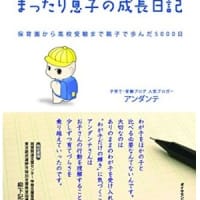











その変わり響きの余韻があるので、基本、指でのレガートと現代ピアノの特性を考えて、プラス味付けがすると良いですね。
皆さん、ペダルがないと不安になる様です。
でも長いフレーズ、ペダルの指示がないところも多いです。
そこを指示通り、ペダルなしで丁寧に指で表現すると、時にささやき声の様な息遣いを感じます(*^^*)とても素敵で、安易に踏まないで欲しいと思う事が多いです。
打鍵や音色も当然問われますので、大変ですが。
ペダルを離す目的には、例えば低音を残したくない、響きを濁らせたくない、等々様々ですが、ショパンの場合、更に躍動感、息遣い、等々様々な表現をペダルで指示しています。
エオリアン・ハープの躍動感は素晴らしいですよね(*^^*)
ショパンがどう弾いて欲しかったのか、ペダル記号もそう、スラー、強弱、各種指示、楽譜はショパンの手紙の様なもので、読譜している時にショパンと対話している様で幸せです(*^^*)
ショパンが書いたペダル記号は、当時のピアノを前提にしてたわけだから、ほんとうは書かれたとおりをそのピアノで試してみて、「そんな響きを求めて」現代ピアノで工夫するというのが正攻法なのかもしれませんが…
そうしょっちゅう弾かせてもらうこともできず(といいつつ弾かせてもらうこと前提)試すにしても技術が伴わず迷宮入りしたりと、なかなかたいへんです。
> ペダルを離す目的には、…
ほんと、一端を垣間見ただけですが楽しいです。楽譜といったら全音一択、ピアノといったらヤマハ一択の世界から(笑)めっちゃ広がってきて幸せ(^-^)