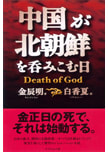同僚のT先生、この8月から大連に赴任しました。2日前に電話があり、無事入国できたとのこと。これからT先生は、たくさんのエピソードを作っていくことでしょう。
さて、これまた同僚のS先生が「読みますか?」といって貸してくれた文庫本。
須藤みか『上海発!新・中国的流儀70』(講談社+α文庫、2007年6月)
須藤氏は、中国国営出版社に勤務したことがあり、中国の大学院で新聞学の修士を取得した、フリーのライターのようです。そして現在も上海に在住のようで、上海を中心とした生活のあれこれについて発表してきたものを一冊にまとめたのが本書です。
大連滞在中、学生の何人かが「卒業後は上海で働きたい」と話していましたので、中国の人々の中には、北京より上海にあこがれる人がいるということでしょう。また大連滞在中、「北京は政治の中心、上海は経済の中心です」という話も聞きましたので、働くなら上海、という考え方があってもおかしくはないでしょう。
小生、上海には行ったことがありません(というよりまだ見ぬ中国の方が多いのですが)。上海出身の教え子もいて「ぜひ遊びに来てください」といわれたのですが、テレビ番組で紹介されている上海は、あまりに東京や大阪のような日本の大都会然として、旅行で訪れようという気になれません。
ところで、須藤氏の本には、上海の社会、ビジネス、在留邦人などにまつわるエピソードが短い文章で70本、掲載されています。
その一つ一つを紹介するのもしんどいので(苦笑)、内容はお読みいただくとして、読みながら思ったことは『やっぱり上海はビジネスの拠点であり、大都会だ』ということでした。つまりは東京などと変わらないわけです。
新しく知ったことも数多くありましたが、一方で大連での生活を振り返り、『あり得る話だよな』と思ってしまいます。
これから中国(とくに上海)を訪れたい、と思っている人には、予備知識として知っていても悪くはない話で、語調も柔らかいですので、気軽に読める本でしょう。
というわけで、本箱へ(もちろん、現物はS先生に返却します)。
さて、これまた同僚のS先生が「読みますか?」といって貸してくれた文庫本。
須藤みか『上海発!新・中国的流儀70』(講談社+α文庫、2007年6月)
須藤氏は、中国国営出版社に勤務したことがあり、中国の大学院で新聞学の修士を取得した、フリーのライターのようです。そして現在も上海に在住のようで、上海を中心とした生活のあれこれについて発表してきたものを一冊にまとめたのが本書です。
大連滞在中、学生の何人かが「卒業後は上海で働きたい」と話していましたので、中国の人々の中には、北京より上海にあこがれる人がいるということでしょう。また大連滞在中、「北京は政治の中心、上海は経済の中心です」という話も聞きましたので、働くなら上海、という考え方があってもおかしくはないでしょう。
小生、上海には行ったことがありません(というよりまだ見ぬ中国の方が多いのですが)。上海出身の教え子もいて「ぜひ遊びに来てください」といわれたのですが、テレビ番組で紹介されている上海は、あまりに東京や大阪のような日本の大都会然として、旅行で訪れようという気になれません。
ところで、須藤氏の本には、上海の社会、ビジネス、在留邦人などにまつわるエピソードが短い文章で70本、掲載されています。
その一つ一つを紹介するのもしんどいので(苦笑)、内容はお読みいただくとして、読みながら思ったことは『やっぱり上海はビジネスの拠点であり、大都会だ』ということでした。つまりは東京などと変わらないわけです。
新しく知ったことも数多くありましたが、一方で大連での生活を振り返り、『あり得る話だよな』と思ってしまいます。
これから中国(とくに上海)を訪れたい、と思っている人には、予備知識として知っていても悪くはない話で、語調も柔らかいですので、気軽に読める本でしょう。
というわけで、本箱へ(もちろん、現物はS先生に返却します)。