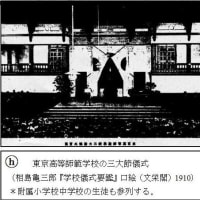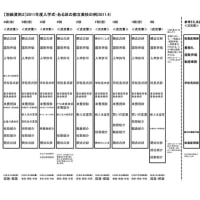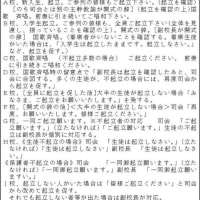◎青木茂雄氏の『虎の尾を踏む男達』論
先月二五日から二七日まで、黒澤明監督の映画『虎の尾を踏む男達』を取り上げた。二七日に、映画評論家の青木茂雄氏に電話すると、ブログを読んだ上で、コメントを送るということであった。そのコメントが、一昨日、メールで届いた。コメントというより、ひとつの論文になっている。
ご本人の了解を得て、以下に紹介したい。
『虎の尾を踏む男達』(1945年・東宝、1952年公開)について 青木茂雄
礫川氏によって、このブログで採り上げられた『虎の尾を踏む男達』(1945年・東宝、1952年公開)について一言。
中村秀之『敗者の身ぶり―ポスト占領期の日本映画』で同作品の製作時期について、通説との違いについて触れられている。『虎の尾を踏む男達』(以下、『虎の尾』と略)は、作品の企画も含めて、1945年8月15日以降につくられた、と言う。これまでの通説は、戦争末期の企画が進められ、製作中に8.15を迎えたとしている。
私は中村氏のその著書を読んでいないので、礫川氏の引用だけによるが、同書は『虎の尾』戦後構想・製作説の根拠として、①製作主任の宇佐美仁の談話によれば、黒澤が能の「安宅」の映画化を思いついたのが8月15日である、という点、②源義経に扮した仁科周芳の1994年5月10日における文芸坐でのトークショウでの、「敗戦で東京にもどったあと『虎の尾を踏む男達』のクランクインがあったが、それが8月20日」、との発言、をあげており、これらを根拠として、『虎の尾』は戦後になって構想され製作が開始された作品だとしている。確かに通説とは違う。
私の手元にある文献・資料には同作品の製作時期や製作事情についてどのように書かれているか、調べてみた。
黒澤の自伝『蝦蟇の油』(1984年初版・岩波書店)によると次のようにある。
《『虎の尾を踏む男達』は、『どっこい、この槍』が撮影不可能となったので、その代案として急遽企画されたものである。
この案は、『勧進帳』を基にして、全体の構成もそのまま、大河内の弁慶もそのままで、ただエノケンのために新しく強力の役を書き加えるだけだから、2日もあれば脚本は書ける、と私が申し出たので、上映作品が不足して困っていた会社は渡りに舟だった。また、セットは一つ、ロケは、当時、撮影所の裏門の外から続いていた御料林で済ます、というのだから会社は喜んだ。
ところが、それが、獲らぬ狸の皮算用で、とんでもない事になる。
この『虎の尾―』の撮影が順調に進んでいるうちに、日本は戦争に負けて、アメリカ軍が進駐し、わたしのセットにも、アメリカの兵隊が時々顔を見せるようになった。》
このあと自伝では、アメリカ兵が面白がってロケの見学、ひやかしに次々に訪れたこと、やがて高級将校に交じって映画監督ジョン=フォードまで見学にやって来たなどが書かれ、そして占領下の日本の内務省の下の検閲官が来て、作品に「この“虎の尾”というのは何だ」とか「日本の古典芸能である歌舞伎の“勧進帳”の改悪であり、それを愚弄するものだ」とか難癖をつけて、とうとう検閲官が撮影中の日本映画の報告書の中から『虎の尾』を削除したため、占領下の未報告の非合法作品として葬り去られた、と黒澤は書いている。 どうやら、通説となっていた『虎の尾』が主従関係の絶対を説いた封建思想のためにGHQの許可が降りなかったのではなく、その逆で日本の検閲官が日本の伝統文化に対する“不敬”のために、闇に葬ろうとしたというのが黒澤自身によれば真相らしい。
ところで“定説”はどうかというと、国立近代美術館フィルムセンター発行の冊子『フィルムセンター74 日本映画史研究2東宝映画50年の歩み①』(1982年10月発行)所収の『虎の尾を踏む男達』の項目には次のようにある。
《敗戦の色濃い時期に制作開始されたこの作品は、当局の検閲を通すには忠君物であることが容易であったろうが、終戦を迎えて占領軍の検閲下に入り、当時の映画政策としては時代劇や歌舞伎に題材をとったものは封建的と見られ、完成後オクラ入りとなり、講和条約締結後の1952年に公開されるに至った映画である。》
おそらくこの文章の執筆者は、映画評論家でありすぐれた映画史研究者でもある佐藤忠男氏であろうと思う。黒澤明についての最初の本格的な研究書である佐藤氏の『黒澤明の世界』(1969年)では、『虎の尾を踏む男達』は戦争末期の映画として位置付けられており、次のように解説している。
《1945年8月、日本が降伏するまぎわの社会のすべてがもっとも混乱していたとき、黒澤明は、喜劇味の豊かな小品の劇映画『虎の尾を踏む男達』をつくっていた。
この映画は能の『安宅』と、それを脚色した『勧進帳』にもとづくもので、主君にたいする家来の忠義を扱っているという点で、かろうじて当時の検閲の方針と矛盾しなかったとはいうものの、戦争協力の意味はほとんどなく、純粋の娯楽映画であり、また、当時の苛酷な社会情勢の中においては驚くべきことといわなければならないが、古典様式のパロディ化という、当時誰もやったことのない形式上の実験を試みた映画でもあった。》
佐藤氏は、戦争末期にこれだけ自由な実験精神あふれる作品を製作した黒澤明を高く評価している。
また、現時点でも最も優れた黒澤明の包括的な研究書の一つと言って良いドナルド=リチーの『黒澤明の映画』(1979年、三木宮彦訳)も通説の通り、「映画の撮影がすべて終わったとき、偶然にも第2次世界大戦のほうも終わりを告げた」と書いている。
さて、この作品の製作時期のことであるが、さきにあげた黒澤明の自伝では「撮影が順調に進んでいるうちに、日本は戦争に負けて、アメリカ軍が進駐し」とあるところから黒澤は明らかに、戦争中に撮影を開始したと書いていることは間違いない。しかし、自伝のこのあたりのところは、読んでみると時間の前後関係が錯綜した文章となっていて、この箇所も「日本は戦争に負けて」の句も前の「撮影が順調に進んでいるうちに」に係るのか、それとも後の「アメリカ軍が進駐し」に係るかとではニュアンスが微妙に違ってくる。
さきにあげた「2日もあれば脚本は書ける、と私が申し出たので、上映作品が不足して困っていた会社は渡りに舟だった」という箇所も、これがいつの時点での話なのかということは書いていない。「2日もあれば」とか、「上映作品が不足して」などは、8.15直後のことを思わせる書き方である。もしかしたら、黒澤自身も記憶が不確かだったのではないのか、と思わせるものである。
これまでの証言はすべて製作当事者のものである。ところで、第三者の証言はどうであろうか。東宝で長く助監督をつとめ、後にシナリオライターとなった廣澤榮氏は『日本映画の時代』(1990年、岩波同時代ライブラリー)の中で、この映画の撮影は7月下旬から始まっていたと、次のように証言している。
《わたしが復員して東宝撮影所へ出社したのは、敗戦の日から5日後の8月20日である。(略)このとき私は21歳だった。この未曾有の混迷の中でどうしたらいいかわからず、久方ぶりに職場に戻ってきたのである。
ところが、撮影所へやってきて驚いた。なんと第1ステージでは撮影をやっていたのである。
ライトが煌々と輝き、ドーランを塗った俳優たちやスタッフが気ぜわしく大声で叫びながら走り回っている―私はその瞬間、なにかまるで別の世界にやってきたように思った。 撮影していたのは黒澤明監督の『虎の尾を踏む男達』であった。そしてステージ一杯に安宅の関のセットが組まれ、山伏姿の大河内伝次郎や榎本健一が談笑していた。
そのとき私はスタッフの中で誰か顔見知りをつかまえて聞いている。それが誰だったかは思い出せないが、その男は『虎の尾』は7月下旬からクランクしている。それが敗戦で一時中断したが、「やりかけた仕事だからやっていまうのだ」という。そして「もう空襲なんかないから仕事がやりいい」などという。その男の顔は忘れたが、その声がとてもいきいきしていたことが記憶に残っている。》
内容の具体性から言って、この廣澤の証言には信憑性があると私は思う。あきらかに『虎の尾を踏む男達』は戦争末期に企画され撮影が開始されたものである、と見て間違いない。しかし、中断され、本格的な製作の開始はやはり8月15日以降であり、その日以降に大幅な企画の変更も行われたに違いない。冒頭の制作主任の宇佐美仁の談話や仁科周芳のトークも、事実上はまったく新しい作品として取り組まれたことを示している。黒澤の「2日もあれば脚本は書ける」という発言も、正しくは「2日もあれば脚本は書き直せる」ではなかったか。脚本が命である黒澤にとって、2日で脚本を完成させる、などとうていあり得ない話だ。
廣澤が偶然にも遭遇したのは8月20日の撮影の本格再始動の日の光景だった。それは感動的な光景だったに違いない。“また始まっている”、それは戦後日本社会の始動の日とも重なる。
「安宅の関」での大河内弁慶による「勧進帳」の読み上げのシーンも、そのような状況のもとで撮影されたものと思われる。
『虎の尾を踏む男達』はまぎれもなく、戦後日本映画の最初の作品である。
ラストシーンの、酔いから醒めて、前方を見渡すエノケン強力、そしてそこには誰もいない草原、そのエノケンの姿に敗戦で茫然自失する自分自身を重ね合わす、おそらく完成直後に公開されれば、そのようにして鑑賞されたであろう。しかし、そのように鑑賞されるためには、幸か不幸か公開までの7年間はあまりにも長すぎたのである。
*このブログの人気記事 2015・3・5
- 鈴木貫太郎を蘇生させた夫人のセイキ術
- 石原莞爾がマーク・ゲインに語った日本の敗因
- 「仏教者の戦争責任」を問い続ける柏木隆法さん
- かつてない悪条件の戦争をなぜ始めたか(鈴木貫太郎)
- 憲兵はなぜ渡辺錠太郎教育総監を守らなかったのか
- 古畑種基と冤罪事件
- 神社祭式と行事作法に関する用語とその読み方
- 伊藤博文、ベルリンの酒場で、塙次郎暗殺を懺悔
- なぜ岡田啓介首相は、救出されたあと姿を隠したのか
- 蓑田胸喜による日蓮批判と国神不敬事件