親会社のGMからも、スウェーデン政府からも支援が期待できず、資金繰りを急速に悪化させていくSAAB(サーブ)。しかも、昨日の暗いニュースを聞いて、さぁこれからSAABを買おう、と思う消費者はほとんどいなくなってしまっただろう。ブランド名としても全く落ちてしまった。

しかし、すぐに倒産や工場閉鎖に向かうわけではないようだ。希望の光も、わずかだが残されている。
それは、会社更生という手続きだ。SAABとしては、まずこの手続きを使って経営再建を試みた上で、それでもだめなら、倒産や工場閉鎖といった手続きに移る構えのようだ(ただし、これも現在、SAAB内で協議が続けられており、どうなるかまだ分からない。)
会社更生の申請は、債務の返済が不可能になった企業が地方裁判所に提出する。すると、裁判所は管財人を指名し、この管財人の仲介のもとで、債権者とSAABの間で債務削減のための交渉が行われることになる。債権者とは、この場合、銀行や下請け業者。下請け業者は納入した部品の代金をSAABから後払いで受け取っているため、その代金がちゃんと支払われるまでは「SAABに対して債権を持っている」ことになる。
たとえば、債権の50%を帳消しにしましょう、といった合意が結ばれることになる。債権者(銀行や下請け業者)は債権の一部を手放してしまうことになるが、それでも彼らにとっては有利となりうる。なぜなら、もしSAABが倒産してしまえば、債権を100%放棄せざるを得ないからだ。だから、適当なところで妥協を迫られることになる。
一方、SAABのほうも、企業の再建計画を提示しなければならない。どのようにして企業の収益性を回復させるつもりなのか。業務分野の統廃合、従業員のリストラ、組織の再編成…。SAABをスリムにしていかなければならない。そして、生まれる新生SAABは現在のSAABとは大きく様変わりすることになる。そして、買い手を見つけ売却されることになる。
しかし、これもうまく行けば、の話。新生SAABが誕生するまでに3~12ヶ月かかる。そして、買い手が現れなければならない。それに、それ以前の段階で「収益性回復プラン」が示せず、結局は倒産、ということもありうる。専門家の中には「政府が全く手を貸してくれないのであれば、会社更生すら無理」と言う人もいる。
会社更生が失敗して倒産となれば、従業員はすべて解雇。債権者(銀行や下請け業者)は債権をすべて失う。そして、新たな倒産をドミノ倒しのように生み出しかねない。
もしくは、倒産ではなく、工場閉鎖という手もある。しかし、解散だと膨大な費用がかかる。SAAB車を扱う販売業者や修理工場、下請け業者などとの契約を一つ一つ解消していかなければならないからだ。
――――――

SAABの工場があるトロルヘッタン(Trollhättan)やその周辺地域は、これまで数年にわたってスウェーデン政府が、様々な投資をしてきた。ヨーテボリに本拠地を置くVolvoや周辺の自動車関連産業とともに「自動車産業クラスター」の形成を促進するためだ>。特定の企業や産業にお金をつぎ込むとEUの原則に抵触するため、あくまでもインフラ整備や教育、研究開発への支援、という形をとってきた。
- 自動車産業に従事する労働者の能力水準の向上を目的とした教育投資
- トロルヘッタン(Trollhättan)とウッデヴァッラ(Uddevalla)間の国道の高速道路化
- トロルヘッタンとヨーテボリ間の国道の4車線化
- トロルヘッタンとヨーテボリ間の鉄道の複線化。貨物輸送力の拡大。
- トロルヘッタンにある地方大学「University West」と自動車産業との連携強化。研究開発における連携および、自動車産業の求めるエンジニアの育成。
- 環境に良い車「Gröna bil」プロジェクトの延長

これらの投資プログラムが発表されたのは、2004年の暮れ。当時は、SAAB車の生産をトロルヘッタン工場で行うのか、それともドイツにあるOpelの工場で行うのか、を巡って、GM内で議論が続いていた。政府としてはSAAB車の生産のために、是非ともトロルヘッタン工場を選んで欲しかった。だから、トロルヘッタンやヨーテボリを含む「スウェーデン西部地域」の「自動車産業クラスター」を強化し、魅力を向上させるために、このような投資プログラムを行ったきたのだった。
当時、2004年の新聞記事を読み返しながら「こんな時代もあったな」と、何だか懐かしくなってしまった。SAABがなくなってしまえば、高速道路とか4車線化とか、鉄道の複線化といったせっかくの投資も報われないことになってしまう・・・。
Utbildning ska rädda Trollhättan (Dagens Nyheter:2004-11-02)

しかし、すぐに倒産や工場閉鎖に向かうわけではないようだ。希望の光も、わずかだが残されている。
それは、会社更生という手続きだ。SAABとしては、まずこの手続きを使って経営再建を試みた上で、それでもだめなら、倒産や工場閉鎖といった手続きに移る構えのようだ(ただし、これも現在、SAAB内で協議が続けられており、どうなるかまだ分からない。)
会社更生の申請は、債務の返済が不可能になった企業が地方裁判所に提出する。すると、裁判所は管財人を指名し、この管財人の仲介のもとで、債権者とSAABの間で債務削減のための交渉が行われることになる。債権者とは、この場合、銀行や下請け業者。下請け業者は納入した部品の代金をSAABから後払いで受け取っているため、その代金がちゃんと支払われるまでは「SAABに対して債権を持っている」ことになる。
たとえば、債権の50%を帳消しにしましょう、といった合意が結ばれることになる。債権者(銀行や下請け業者)は債権の一部を手放してしまうことになるが、それでも彼らにとっては有利となりうる。なぜなら、もしSAABが倒産してしまえば、債権を100%放棄せざるを得ないからだ。だから、適当なところで妥協を迫られることになる。
一方、SAABのほうも、企業の再建計画を提示しなければならない。どのようにして企業の収益性を回復させるつもりなのか。業務分野の統廃合、従業員のリストラ、組織の再編成…。SAABをスリムにしていかなければならない。そして、生まれる新生SAABは現在のSAABとは大きく様変わりすることになる。そして、買い手を見つけ売却されることになる。
しかし、これもうまく行けば、の話。新生SAABが誕生するまでに3~12ヶ月かかる。そして、買い手が現れなければならない。それに、それ以前の段階で「収益性回復プラン」が示せず、結局は倒産、ということもありうる。専門家の中には「政府が全く手を貸してくれないのであれば、会社更生すら無理」と言う人もいる。
会社更生が失敗して倒産となれば、従業員はすべて解雇。債権者(銀行や下請け業者)は債権をすべて失う。そして、新たな倒産をドミノ倒しのように生み出しかねない。
もしくは、倒産ではなく、工場閉鎖という手もある。しかし、解散だと膨大な費用がかかる。SAAB車を扱う販売業者や修理工場、下請け業者などとの契約を一つ一つ解消していかなければならないからだ。
――――――

SAABの工場があるトロルヘッタン(Trollhättan)やその周辺地域は、これまで数年にわたってスウェーデン政府が、様々な投資をしてきた。ヨーテボリに本拠地を置くVolvoや周辺の自動車関連産業とともに「自動車産業クラスター」の形成を促進するためだ>。特定の企業や産業にお金をつぎ込むとEUの原則に抵触するため、あくまでもインフラ整備や教育、研究開発への支援、という形をとってきた。
- 自動車産業に従事する労働者の能力水準の向上を目的とした教育投資
- トロルヘッタン(Trollhättan)とウッデヴァッラ(Uddevalla)間の国道の高速道路化
- トロルヘッタンとヨーテボリ間の国道の4車線化
- トロルヘッタンとヨーテボリ間の鉄道の複線化。貨物輸送力の拡大。
- トロルヘッタンにある地方大学「University West」と自動車産業との連携強化。研究開発における連携および、自動車産業の求めるエンジニアの育成。
- 環境に良い車「Gröna bil」プロジェクトの延長

これらの投資プログラムが発表されたのは、2004年の暮れ。当時は、SAAB車の生産をトロルヘッタン工場で行うのか、それともドイツにあるOpelの工場で行うのか、を巡って、GM内で議論が続いていた。政府としてはSAAB車の生産のために、是非ともトロルヘッタン工場を選んで欲しかった。だから、トロルヘッタンやヨーテボリを含む「スウェーデン西部地域」の「自動車産業クラスター」を強化し、魅力を向上させるために、このような投資プログラムを行ったきたのだった。
当時、2004年の新聞記事を読み返しながら「こんな時代もあったな」と、何だか懐かしくなってしまった。SAABがなくなってしまえば、高速道路とか4車線化とか、鉄道の複線化といったせっかくの投資も報われないことになってしまう・・・。
Utbildning ska rädda Trollhättan (Dagens Nyheter:2004-11-02)










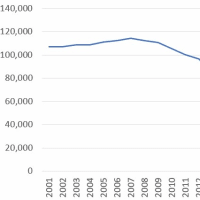
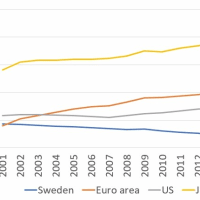
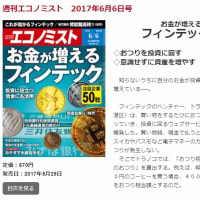
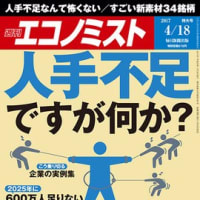






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます