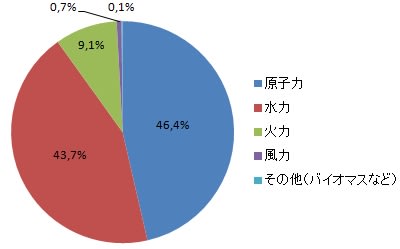前回紹介したスウェーデン議会の「温暖化対策準備委員会(Klimatberedningen)」は、与党・野党を問わず、国政政党7党すべてからの代表者によって構成されている。気候変動の対策のために党派を超えた幅広いコンセンサスを築き、具体的な政策を実行に移し(掛け声だけではなく)、さらには国際レベルでの合意形成にスウェーデンとして貢献していくことが目的なのだ。

中央の小島にある建物が「議会議事堂」。本会議場があるのは後ろの影に隠れている半円の建物
この委員会は、議会から与えられた「指令(ミッション)」に基づき、3月4日までに報告書を議会へ提出することになっている。与野党がともに参加している委員会なので、合意形成は大変なんじゃないか!?、と思われるかもしれないが、いくつかの点については既に合意に至り、早くも先週の段階で、その一部がメディアに流れたのだった。
それはまず、
(1) ガソリン税とディーゼル税のさらなる引き上げ(リットルあたり0.70クローナ=12.6円。おそらく名目は「二酸化炭素税」として)
スウェーデンでも、自家用車の使用や運輸部門からの排出量をさらに減らしていく必要がある、と考えられている。そのための一つの手段は、燃料コストを引き上げること。大気汚染や温暖化といった形で、社会全体に対して「費用」が生じているのに、それが車の利用者によってきちんと支払われていないから、「税」という形でガソリン価格に上乗せする(つまり、車の利用による社会的費用を経済システムの中に「内部化する」)と捉えることもできる。
そして、
(2) 運輸トラックに対して走行距離に応じた「キロメートル税」を課す
長距離運送のトラックの数は近年も増え続けているという。そのため、走行距離に対して直接課税することで、トラック輸送に対する需要を抑え、さらに、運送会社がより効率的にトラックを運用することを狙っている。税の徴収も制度的に難しいことではなく、スイスやドイツ、オーストリアでは既に導入されているという。1kmあたり1-2.5ユーロ(ただし、独と墺では高速道のみ)。
さらには
(3)通勤に自家用車を使う人には、一定の条件を満たす場合に、所得控除が認められていたのだが、その条件を厳しくして、公共交通の利用を増やす
(4) ストックホルムが導入している「渋滞税(都心乗り入れ税)」の制度を、他の都市でも導入しやすいように法の改正を行う。
そして、今日も新たな情報がメディアに流れた。
(5) 2020年までの排出抑制目標として、スウェーデンは「30%減」を掲げる
これは実際にはまだ合意に至ったものではなく、あくまで来週の委員会会合で採決が取られる予定の“議長案”なのだが、与野党のそれぞれ1党が既に支持を表明しており、委員会の他のメンバーの出方が注目されている。
先日も書いたように、EU全体の温暖化対策では2020年までの削減目標を20%減に定め、そのもとでスウェーデンには17%減を課しているのだが、「このEUの目標にスウェーデンとして単に追随するだけでは不十分」という認識が、委員会メンバーの一部にあるらしい。そのため、来週の会合での採決を前に、世論や専門家、メディアの反応を確認する目的で出された一種の「リーク」ではないかと私は思う。
――――――
普段はいがみ合っている与野党のすべてが参加しているこの委員会で、なぜ、こんなにも早く意見形成が可能なのか?
(続く...)

中央の小島にある建物が「議会議事堂」。本会議場があるのは後ろの影に隠れている半円の建物
この委員会は、議会から与えられた「指令(ミッション)」に基づき、3月4日までに報告書を議会へ提出することになっている。与野党がともに参加している委員会なので、合意形成は大変なんじゃないか!?、と思われるかもしれないが、いくつかの点については既に合意に至り、早くも先週の段階で、その一部がメディアに流れたのだった。
それはまず、
(1) ガソリン税とディーゼル税のさらなる引き上げ(リットルあたり0.70クローナ=12.6円。おそらく名目は「二酸化炭素税」として)
スウェーデンでも、自家用車の使用や運輸部門からの排出量をさらに減らしていく必要がある、と考えられている。そのための一つの手段は、燃料コストを引き上げること。大気汚染や温暖化といった形で、社会全体に対して「費用」が生じているのに、それが車の利用者によってきちんと支払われていないから、「税」という形でガソリン価格に上乗せする(つまり、車の利用による社会的費用を経済システムの中に「内部化する」)と捉えることもできる。
そして、
(2) 運輸トラックに対して走行距離に応じた「キロメートル税」を課す
長距離運送のトラックの数は近年も増え続けているという。そのため、走行距離に対して直接課税することで、トラック輸送に対する需要を抑え、さらに、運送会社がより効率的にトラックを運用することを狙っている。税の徴収も制度的に難しいことではなく、スイスやドイツ、オーストリアでは既に導入されているという。1kmあたり1-2.5ユーロ(ただし、独と墺では高速道のみ)。
さらには
(3)通勤に自家用車を使う人には、一定の条件を満たす場合に、所得控除が認められていたのだが、その条件を厳しくして、公共交通の利用を増やす
(4) ストックホルムが導入している「渋滞税(都心乗り入れ税)」の制度を、他の都市でも導入しやすいように法の改正を行う。
そして、今日も新たな情報がメディアに流れた。
(5) 2020年までの排出抑制目標として、スウェーデンは「30%減」を掲げる
これは実際にはまだ合意に至ったものではなく、あくまで来週の委員会会合で採決が取られる予定の“議長案”なのだが、与野党のそれぞれ1党が既に支持を表明しており、委員会の他のメンバーの出方が注目されている。
先日も書いたように、EU全体の温暖化対策では2020年までの削減目標を20%減に定め、そのもとでスウェーデンには17%減を課しているのだが、「このEUの目標にスウェーデンとして単に追随するだけでは不十分」という認識が、委員会メンバーの一部にあるらしい。そのため、来週の会合での採決を前に、世論や専門家、メディアの反応を確認する目的で出された一種の「リーク」ではないかと私は思う。
――――――
普段はいがみ合っている与野党のすべてが参加しているこの委員会で、なぜ、こんなにも早く意見形成が可能なのか?
(続く...)