雫石鉄也の
とつぜんブログ
破滅の王
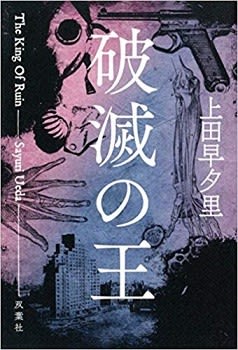
上田早夕里 双葉社
舞台は戦前の中国は上海それに満州。主人公は細菌学者。それにもう一人、日本大使館付陸軍武官補佐官の少佐。
その細菌は細菌を食べて繁殖する菌。人に感染すれば大腸菌をエサにして増殖、被感染者は死ぬ。治療薬はない。上海自然科学研究所の宮本は日本総領事館に呼び出される。そこで灰塚少佐に引き合わされる。宮本は灰塚にある細菌に関する論文の精読を命じられる。
それに書かれている細菌はR2v=キングと呼ばれる。人に感染し、パンデミックとなれば人類にとって大きな脅威となる。その論文は一部分だけ。全文を読まなければキングの全容は判らない。灰塚は宮本に治療薬の開発を命じる。
キングはこのままでは兵器としては使えない。撒布すれば敵も味方も殺してしまう細菌は兵器ではない。敵だけを殺してこそ兵器となるのだ。
帝国陸軍関東軍防疫給水部=石井部隊731部隊に関わった男が論文の執筆者らしい。この件を良く知る宮本の親友が謎の死をとげる。その親友の婚約者という不思議な女も宮本に接近してくる。
石井四郎のような実在の人物、架空の人物が入り乱れて、R2vキングという究極の殺人細菌をめぐる壮大な物語。キングの治療薬を持つ。それは凶暴な虎に首輪をつけ飼いならして敵だけを食う虎にするということ。
キングの開発者は人類に絶望した科学者。しかし、この小説の底を流れるのは科学に対する信頼と愛だ。主人公は作者の思想を具現化する存在。宮本はキングの治療薬は必ずできる。その信念は揺るがない。キングを兵器とするためではなく万が一感染者が出たときのためだ。主人公宮本は科学を信じる。それは作者上田早夕里が科学を善と見なしたいのであろう。科学への信頼がテーマの小説。それは優れたSFであるいえよう。上田早夕里という作家の存在を日本のSFもんとしてたいへんにうれしく思う。
コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )
神戸歴史散歩

都市研究会編 洋泉社
神戸の地元紙神戸新聞のベストセラーリストのノンフィクション部門で、息長く上位にいる本である。こういう本は神戸以外の人はあまり読まないと思う。この本を興味を持って手にする神戸市民が多いということだろう。小生も長年の神戸市民である。六甲山の見えない所には住んだことがないし、これからも住むつもりはない。
と、いうわけで読んだ。ふむなるほど。なぜ神戸がハイカラモダンな「神戸」となったのか。ひととおり触れてある。ではあるが、神戸に対する愛が感じられない。神戸に関する名著といえば2015年に亡くなった西秋生の「ハイカラ神戸幻視行」と「ハイカラ神戸幻視行 紀行篇 夢の名残り」があるが、西の2冊には神戸愛に満ちていたが、本書は科学者が対象物を観察するような冷たさを感じる。執筆者はほんとに神戸在住なのだろうか。たとえ在住者であっても10年以上の神戸市民なのだろうか。疑問である。
なぜ神戸は、今の神戸になったのか。要因は三つ。六甲山と和田岬と平清盛である。六甲山が北からの強風を防ぎ(阪神タイガースの球団歌「六甲おろし」はその六甲山をこえてきて南がわの阪神間に吹く風のこと)、明石海峡からの強い潮流を和田岬が防ぎ兵庫津を天然の良好神戸港にした。そしておおかたの反対を押し切って強引に福原に都を移した清盛。港を整備し福原を京都に負けない都にしようと計画していた。
NHKの人気番組「ブラタモリ」も神戸に来たこともあった。この本もその「ブラタモリ」的面白さを持ちつつもサブタイトルの「地図と地形で楽しむ」いがいのことも言及している。
気になるところもいくつかあった。「はじめに」で「神戸にはイノシシもいるんだぜ」最初からずっこける。神戸人はこんないいかたはしない「神戸にはイノシシもおるで」
菊正宗は灘五郷の御影郷と書いてあったが魚崎郷である。現地に来たのか?神戸市営地下鉄「長田駅」とあったが、神戸の地下鉄にそんな駅はない。神戸市営地下鉄海岸線に「新長田駅」ならある。
ま、それはそれとして、本書で言及されている所は、多くが小生の散歩コースにある。こんど見よう。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
死の鳥

ハーラン・エリスン 伊藤典夫訳 早川書房
エリスンである。ずいぶん久しぶりである。エリスンの短編集は「世界の中心で愛をさけんだけもの」以来である。ハヤカワの銀背で40年以上昔に読んだ記憶がある。
「悔い改めよ、ハーレクィン!」とチクタクマンはいった
竜討つものにまぼろしを
おれには口がない、それでもおれは叫ぶ
プリティ・マギー、マネーアイズ
世界の縁にたつ都市をさまよう者
死の鳥
鞭打たれた犬たちのうめき
北緯38度54分、西経77度0分13秒 ランゲルハンス島沖を漂流中
ジェフティは五つ
ソフト・モンキー
この10篇が掲載されている。このうち「悔い改めよ~」「おれには口が~」
「ランゲルハンス島~」の3篇はSFマガジンでヒューゴー賞だかネビュラ賞だかの特集で読んだのを覚えている。確か「おれには口が~」は「声なき絶叫」というタイトルで掲載されていた。一読した時に衝撃を半世紀近く経った今も覚えている。うわあ、ごっついかっこええ作家が出てきたな。このたび、ものすごく久しぶりに再読したわけだが、その衝撃の残滓を感じることができた。小生も老いた。SFを読み始めて50年以上。この作品の持つ衝撃を感じる感性がまだ残っていることをうれしくおもう。
こうしてエリスンの作品をまとめて読んで思ったことだが、エリスンが書くSFには天井がある。短編の天才といっていい作家が書くSFである。上質のSFだけが有する「ぶっとび感」があるが、なんか室内でぶっとんでいるのだ。室内といっても小さな住宅ではなく、大伽藍ともいうべき巨大な室内ではあるが天井があるのだ。ものすごく高い天井なのではあるが。
これが例えばエドモント・ハミルトンあたりだと、天井がない、屋外の空があり、それが無限の宇宙まで感じることができる。
エリスンの天井があるのはなぜだろう。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
七人のイヴⅠ

ニール・スティーヴンスン 日暮雅通訳 早川書房
小生、上方落語ファンにつき、江戸落語にはなじみがないが、聞いた話では古今亭志ん生の落語の出だしは「ようこそのお運びで。まいど馬鹿馬鹿しいお笑いを」なんて出だしではなくて「てえ、ことでございまして」と、いきなりはじまるとか。
この小説の出だしも志ん生流だ。「てえ、ことでございまして、月が七つに壊れちまったということでございます」
と、いうわけで七つの月の破片は衝突をくり返しバラバラに。その月の破片がいっせいに地球に降り注いでくる。地球は灼熱地獄となる。これが5000年続く。そんな状態で生き残るのはクマムシぐらい。もちろん人類は絶滅。さあ、えらいこっちゃ。
人類をはじめ地球の生物を「種」として残さなければならない。宇宙の「箱舟」クラウド・アーク計画が始動した。国際宇宙ステーションを足がかりにして計画が動き始める。
物語の大部分は、この国際宇宙ステーション「イズィ」で展開される。ご時勢なのか、この小説の主要登場人物は女性が多い。主人公ともいうべきイズィ駐在のロボット学者、イズィの司令官、それにアメリカ合衆国大統領、これらのキャラは全員女性。男性で主要登場人物は、地上で活躍する天文学者ぐらいか。
あと2年で地球上のほとんどの人は死ぬ。生き残れるのは数千人。人々はどう動き、なにを考え、なにをしたか。そういったことはまったく描かれていない。愁嘆場は一切なし。故山野浩一先生なら「えらい人ばかりで一般庶民がえがかれていない」と論評されたであろうが、この巻は全3巻の1巻目。物語の発端部分である。もともとは1冊の本だが、早川は3冊の分冊で出した。できたら1冊の本として出して欲しかったな。作者スティーヴンスンはOKしたのだろうか。京極夏彦先生なら1冊の本で出せといっただろう。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
柳生忍法帖
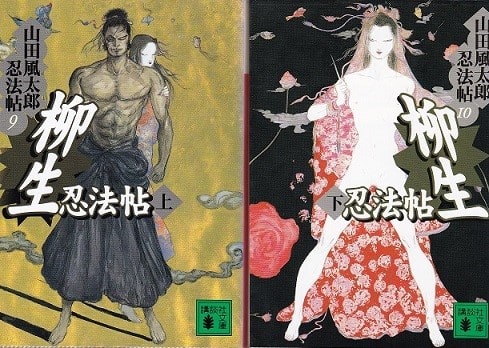
山田風太郎 講談社
やっぱ山田風太郎はエンタメ小説の天才である。ものすごく面白い。主人公は柳生十兵衛と七人の美女。この七人の美女の仇討ちの物語である。十兵衛は美女たちのコーチである。仇は悪逆非道の会津藩主加藤明成と明成の親衛隊会津七本槍と称する化け物的な武芸者。十兵衛と七人はたびたび絶体絶命の危機におちいる。どう考えても脱出不可能は危機ではあるが脱出する。読後、冷静になって考えると、だいぶん都合がいいところもあるが、読んでいる最中は夢中でそんなことは気にならない。そこはそれ、山田風太郎の筆先の魔術である。
加藤明成はその性格残虐。あまりのひどさに家老堀主水は会津藩を見限って一族を引き連れ会津を離れる。激怒した明成、高野山に逃れていた堀一族を捕らえる。一族の女性たちは鎌倉の駆け込み寺東慶寺にかくまわれていた。会津七本槍の七人は男子禁制の東慶寺に乱入。堀一族の女たちを虐殺。
この寺、現将軍の姉である天樹院千姫の娘が住持を務めている。豊臣秀頼の正室にしてあの神君家康の孫千姫である。将軍が頭が上がらないただ一人の人物。この徳川の御世において豊臣家の紋章五三の桐がついた籠に平然と乗っている。この天樹院が七本槍の狼藉を止めた。七人の女が生き残った。
天樹院がいう「女の寺への乱暴狼藉ゆるしがたし。女の寺での虐殺。あの七人への仇討ちは女の手で成さなければならぬ。お前たち七人の手であの七本槍を倒せ」
化け物のような七本槍を、女の細腕で倒すことは不可能。天樹院は高僧沢庵禅師に相談。あの女たちに武芸軍学のコーチを付ける必要がある。だれがいい。
そして沢庵が連れてきたのが柳生十兵衛。十兵衛は「面白い」といって引き受ける。十兵衛はあくまでコーチで指南役。仇討ちを実行するのは七人の女でなければならない。武家の女とはいえ武芸は素人の七人の女に、化け物的武芸者の会津七本槍を討てるのか。
コメント ( 8 ) | Trackback ( 0 )
SFマガジン2018年8月号

SFマガジン2018年8月号 №728 早川書房
雫石鉄也ひとり人気カウンター
1位 博物館惑星2・ルーキー 第4話 オパールと詐欺師 菅浩江
2位 うなぎロボ、海をゆく 倉田タカシ
3位 赦しの日 アーシュラ・K・ル・グィン 小尾芙佐
4位 悪魔人間は悼まない 上遠野浩平
5位 沼樹海のウィー・グー・マー(後篇) 瀬尾つかさ(未読。前篇は2ヶ月も前なんで忘れた)
連載
小角の城(第48回) 夢枕獏
椎名誠ニュートラル・コーナー(第61回)
ナグルスの逃亡 椎名誠
先をゆくもの達(第4回) 神林長平
マルドゥック・アノニマス(第21回) 冲方丁
幻視百景(第15回) 酉島伝法
SFのある文学誌(第59回) 長山靖生
筒井康隆自作を語る 最終回
筒井康隆コレクション完結記念(後篇) 筒井康隆
昆虫食は愛だ(新連載) 篠原祐太
アニメもんのSF散歩(第118回) 藤津亮太
SFファンに贈るWEB小説ガイド(第2回) 柿崎憲
人間廃業宣言 特別篇 友成純一
読切コミック
と、ある日のウチの愛未 宮崎夏次系
アーシュラ・K・ル・グィン追悼特集
今月号の特集は今年の1月に逝去したアーシュラ・K・ル・グィンの追悼特集。表紙はそのル・グィンの肖像写真。このところアニメ雑誌かSF専門誌か判らん表紙が続いておったが、今月号のル・グィンの表紙は良かった。ル・グィンが実に魅力的な女性であったかがよく判る。うすっぺらな魅力ではない。知性の裏うちされた魅力だ。
そのル・グィンの特集。今までなんどか逝去した作家の追悼特集もあったが、今回はよくまとまっていた。
未訳作品の紹介、追悼評論、追悼エッセイ、ブックガイド、年譜など。過不足のない企画であった。
コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )
黒革の手帖

松本清張 新潮社
主人公は悪人である。ピカレスク・ロマンである。ピカレスク・ロマンは悪人が悪をつくして、さらなる巨悪をやっつけるというモノだが、本作は主人公もやっつけられるヤツもおんなじような悪人だ。
主人公の原口元子は元銀行員。銀行の金をババして、その金で銀座にバーを開店してママにおさまる。元子の武器は黒い革の手帳。架空名義の口座やら外聞をはばかる口座のリストを作成黒革の手帖に記録して、支店長と次長をおどしてまんまと7500万をせしめて銀行におさらば。
上昇志向の強い元子はそれで満足しない。もっと大きな店を手に入入れようと算段する。次のターゲットは大きな産婦人科病院の院長。保険外診療でたんまりもうけてため込んでいる。もちろん脱税もしている。これを黒革の手帖に。その病院の看護婦長を使って院長をおどす。
こんなことでは元子の欲望は満足しない。次なる犠牲者は医大系予備校の経営者。医者の息子を医大への裏口入学をあっせんして大儲け。現実には文部省の官僚が自分の息子をズルしてたけど。
原口元子もワルだけど、院長や予備校経営者もどうしようもないワル。この小説、ワルもん図鑑ともいえる。ワル、クズ、バカ、アホがたくさん出てくる。
この原口元子はいわば男女格差社会の犠牲者といえる。ベテランの銀行員。たいへんに有能だが、女だから出世の見込みはない。若くない。30代半ば。美人でもない。このまま、銀行の白い壁に囲まれて、地味な女性銀行員として一生を過ごすのか。過ごさなかった。元子は飛び出した。白い壁から。黒い革の手帖を持って。ちなみに表紙の写真は武井咲だがぜんぜん原口元子ではない。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
神戸あるある

寺井広樹 TOブックス
しかし、こんな本、神戸市民以外の人が読んで面白いのだろうか。神戸独特の「街角」「交通」「買い物」「食べ物」「言葉・文化」を1ページ1エピソードで紹介している。例えば、神戸市民は他の街に行くと道に迷う。イノシシが街中をネソネソ歩いてる。それを見てもだれもおどろかない。神戸を通る鉄道。エライもん順。阪急、JR、阪神。などなど。
なるほどというモノもあるし、こんなん知らんぞというのもある。例えば阪急三宮駅北側の広場(今は工事中)を「パイ山」なんていうのは知らなかった。東灘の深江に南米人が多いのも知らなかった。深江はよくうろうろするが南米人は見かけたことがない。深江にはブラジル料理店ペルー料理店があるというが、神戸に長年住んでいる小生は知らない。
また、間違いもある。「首地蔵」の場所を灘区と書いてあるが東灘の間違い。灘中学・灘高校は灘区ではなく東灘。どうも、この著者東灘と灘の区境がどこにあるか知らないようだ。石屋川が区境である。
ま、なっとく行くのもあったし、いかへんのもあった。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
ユナイテッド・ステイツ・オブ・ジャパン

ピーター・トライアス 中原尚哉訳 早川書房
第二次世界大戦は日本とドイツが勝った。ドイツは東海岸を日本は西海岸を領有した。アメリカ合衆国は崩壊。大日本帝国はロスアンジェルスを首都に日本合衆国を建国した。
と、いう設定の小説である。フィリップ・K・ディックの「高い城の男」に触発されて書かれた小説である。著者自ら献辞でディックに感謝の意を表明している。
表紙のイラストを見て、そういう小説であると期待したら失望する。かような巨大人型兵器は出てくるが、期待ほどは活躍しない。後半で少しアクションを披露して読者のご機嫌をうかがってくれる。
アクション小説というより、カリフォルニアに建国された日本合衆国なる国を行くディストピア小説である。この合衆国も大日本帝国だから、絶対君主は天皇である。国民は天皇に忠義を尽くすのが美徳とされている。
主人公は二人。まず石村紅功大尉。ベンという。士官学校をベタから数えたほうが早い成績で卒業した劣等生。同期がみんな佐官になっているのに昇進が遅れている。剣道がヘタで仕事のことより女のことを考えている落ちこぼれ将校。そしてもうひとり。槻野昭子。特別高等警察(特高)の女性課員。石村大尉と違い、めちゃめちゃ有能で沈着冷静。冷酷非情。平然と人を射殺する。陛下の絶対忠臣を任じていて、陛下にあだなす者には容赦しない。どんな拷問には耐える。
このカリフォルニアの日本合衆国にもアメリカ人の抵抗組織がある。その組織にもぐりこみ、「USA」というアメリカが勝った設定のゲームを開発した、元帝国陸軍の将軍を石村、槻野のコンビが追う。
コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )
火の鳥 太陽編

手塚治虫 角川書店
大手塚のライフワーク「火の鳥」手塚の構想では、未来と過去を行き来しながら、最終的に「現代」に収束して「火の鳥」は大団円を迎えるはずであったとか。手塚の死によって、それは幻となったが、この太陽編は1作のなかで、未来と過去を往復している。この「太陽編」が最後の「火の鳥」である。
天智天皇の時代、壬申の乱前夜と、乱終息後の時代を背景に物語りは進む。白村江の戦いで倭国は大敗。倭国の支援を受けた百済の王族の一員ハリマは敗残兵となり唐軍に捕らえられ顔の皮をはがれ狼の頭をかぶせられる。ハリマは仙術を心得る老婆に助けらて生きのびる。海岸を歩くと虫の息の倭国の将軍を見つけ助ける。
ハリマは老婆、将軍とともに倭国に渡る。倭国でハリマは将軍のはからいで領地をもらい豪族となり、犬上と名のる。
そのころ倭国には仏教が渡来していた。時の天皇天智天皇は仏教に帰依、仏教を人民に強制する。倭国土着の産土神の狗族の長老の娘を助けた犬上は狗族と親交を結ぶ。狗族をはじめ産土神たる倭国土着の守護神たちと侵略者仏法者との決戦が始る。
この作品では、仏教は外来の侵略者で、それに帰依した天皇は民衆への抑圧者として描かれる。宗教の存在が人の不幸の元凶となっているわけ。
主人公犬上は渡来人でありながら倭国の土着の神々と契りを結び仏教と戦う。その犬上が頼ったのが天皇に反乱を起こした大海人皇子。
この犬上の物語と並行してスグルの物語が描かれる。スグルの世界ははるかな未来。そこは「火の鳥」をご神体とする「光」教団が支配する世界。スグルは「光」と戦う「シャドー」のゲリラ戦士。「おやじさん=猿田か?」」の指示で「光」の本殿に潜入する。そこで「火の鳥」を見つける。
犬上とスグルは同じ人物が転生したのか。またその恋人も。大海人皇子は反乱に勝利し天武天皇となる。「おやじさん」も「光」の教祖を倒し新たな宗教の教祖となる。犬上/スグルは勝利者側に与したにも関わらず静かに去っていく。権力者を倒しても新たな権力者が生まれるだけだ。
コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )
涙香迷宮

竹本健治 講談社
うわあ。すごいな。ようけのいろは歌考えたな。よう、こんなん考えたな。連珠のうんちくたっぷり。すごいな。
ともかく、たいへんな労作ですな。いろは歌。ご苦労さん。え、いろは歌の労力は評価してるけど、小説としてどうなん。いちおう読めた。最後に、もういっぺん。いろは歌、ご苦労さん。
コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )
上方落語の戦後史
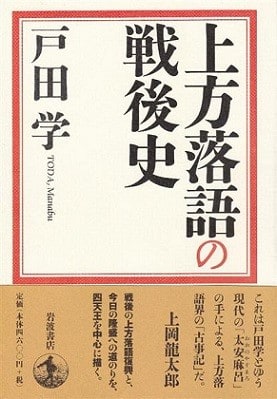
戸田学 岩波書店
大労作である。500ページを超える大作。この長大な分量に上方落語の凋落、復活、そして隆盛が仔細に書き留められている。上方落語を愛する者にとっては、終生、座右に置きたい本である。
爆笑王といわれた初代桂春団治から稿を起こし、桂米朝の人間国宝認定で終わる。上方落語興亡史である。
エンタツ、アチャコをはじめとする漫才の人気に押され、上方落語は衰退し、高座を設ける場所さえ事欠いた。2代目桂春団治が亡くなった時には「これで上方落語は死んだ」とさえいわれたものだ。この上方落語の危機を救ったのは、いわゆる四天王、笑福亭松鶴、桂米朝、三代目桂春団治、五代目桂文枝である。しかし、この四人が登場する前にも上方落語を後世に残すべく心血を注いでいた落語家がいた。五代目笑福亭松鶴と四代目桂米団治である。そして三代目林家染丸が戦力に加わり、江戸落語の桂文楽、古今亭志ん朝が側面から支援した。このあたりは水滸伝を思わせる面白さだ。
本書を読んでいて、日本SFのことを思い浮かべた。かってSFを手がける出版社は必ずつぶれるといわれた時代があった。上方落語はそこに、まだ地中に根が残っていたが、日本SFは不毛の荒野であった。そこにアメリカから矢野徹が種を持ち帰り、江戸川乱歩のアドバイスによって日本にSFの種を植え付けた。そして福島正実がSFマガジンを、柴野拓美が宇宙塵を創刊し、これが日本SFの母胎となった。そこから星新一が、小松左京が、筒井康隆が、眉村卓が、光瀬龍が登場し、現代の日本SFの隆盛となった。
上方落語と日本SF。よく似ているではないか。そういえば上方落語とSFは親和性が大きい。堀晃さん、かんべむさしさんをはじめ、関西のSF者には上方落語好きが多い。
本書を読んで、その上方落語と日本SFの不思議なえにしを感じる話がいくつか載っていた。
正岡容。中川清青年(桂米朝)がこの正岡に入門したのが、上方落語復興の1つの契機となった。この桂米朝の師正岡容の甥が平井イサクである。SF好きなら聞いたことのある名前だろう。アイザック・アシモフやアーサー・C・クラークを多く翻訳した人である。
桂文珍の初期の独演会は下座でシンセサイザーを演奏する画期的なモノだった。そのシンセサイザーを演奏したのが難波弘之。古くからのSFのビッグネームファンで巽孝之氏の大学の先輩である。
二代目桂春団治の公演のポスターのイラストを描いたのが、学生時代の手塚治虫。この時、手塚は落語家への転身をすすめられたとか。このとき手塚がOKしていたら、大きな落語家が上方に生まれていたかもしれない。その代わり日本の漫画は別の歴史をたどっていただろう。
そして桂米朝と小松左京の終生変わらぬ友情は万人の知るところである。
もれなく上方落語の戦後史を記しているといいたいが、そうでもないのが二つほどある。まず、桂枝雀一門と桂ざこば一門の上方落語協会脱退の真相。この件に関しては「脱退した」と事実だけが記してあった。なぜ脱退したのか書いてない。当時の上方落語協会会長の露の五郎会長といかなる確執があったのか。また、6代目笑福亭松鶴亡き後、なぜ順当に総領弟子の笑福亭仁鶴が7代目松鶴にならなかったのか。なぜ仁鶴は嫌がったのか。鶴光、福笑、6代目松喬、松枝、呂鶴といった兄弟子たちを飛び越えて、松葉が7代目松鶴を継いだのはなぜか。上方落語ファンなら知りたいところである。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
深夜食堂×dancyu

dancyuは創刊号以来愛読している。「深夜食堂」は原作の漫画は未読だが、テレビや映画は観た。そのdancyuと深夜食堂のコラボ本である。
取り上げてある料理は、ウィンナー、マカロニサラダ、ハムカツ、ソース焼きそば、ゆでたまご、唐揚げ、タコぶつ、目玉焼き、やっこ、などなど、いずれもシンプルな料理ばかり。
これらシンプルな料理を紹介しつつ、それぞれに関するうんちくが書いてる。それが料理好きとしては実に楽しい。例えば、ゆでたまご。ただ卵をゆでるだけと思うなかれ。卵の選び方からゆでる湯温からゆで時間などなど、おいしいゆでたまごを調理するためにはさまざまなうんちくがあるのだ。
夜おそくまで自宅で仕事。さて寝ようか。その前にちょっと一杯ひっかけて寝よう。軽くアテを欲しい。そんなときに開きたい本だ。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
SFマガジン2018年6月号

SFマガジン2018年6月号 №727 早川書房
雫石鉄也ひとり人気カウンター
1位 ひとすじの光 小川哲
2位 十二月の辞書 早瀬耕
3位 博物館惑星2・ルーキー 第3話 手回しオルガン 菅浩江
4位 沼樹海のウィー・グー・マー(前篇) 瀬尾つかさ
5位 プレイヤーズ・アンノウン・ストリーミン・グラウンド 小川一水
6位 ハイ・リプレイアビリティ 廣江聡太朗(あでゆ)
7位 超能力戦士ハリアーの意思 クラベ・エスラ
8位 姫日記 柴田勝家
連載
小角の城(第47回) 夢枕獏
椎名誠のニュートラル・コーナー(第60回)
居酒屋会議 椎名誠
先をゆくもの達(第3回) 神林長平
マルドゥック・アノニマス(第20回) 冲方丁
幻視百景(第14回) 酉島伝法
SFのある文学誌(第58回) 長山靖生
アニメもんのSF散歩(第22回) 藤津亮太
筒井康隆自作を語る ♯7 筒井康隆
SFファンに贈るWEB小説ガイド 柿崎憲
読切コミック
と、ある日の私の色 宮崎夏次系
ゲームSF大特集
「ゲームSF大特集」と銘打った企画であるが、羊頭狗肉である。「ゲームSF」の特集ではなく、「SFゲーム」の特集である。
この企画の眼目は「ゲームを題材としたSF」の特集ではなく、「SFっ気のあるゲーム」の特集である。で、あるからして、この雑誌は文芸誌としての誇りも矜持も捨て去り、たんなるゲーム紹介にうつつをぬかすゲームミーハー雑誌に堕してしまった。
小生もゲームは嫌いではない。若いころはゲームをよくした。「大戦略」「信長の野望」「ハイドライド」「ザナドゥ」などを夢中でやったもんだ。アレから幾星霜、小生もこんなトシになった。なにをやるにも限りがある。人生は無限ではなく有限であることを強く意識するようになった。これから読む本観る映画も限りがある。時間に限りがあるのだ。その限りある時間をゲームに費やす余裕はない。よって、この特集企画は小生とは縁なきモノであった。とはいいつつも特集関連連の小説は読んだ。人気カウンターの5位6位7位8位のモノがそれ。いづれも駄作。ゲームを文字で書いただけ。
編集後記に(溝)なるご仁が、「文芸誌によるゲーム特集をお届けしました」と記していたが。自分が編集している雑誌が「文芸誌」だと思っているのだろうか?
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
奇想天外 21世紀版 アンソロジー

山口雅也編著 南雲堂
「奇想天外 復刻版」と、同時発行がこの「奇想天外 21世紀版 アンソロジー」である。伝説のSF雑誌「奇想天外」が21世紀のいまも刊行されていればというコンセプトで編集発刊されたのがこの本というわけ。500ページを越える大部である。
結論からいう。「奇想天外」がいまもあったとしても、こんな本にはなっていなかったであろう。特に第二期奇想天外を思い出せば、そういうことである。
小説の執筆者は次の通り。まず海外。アーサー・モリスン、ウィリアム・トレヴァー、アントニイ・バークリー、カミ、ボブ・ショウ。ボブ・ショウ以外知らない。国内。新井素子、有栖川有栖、井上夢人、恩田陸、京極夏彦、法月綸太郎、宮内悠介、山口雅也。この中でSFプロパーといえるのは、新井、恩田、宮内だけ。
通読しての印象だが、SFっ気はたいへんにうすい。変格ミステリーとホラーに偏重している。それに「幻の作家たちをプレイ・バック」と称して、編者山口のワセダミステリクラブ時代のお友だちの作品を紹介していた。これはあきらかに山口の公私混同である。ファンジンならいざ知らずプロの雑誌でこういうことはやるべきではない。もし小生(雫石)がこんな仕事をやったとしても星群の古い同人の作品を掘り出して、かようなところに掲載することは絶対にない。
古狸SFファンとしては、この企画、なんとも欲求不満が残る企画であった。こんど同様の企画をやるときは、巽孝之氏か大森望氏、はたまた山本弘氏のようなSFがよく判った人にやってもらいたい。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
| « 前ページ | 次ページ » |



