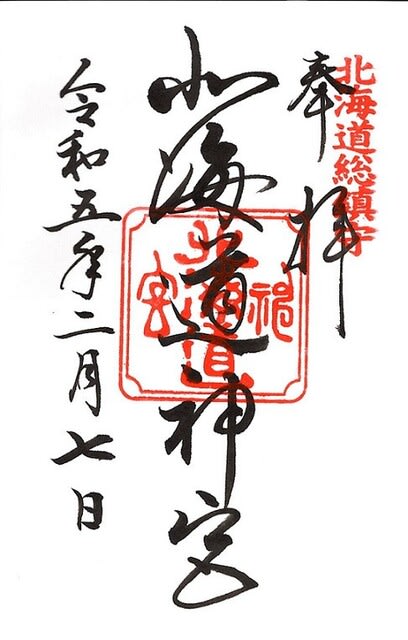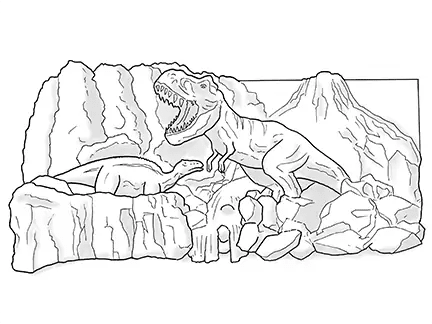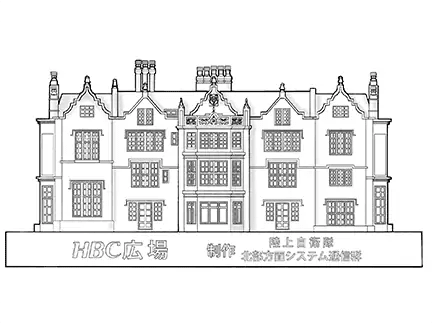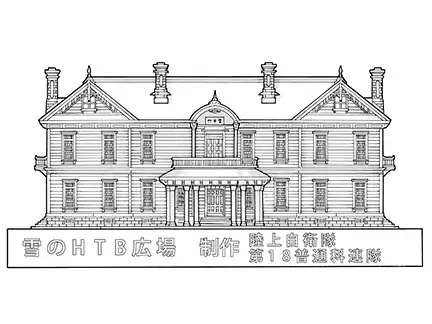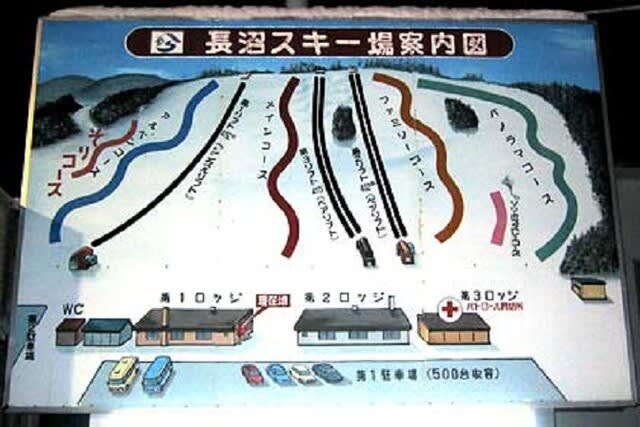野村良太君は知的で爽やかな好青年だった。前人未到の大冒険をやってのけたのに、彼は時にユーモアを交えながら自分の偉業をさりげなく語ってくれた。彼のやってのけた偉業を、私はどれだけ伝えることができるだろうか?

例えば…、45キロもの荷物を背負い雪深い前人未踏の山道を670kmも連続して歩くことができるだろうか?
例えば…、63日間も来る日も来る日も同じ食事が続けられるだろうか?
例えば…、極寒の山中、強烈な吹雪の中で、テント一枚で一人63日間も過ごせるだろうか?
例えば…、63日間もの間、風呂に入ることも出来ずにいることに耐えられるだろうか?等々…。
ヒトとしてたくさんの?が付くことを敢然とやり遂げた男が野村良太君なのだ。(28歳の好青年であることから敢えて ”君” 呼びさせてもらう)
2月5日(日)夕刻、かでるホールにおいて日本山岳会北海道支部主催による「積雪期単独 北海道分水嶺大横断 ~宗谷岬から襟裳岬670km 63日間のみちのり~」と題する野村良太講演会が開催され参加し、彼の話に耳を傾けた。
ルートの約8割が人跡未踏という冬期の分水嶺を2022年の2月から3月にかけて宗谷岬から襟裳岬まで670キロ、63日間にわたって縦走するということがどれほど困難なことなのか、素人には想像もつかないことだが、それをやってのけたのが野村良太君である。

※ 野村良太君が63日間をかけて辿った北海道の分水嶺のルートです。(赤線)
彼がやったことがどれだけ困難なことなのか、彼は自らの大冒険を振り返りながら次のようなエピソードを紹介している。
「完全単独ワンシーズンであれば、極地の単独歩行横断に匹敵する、最も困難で素晴らしい記録になることは間違いない。」
極地というと、北極や南極ということだろうか。そこがどのようなところなのか僕はまだ知らない。ひょっとするとそのレベルのすごい計画なのかもしれない。17年もの歳月を費やしてこの計画を完遂し、その記録を『北の分水嶺を歩く』にまとめた著者、工藤英一氏があとがきに残したこの言葉が頭を離れない。工藤氏はその後にこう綴っていた。
「いつの日か誰かに、人並はずれた艱難辛苦に耐える精神力と強靭な体力の持ち主に、挑戦し実現してもらいたい。本州や外国ではなく地元の北海道にこんな素敵なかけがえのないルートがあるのだから、道内のこれからの若き岳人に期待している。人間の精神力と体力の可能性を広げ、登山者はもとより、登山の世界を知らない一般市民にも感動と夢を与えてやまない、本物の山行になると僕は強く信じている。」
ぼんやりと、この若き岳人って僕のことにならないかな…。と思う。「本物の山行」という言葉は僕の心を惹き、深く脳裏に焼き付いた。
実は彼のこのエピソードを知ったのは、NHKローカルの「北海道道」という番組の中でのことだった。実は彼の偉業は、「北海道道」の番組だけではなくNHKはBSや総合TVにおいて「白銀の大縦走」と題して何度か放送していた。今回の講演会はそれらの番組を視聴した方が大半だと思われる方々で満員の盛況だった。
したがって野村君の講演の内容は、北海道の分水嶺を縦断するルートの紹介、そして計画における諸準備の話、実施後の総括に絞られ、他は野村君自身が縦断中に自ら撮影(自撮り)した動画を映しながら話すことが大半だった。
私がまず驚いたのが、恐るべき緻密さで計画を立てていたことだ。実は野村君は、この大縦走を実施する前に「積雪期単独知床半島全山縦走」(12泊13日)、「積雪期単独日高山脈全山縦走」(16泊17日)を一つのシーズンに達成していてかなりのノウハウをすでに体得していた。そして今回成功した前年の2021年に今回とは反対の襟裳岬から宗谷岬を目指したものの、計画の甘さからあえなく撤退しなければならなかったという体験も彼の計画を一段と緻密なものにしたようである。
その一例である。彼の63日間の食糧計画は実に緻密だった。彼は冒険中の食糧計画を次のように語っている。
1日当たりのカロリーについてはこれまでの経験則をベースに3000kcal以上は必要であると考えた。そのあと参考にしたのは、極地探検をしている冒険家の食料事情だ。彼らはたいてい1日5000kcal程度準備している。それでも一日に7000kcal消費するからどんどん痩せていってしまう。彼らの舞台は−30℃を下回る世界である一方、こちらはせいぜい−20℃程度であること、彼らはそりなどを使っているのに対して、こちらはザックですべてを背負わなければいけないことから、3500kcal/1日とすることで落ち着いた。食料はできるだけ軽くてカロリーがあるものだけで構成した。500kcal/100g未満のものはできるだけ使わないと決めたが、例外としてビタミン不足解消を意識してフルーツグラノーラを追加。気休め程度に一日一錠のビタミン剤(マルチビタミン)も準備した。主食は1食100gのアルファ化米を1日3食(64日間で192食分)だ。おかずとなるのは学生時代から作っていたペミカン約30〜40g(アメリカ先住民の伝統的な保存食を日本風にアレンジしたもの。豚ひき肉を炒めて水分を飛ばし、塩胡椒で味付けした後に牛脂やバターで固める。水分がなくなることで腐りづらくなり、また軽量化することもできる)だ。アルファ米、ペミカン、それに乾燥野菜と高野豆腐をジェットボイルにひとまとめに入れ、フリーズドライのスープで雑炊のようにする。
私が凄い!と思ったのは、用意した食糧(材)一つ一つのカロリーを計算していたことだ。その膨大な資料の一部をスライドで見せていただき、その緻密さに驚いた。そして用意した63日分の食糧の重量は50kgを超えたという。食糧以外の装備が30kgだったために、食料を背負えるのはせいぜい15kg程度だったという。そのために残りの食糧はルートの途中にある4つの山小屋に予めデポ(保管)することで解決したという。

過去の縦走体験、前年の失敗を糧として、事程左様に慎重に準備を進めたことが今回の成功の裏にあったことを知らされた。
そうした緻密な準備と共に、今回の成功を導いたのは何より彼の体力、気力が並外れたものであったことは言うまでもない。
そうした偉業を達成しながらも、ユーモアを交えつつ、サラッと言ってしまうところに彼の凄さを見る思いがした。彼は次の目標としてヒマラヤにあるJarkya Himal(ジャルキア・ヒマール)という人類未踏の6,473mの登頂を今春目指しているという。彼の成功を陰ながら見守りたいとう思う。
タイミング良く、本日(2月7日付)の北海道新聞紙上に彼の今回の偉業を讃えて「第27回植村直己冒険賞」が授与されることが決定したと報じられていた。
なお、今回の彼の偉業をもっと詳しく知りたいという方はヤマケインラインのページを参照することをお勧めします。こちらをクリックしてください。⇒YAMAKEI 積雪期単独北海道分水嶺縦断記