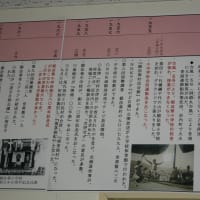▼我が国会の体たらくを見るにつけ「戦後民主主義教育の荒廃ここに極まり」と嘆いてしまう。良識がない者が,“高給”官僚や“高給”議員だとは、妻に“時々”良識に欠けると言われる私でも、さすがに呆れてしまう。
▼広辞苑=「良識」とは、社会人としての健全な判断力とある。“健全”とあるので思い出したのが「教育とは健全な地域社会と健全な人間をつくる」というのは、ある哲学者の言葉だ。
▼やはり国会の体たらくは、戦後民主主義教育が十分な成果を上げれなかったことにあるのではないかという、結論に達する。
▼だが、ここでブログが終了するのではない。今日のテーマは水戸黄門なのだ。出だしがテーマからずれると、元に戻すことが容易でなくなる。
▼しかしここで引き下がれば、能力が問われるのではないかと考え、何とか続行を試みようと思う。
▼と、意固地に思ってしまうのは、軍人の資質に似ていると思ったからだ。というのは、今朝蒲団の中で、昨夜の読書の続きを読んでいた。
▼半藤一利著「日本のいちばん長い日」だ。終戦前夜の8月14日と15日にかけての、軍部の将校たちの、最後の一兵まで戦うという気迫が私の胸を熱くさせる。非常に臨場感あふれる、映像が浮かぶ内容だ。
▼天皇に終戦の決断をさせたことに、天皇の軍隊は、自分たちの至らなさを叱責し、命を賭しても天皇を守らなければならないと思う。
▼軍人とはそういう類の精神を持ち合わせた、実直で硬直な人間集団なのだろう。そうであれば、私は自衛隊を軍隊にしてはならないと思う。
▼先日、元自衛隊員に尋ねたら、集団的自衛権行使で他の国で戦うことは、隊員のおおくは反対していると思う。専守防衛なら、命を懸けて戦うと話していた。
▼だから今の自衛隊で十分ではないかと思う。自衛隊だって、人殺しをする戦争なんて、誰もがいやだと思っているのだ。
▼だが、軍隊となれば、旧帝国軍の考えと今も、まったく同じ精神構造に違いない。クーデターを起こしたミャンマーの軍隊をみても、自分の家族や市民に向け発砲する意識は、軍隊の本質を物語っているからだ。
▼「おそれおおくも・・・」といえば、すぐに天皇陛下が浮かんできた旧軍隊だ。直立不動になった後、ゲンコツが飛んできた。天皇のゲンコツは、誰もが逆らうことなど出来なかった。
▼今テレビで観ている水戸黄門役は、故西村晃だ。札幌出身の西村は、終戦の日に徳島航空隊の特攻隊員だった。そこで親友になったのが、後に裏千家宗主となる、千玄室だ。
▼明日は特攻として旅立つ仲間を励ますため、二人は漫才をやり笑わせていた。上官から何度もビンタをくらっても、やめなかったと話していたのが記憶にある。
▼その隊で生き残ったのが、西村と千二人だったという。生前からの約束で、西村が74歳で旅立った時、千が葬儀委員長を務めたという。
▼助さんが「おそれおおくもご老公の御前である!頭が高い、控え居ろうっ!!」と叫ぶ。一同座して頭を下げる。その時西村黄門は「おそれおおくも」の台詞に、軍隊での同じ言葉を思い出していたのではないだろうか。
▼絶対はむかうことは許されなかった「おそれおおくも」の時代には、自分は正しくとも殴られた。だが自分が水戸黄門となり「おそれおおくも」を振りかざすと、正しいものは助かり、悪は成敗される。
▼なんとも矛盾した立場の自分を感じていたのではないだろうか。黄門は諸国を漫遊し、庶民を救った。それに、戦後の天皇の行幸を重ねていたのではないかと妄想する。
▼コロナ戦争の真っ最中に、国会は乱れに乱れている。印籠を出しても無視する、今の我が国会だ。そんなコロナ禍での、勧善懲悪の水戸黄門が大好きだ。
▼普通の国にしたいというが、軍隊を持つことで、平和は得ることはできない。そんな普通の国にはなりたくない。水戸黄門のドラマのように“良識”がまかり通る「普通の国」であってほしい。
▼繰り返す。【良識とは社会人としての健全な判断力】だ。水戸黄門のドラマにはそれがあるが、スガ政権のドラマは、観るに値しない茶番劇だ。
▼どうやら紆余曲折しながらも、水戸黄門にたどり着いたようだ。
曲った道をまっすぐに歩きたい
三等下