
小さいながら、トモエソウにシモバシラが。初観測です。初観測の1月4日の最低気温はマイナス4.8度でした。
これまで庭で観測したのは、シモバシラ、セキヤノアキチョウジ、ミカエリソウ、テンニンソウ、カシワバハグマ、ベニバナサルビア、そして昨シーズンはコセンダングサに初観測でした。

昨シーズン発生したコセンダングサです。2017年12月28日です。木陰にあったのでまだ葉がしおれたばかりで、茎は生っぽいものでした。
この日の最低気温はマイナス4.9度でした。
コセンダングサが完全に枯れてしまうと発生しません。

今回初観測したトモエソウにはこれまで発生したことがありません。なぜ今回発生したのか。それは水をたっぷり含んだ土のためと思われます。水が十分にあっても小さなものしか発生しませんでした。やはりトモエソウは発生しにくいようです。

1月7日にトモエソウに2回目の観測です。朝の最低気温はマイナス4.1度でした。
石の上の緑の葉はヒメオニヤブソテツです。
私のブログを見ておられた方が、この私雑草のブログを見てくださり、現地へ行ってくださり、顕微鏡で胞子の数を確認してくださった結果、2か所とも64個であったそうです。その方から私の先生に連絡があったので、先生からご連絡をいただきました。
2019年度の南高校の特別講座「楽しい自然観察」が始まりましたら、授業の中で先生のご指導の下で顕微鏡で胞子を見てみたいと思います。
これで、茨城の海岸のヒメオニヤブソテツは3か所にあることがわかりました。
私が出会ったヒメオニヤブソテツ2か所の発見の経緯を簡単に書き記しておきます。
1 フォト蔵のFeさんが宮城県の海岸のヒメオニヤブソテツをフォト蔵に載せられたときに初めてその存在を知りました。20181129
2 楽しい自然観察でオニヤブソテツは何回か話題に出るもナガバヤブソテツは現物まで見たが、ヒメオニが話題にならなかったので茨城になさそうと思ったが、分布領域範囲内なのでFeさんんへコメントしたところ、20181129
3 Feさんから、茨城にもあるかもしれないとコメントいただきました。20181130
4 12月20日実家から弟夫婦が来て、いつものように海岸へ石拾いに行ったときに、海岸でヒメオニのことを思い出して護岸を歩いて、それらしき株を発見してフォト蔵に乗せ、Feさんの感想を請う。20181220
5 Feさんからヒメオニでよさそう。生えている環境もいかにもヒメオニのある場所とコメントをいただく。20181221
6 先生に電話でヒメオニと思われるものを発見したことをお伝えしたところ、これまで調査されないで、本年2018年に高萩で見つかりヒメオニと確認したとのことでした。また今回の発見場所へ行きたいとのことで案内書を郵送することにしました。20181221
7 Feさんから「シダの先生のご意見を楽しみにしています。」とコメントをいただく。20181221
8 先生に現地案内書とヒメオニの写真を送り、到着したと電話をいただく。20181227
9 1月2日子供らと五浦海岸の六角堂を見に行ったが、休日で入れず。六角堂が見える場所を探して崖の小道でヒメオニらしい株を発見。
先生にメールで伝える。20190102
10 Feさんに写真を見ていただき感想を請う。20190103
11 先生から電話をいただく。小名浜のヒメオニらしい小型の株は、胞子が大きく数が少ないようだ。雑種のアツバオニヤブソテツ(雑草初耳)かもしれないとのこと。とにかく胞子数を確認したいと。サンプルは12月20日のものが欲しい。
私からはサンプルは12月20日のものが手元にあります。五浦海岸の葉の厚みについて、いかにも潮をかぶった12月20日発見のつやがあって厚い感じに対して、つやが少なく厚みが薄い感じで、オニヤブソテツの生育不良のように感じられたが、小株も大株も胞子があるので不思議に思うと伝えました。20190105
12 Feさんより、小型の株はヒメオニのようだ。大型の株は不明でアツバオニヤブソテツもありうる。判断不可の旨コメントいただく。合わせて日本産シダ植物標準図鑑のヒメオニとオニヤブの羽片と胞子の数を教えていただく。20190106
13 Feさんへ先生と会話した内容と庭のオニヤブの羽片数の概略をコメントする。20190106
14 FEさんへ庭のオニヤブの羽片数についてフォト蔵に掲載して内容をコメントする。20190106
15 先生よりどちらもヒメオニヤブソテツであったと電話をいただく。胞子の数は2019年度の授業の中でも確認したい。20190107
16 Feさんへ先生からの電話の内容をコメントする。20190107
どちらもヒメオニヤブソテツとわかりました。と先生から電話をいただきました。
実は私のブログを見ているもう一人の先生がおりました。その方が私のブログをご覧になって、2か所とも現地に顕微鏡をもって行かれて、胞子数64個を確認したということを、私の先生に連絡してくださったとのことでした。
なお五浦海岸のほうはFeさんがコメントされた通りで、ヒメオニヤブソテツとオニヤブソテツが混じっていたそうです。生物の会報に今回の発見の事を記事として載せるが私の名前を書いてもよいかとのことで快諾しました。
Feさんがこの写真を載せてくださったことがきっかけになって発見に至ったことにお礼申し上げます。もう一度茨城にいらっしゃる機会がありましたら、オオウメガサソウなど南限の植物とともにこのヒメオニヤブソテツをぜひ見ていただきたいと思います。ありがとうございました。
17 Feさんからコメントをいただく
五浦海岸のものは両者が混じっていたのですね。
こちらこそ、興味深い情報をいただき楽しかったです。ありがとうございました!
ヒメオニヤブソテツをはじめ、是非、現地を見に行きたいです。茨城に伺う際にはお声がけしたいと思います。20190108
(以上)













































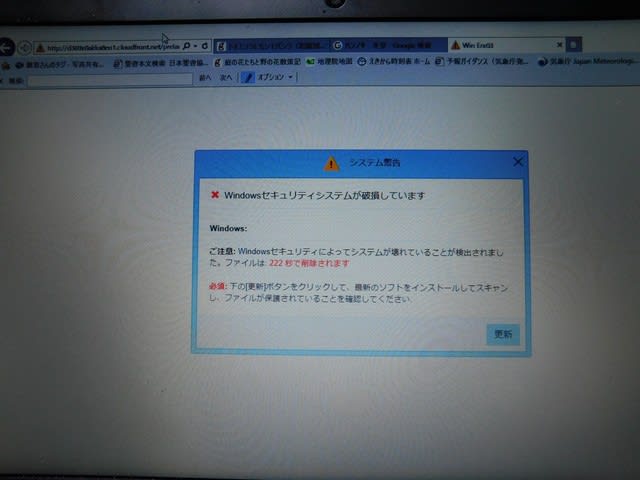
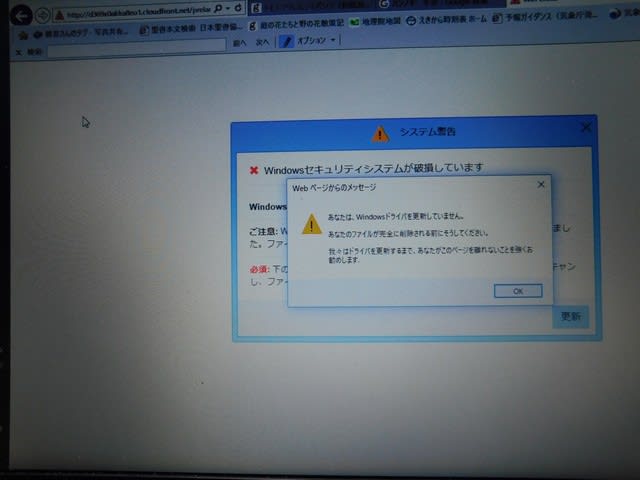

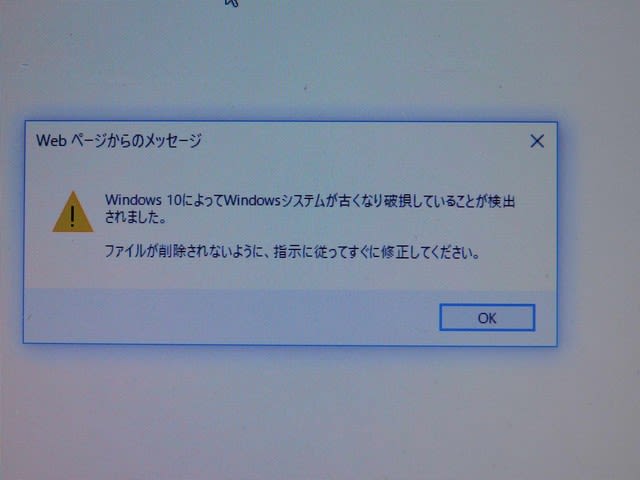
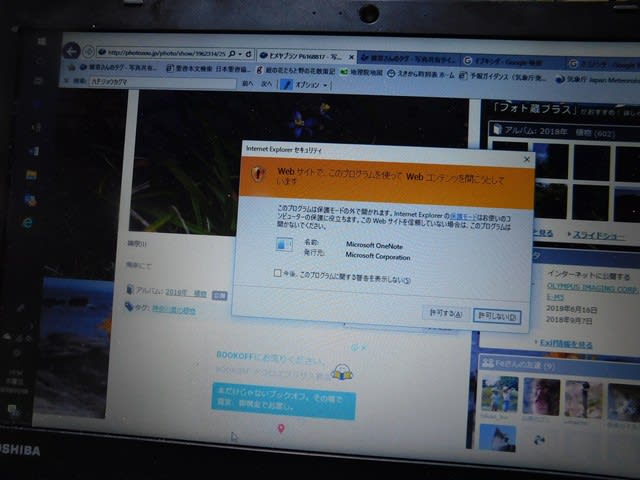
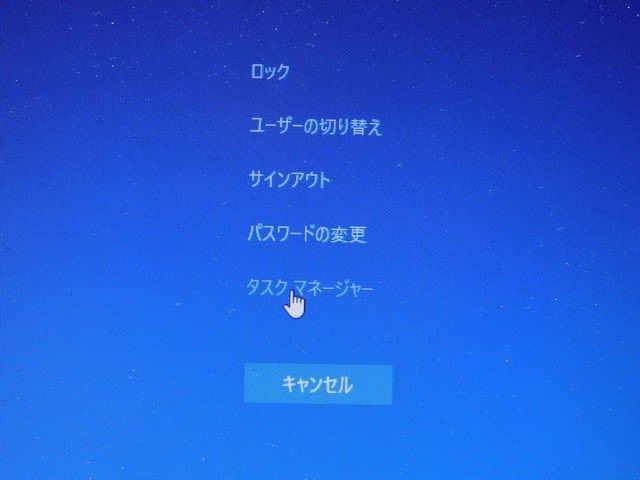

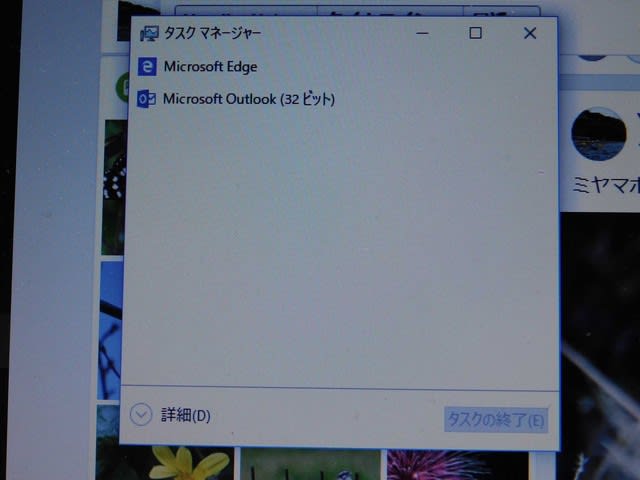
 タンポポ在来種
タンポポ在来種


 冬至梅
冬至梅





















































 八重寒紅
八重寒紅 虎の尾
虎の尾
 水心鏡
水心鏡 冬至梅
冬至梅 八重寒紅
八重寒紅 八重冬至
八重冬至 里見紅
里見紅



























