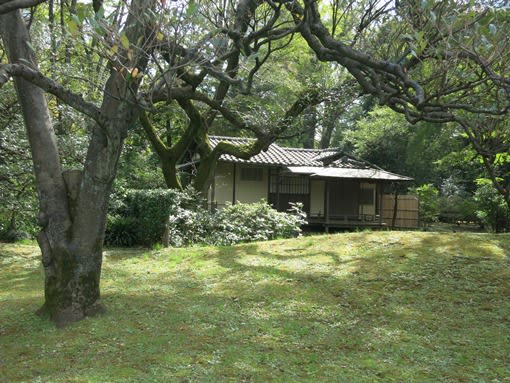一年間の無病息災と五穀豊穣を願って
小正月に行われるどんど焼きの行事は
成人式が15日でなくなってから
各地での実施はまちまちの様です。
ご近所の方が誘ってくれなかったら、
今日である事を知りませんでした。
近くの八幡様では午後1時から始まっていました。
時々青竹のパーンと跳ねる音と共に
燃え上がる炎が気持ちよく感じ、
煙と炎は久しぶりに見た感じです。
火力が落ちてきた頃お団子を焼き始めます。
今年は上手く焼けたので
砂糖醤油が用意されていたので美味しく頂き
童心にかえった様なひと時を過ごしてきました。