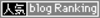こうして、憑依と運動共鳴を使う予測によって、私たちはこの世界を感知する。これによって客観的な物質世界(「現実1」―拙稿19章「私はここにいる」)が構成される。
また、擬人化を使って、憑依できるようなXと、運動共鳴によって予測できる行為Yの組み合わせ(X、Y)を音節列に対応させて人々が共有すれば、言語が構成されます(拙稿18章「私はなぜ言葉が分かるのか?」)。
また、私たちは、コンテキストとともに(X、Y)で表される物事を記憶する。つまり、いつ、どこで、どういう周辺状況(あるいは社会状況)でXがYをして、どうなると予測されて実際どうなったか、を記憶する。感情をともなって、それを記憶し学習する。そういう物事で構成される世界を仲間と共有し、現実として記憶する。
実際、私たち人間はこのようにだれもが同じように現実を記憶し学習する能力を持っている。そのおかげで、人間は言語を習得し社会を維持し、その中で生存と繁殖を持続する動物となっている。逆にいえば、そうして人間だれもが同じように感じとれるものを、私たちは現実と言っている。
ちなみに、途中から拙稿をお読みになっている読者のためにご案内すると、ここで使われている憑依という語は拙稿特有の用語です。もともとは「狐が憑依する」というような文例につかう語ですね。これを援用して、拙稿では、他人の身体に乗り移ったように自分の身体が動きそうになることでその人の身体の動かし方が無意識のうちに分かるというごくありふれた現象を、「その人に憑依する」という言い方でいうことにしました。
あまりうまい造語ではないような気もしますが、表現を簡潔にするには便利なので導入したしだいです。筆者は言葉使いに関しても不調法な上に単純な便宜主義者でして、しかも語感に鈍いので、とりあえず思いついたこの語を安直に使っています。この用語に特に執着があるとか、この語を使って(神秘主義的なものとか)ある種の文学的な雰囲気を出したいとかいうような気はいっさいございません。ましてこの語を普及させたいなどという大それた野心は、筆者にはまったくありません。どなたか、もっとよい用語を思いついたら教えてください。すぐ取り替えます。また、たぶんないでしょうが、この語をこのように使うことで万一どなたかに失礼となっているようならば、言っていただければお詫びの上改めます。
さて、拙稿で使う憑依という語は、語感からは神秘主義の用語あるいは形而上学的表現、または心理学的表現、のようにも聞こえますが、筆者としてはそういう含意はまったく意図していません。単純に、科学の対象となる脳神経回路の物質機構を指して使っています。もちろん、現代の脳神経科学では、拙稿のいう憑依機構に相当する神経細胞組織を解剖学的な意味では同定してはいません。他人の運動を視認する場合に活動する大脳頭頂葉上部、上側頭溝および前頭葉下部皮質の一部神経細胞の集合(ミラーニューロンと呼ばれる細胞群など)が構成する神経機構が関係ありそうですが(二〇〇七年 ヴィンセント・ライト、ゲルゲリ・シブラ、ジェイ・ベルスキー、マーク・ジョンソン『幼児の目的指向行為感知の神経系対応現象』)、詳細は分かっていません。また他人の顔の認知、識別などについての神経学的研究は盛んですが、これが拙稿のいう憑依現象をどのように表現しているかについては、現在の脳神経科学ではほとんど分かっていません。将来は、こういうマクロな認知現象をミクロな神経細胞の活動レベルで同定する科学が可能と思われますが、現代の神経科学の(脳神経画像化などの)測定技術では、とてもミクロな細胞レベルの精密測定は不可能なため、心理学や認知科学の対象であるマクロな認知現象は、神経細胞回路の機構にまで還元できていません。
さて、このような科学の現状でも、拙稿の見解では、マクロな物質現象としての憑依機構の働きは、ある程度、科学的に記述できると思われます。
拙稿ではまず、哺乳動物の脳の運動形成回路には運動感覚シミュレーションのための神経機構が付随しているという仮説を使います。この仮説によれば、対象物を視認しながら身体を動かしている場合、動物の脳神経系では、シミュレーションを伴った運動形成が行われている。そのシミュレーションには、動物の身体運動がモデルとして埋め込まれている。
拙稿の予想仮説によれば、哺乳動物が脳内に保持している身体運動モデルは運動形成回路の最上層で(X、Y)という二項状態変数によって表現されている。Xは注目する運動体を表現する状態変数で、Yは運動の予測結果を表現する状態変数です。
その身体運動モデルは、群棲動物の場合、仲間集団の群運動を表現している。群棲動物の神経系では、仲間の群れが運動すると、それに誘発されて自分の身体が自動的に動いて追従する仕組みになっている。この仕組みのための神経回路が脳にあるはずです。人類では、その回路が発展して憑依機構に進化したと(拙稿の見解では)考えられます。
憑依機構の働きによって、まず仲間の行為と自分の行為とは、同じものと感じられる。そもそも最初から区別されていない。自分の行為を感知する私たちの感覚神経系は、そもそも、(拙稿の見解では)仲間の行為を認知する神経回路と、たぶん同一のものだろうと思われる。前を歩いている人が走り出すと、まず、自分が走り出したと感じる。それから、体性感覚など意識的に点検した後で、その走る人は自分ではなくて自分は走ってはいない、と私たちは気がつくのです。
仲間のだれかが、ある行為Yをしている。それはYという結果になることが予測されます。私たちは無意識のうちにその結果を予測している。そういう場合、まず、私たちはYが起こっていることを感じる。それは自分かもしれないが、自分ではないだれかかもしれない。いずれにしろ、それはYという行為をするようなだれかです。つまり、そういうだれかがYをしている、ということがまず感じられる。
これは、たぶん、群棲動物共通の運動共鳴機構により私たちの身体が共鳴運動を開始するからでしょう。人間の場合、ふつうこの共鳴運動は脳内の仮想運動の段階で抑制されるので筋肉は動きません。しかし、行為Yは、仮想運動の予測シミュレーションとして感知される。
それから次の瞬間に、その行為YをしているものがXであると分かります。そこで、いま起こっていることを(X、Y)で表すことができる。XがYをしている。Yの結果はシミュレーションで予測できている。こういう場合、脳の憑依機構はYをしているXへの憑依を起こしているので、Xの気持ちがよく分かるわけです。Xが何をしたくてYをしているのか、その目的が分かる。逆にいえば、この場合のXとは、Yという行為をするような私たちの仲間であってXと分かるような特徴を持っているものである。
Yという行為をするような仲間は、ふつう複数あります。それらはX1、X2、X3・・・などと区別できる。X1がYをしたことが分かったとすると、その経験は(X1、Y)と表現することで記憶できます。次に同じような状況になったときには学習記憶した(X1、Y)を思い出すことで、ふたたび(X1、Y)が起こるだろうと予測できる。こうして、今後のX1の行動を予測できることで生活が便利になる。この便宜のために、(X1、Y)のような自他感知世界での憑依機構をつかう予測学習のシステムが進化して私たちの身体に備わった、と(拙稿の見解では)考えられます。
同じように、X2がYをすれば(X2、Y)と表現することで、X2の動きが分かる。
特別の場合としては、このXが自分と分かるような特徴を持っていれば、それは自分ということになる。この場合、(X、Y)は(私、Y)となって、自分の行動を表現し記憶し、予測します。