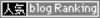そもそも、ある人が生きているかどうかが私たちの内部に起こす変化とはどういうものなのか? その人が生きていれば、私たちはその人とこれからどういうふうに関わるのだろうか、と思います。その人がこれからすることは何だろうか、と思うこともできる。しかしその人がもう生きていない、となると、こういうことを思うことはありません。
その人が生きていてもうすぐ会える、とか、明日会わなければならない、とかいう場合、私たちはその人と会ったときどういう関係になるのか考えます。予測します。どうしようか、とか、どうなるだろうか、とか、期待します。もうしばらくは会わないという関係ならば、あまり深く考えませんね。それでも、時々思い出してどうしているか、と知りたくなったりします。
ある人が生きているか生きていないかということは、こういうことでしょう。それはその人のことを語ったり、思い出したりする私たちの内部の問題である、といえます。
こういう使い方をするために、私たちはそもそも「生きる」という言葉を作って、長い間使っていた。そのうち意味がだんだん広がってきて、「生きる」という言葉は、生物が生存するというような意味になりました。この使い方では、「生きる」という言葉は、客観的に見て生きているかいないかを示すために使われます。この新しい言葉の使い方は、物事を客観的にあるいは科学的に正確に記述するのには便利でよかった。しかしまた人間は、自分自身をも客観的に語る必要を見出してこの語を使うようになる。そうなると、自分を含めた物事を客観的に語るにはますます便利になる反面、いわゆる自己遡及的表現からくる哲学的混乱が現れてきます。
「私が死んだら」とか「私は生きているから」とか自分について語る自己遡及的表現は、すぐに哲学的混乱を呼び起こします。この哲学的混乱を何か神秘的で深淵なものだと錯覚すると、「いのち」、「人生」、「自分の死」というような神秘的概念に思いを巡らすことが高尚な哲学のように思い込んでしまう恐れがあります。
この問題に関して拙稿の見解を言ってしまえば、これは言葉の使い方の混乱であって、神秘でも高尚でもない。「いのち」、「人生」、「私の死」というような言葉は、もともと意味が混乱するように作られてしまった不安定な概念です(拙稿7章「命はなぜあるのか?」第2部p25、拙稿第3部「私はなぜ死ぬのか?」
)。こういう言葉を深刻に受け取ることは危ない。薄氷の上を歩くように、すぐ踏み抜いてしまう恐れがあります。
人が、生きる、というとき、私たちは問題なくその言葉を使うことができる。しかし、私が生きる、というとき、私たちはその意味をきちんと理解することはできません。
私たちが、ある人が生きていると思うということは、いずれその人に会えるだろう、あるいはその人がこれからすることを見聞きすることができるだろう、と思う、ということです。私たちが「ある人が生きている」というとき、話し手も聞き手もそう思っています。ところが、話し手が「私は生きている」といったとすると、これは奇妙な言い方に聞こえますね。しかしこれは文法的には誤りではありません。文法で形式的に説明すれば、この文は、「ある人が生きている」という文の第三人称の主語を第一人称に置き換えた文だというだけです。
実際、どんな場合に「私は生きている」という文が使われるのでしょうか?
「おーい、聞こえるか?ジョン!生きているか?」「俺は生きているよ」というような場面。マンガではよくありそうです。
「俺は生きているよ」という返事を聞いた聞き手は、ああよかった、ジョンと一緒に家に帰ることができる可能性が残っている、そうなるようにがんばろう、と思うでしょう。そう思うことが「私は生きている」という文の意味です。しかし特殊な意味ですね。注意しなければいけないことは、このような意味は、聞き手にとっての意味でしかなく、話し手にとっては変な意味になっている点です。実際、「私は生きている」というとき私は生きているに決まっているし、私が生きていないときは「私は生きている」とも何とも言うはずがないのですから、この文は話し手にとって何の情報もない。
これは独り言で「私は生きている」というときにも当てはまることです。「私は生きている」と独り言を言ってみたところで、何も意味がない。生きている私が「私は生きている」と言っているだけで言っても言わなくても何も変わらない、と思えます。つまりこの文は、これを語っても聞いても、新しいことが分かるわけではない。そうであるとすれば、「私は生きている」という文の内容は空虚なのではないか。意味はカラではないか、と思えます。
しかし、そう簡単に切り捨ててしまわないで、もう少し、この文を口にする場合の話し手の気分というようなものを想像してみましょう。
拙稿19章(私はここにいる
)である小説の例を引いて書きましたが、声を失って瀕死の悪役が筆談で「私はここにいる」と書き残す。このとき、この「私はここにいる」という言葉は独り言ではあるが、それと同時に相手役、読者、あるいは世界中のすべての人間に対して叫んでいる言葉でもある。「私がこれから何をするか、それを見てくれ。私がこれからすることを、あなたと同じ人間が何かを思ってしているのだと認めてくれ」と叫んでいる、といえます。それは、もちろん、自分がそう思いたいからです。そう思うことで、自分が生きていると感じることができる。人はだれもが、死ぬ間際に、あるいは日常的にいつでも、そういう気持ちを持っている、ということでしょう。
人が生きている、という言葉は(拙稿の見解では)、人が仲間とともに客観的な世界を共有している、という意味です。これは現代人の間でよく使われている医学的生物学的な生死の概念とは違って、生きているという言葉のもともとの意味だった、といえます。医学的生物学的な生死の概念は、近代以降、科学が発展するにつれて、言葉が作られたときの元来の意味から外れていって物質現象を描写する概念になってしまった、といえます。それはそのほうが、近代あるいは現代の社会で物事を語り合い、適切に処理していくのに効率的であったからでしょう。
時代とともに言葉の意味がずれていくとしても、いずれにせよ、どの時代でも、人は仲間とともにこの世界の中にいる。自分で自分はそうだと思っています。人間は皆そうだと思っています。そう思うことで生きている。そういう生き方がふつうの人の生き方でしょう。つまりこれは、いわば、生きるという生き方です。
それで、そうでない生き方があるのか?そういう疑問が考えられるでしょう。しかし、生き方、という言葉で言ってしまった瞬間に、私たちは、仲間とともに客観的な世界を共有している、という暗黙の前提を認めてしまっています。
そうでなければ、生きるという言葉の意味が出てこない。現代人の私たちが語り合うときでも、人が生きる、というときの言葉の意味は、単に医学的生物学的な生死をいっているのではなくて、その人が何かをしている姿を仲間に見られている、認められている、という暗黙の想定があります。
互の姿を注目し合う仲間がいて、互にこれからどう動くのかを注目し合っていて、仲間のその視線を意識しながら動く場合に、人は生きている、といえます。極端な例として、まったく人の目から隔絶された空間に生息する人がいたとして、その人がしたことが他の人々から見てまったく痕跡も残らないとしたら、その人は生きていたとはいえません。その状況を本人も理解していたとすれば、自分でも生きていると思えないはずです。ただし、ふつう本人はそういう絶望的な状況でも自分の置かれた状況を正しく理解できずに、自分が今生きていることで何らかの生きた痕跡が残り、いつかだれかがそれを見つけてくれるだろうと楽観的に想像するものですから、自分が生きていないと思う人は実際、現実の人間としてはいないでしょう。
つまり、人間はどんな状況に置かれていても、たとえ絶望的な孤独状態にあっても、あるいは明らかに目前に死が迫っていても、自分がこれからしようとしていること、あるいはいま思っていることが何らかの痕跡を残していつの日かそれがだれかの目に触れるはずだ、という思いを捨てることはできません。