
僕はビル・メイズについては全く知らない。
ジャズの世界においてミュージシャンのことを知ろうと思っても
なかなか情報を仕入れるのが難しかったりする。
そもそも興味を持たなければ、ビル・メイズというピアニストの名前に
かすることもなく人生を終えてしまうことだってあるのだ。
『Tokyo TUC』の会場はコンサート会場と比較すると
とても小さい。
ジャズの生演奏をコンサート会場で行うか、
それとも小さなライブ・ハウスで行うかはその演奏の聞こえ方も違ってくる。
今回、僕が座ったのはまさにジョー・ラバーベラの真ん前である。
ドラムセットが目の前に並び、
通るときには本当に数センチの間を抜けていくような場所だ。
目の前でジャズドラムの妙技を見ることができるというのは
コンサートには無い醍醐味である。
今回、ビル・メイズはライブが始まる前からちょくちょくと会場で談笑を楽しんでいた。
こういったフランクな雰囲気が『Tokyo TUC』にはある。
ピアノの前に座ったビル・メイズはすでにテンションが高い。
1曲目はおそらく「モーニン」だった。
あの「蕎麦屋の出前のアンちゃんが口笛で吹いた」というぐらいの有名曲だ。
ライブを始めるにはちょうどイイほどの景気づけだ。
ビル・メイズの演奏は、いい意味で非常にノリがよかった。
テクニックもあるし、自分を鼓舞して演奏を盛り上げようとするところも
ライブならではである。
日本人のジャズの楽しみ方にも通じるのだが、
ジャズは静かに聴くものだという意識があり、ソロ終わりに拍手という
ある種型にはまった聴き方がある。
まぁ、それはそれでいいのだろうが、
ビル・メイズは「もっと食いついてこいよ」といった視線をちらちらと見せていた。
僕も先陣を切ってというタイプではないので、申し訳なく思う。
それでもちゃんと「やっぱり生でジャズを聴くのはいいよなぁ」と思っていましたよ。
さて、ジョー・ラバーベラであるが、かなり力強い印象を受けた。
ブラッシングで緩やかに通せそうな曲でも、
スティックに持ち替えてリズムを叩き出し、強弱の機微がしっかりとしている。
後期のエヴァンスにも通じるのだが、エヴァンスは曲の中で拍を意図的に変えていた。
当然、それにベースとドラムは対応しなくていけない。
ビル・メイズも同様にリズムを引き延ばしたり、縮めたりした。
さすが、ジョー・ラバーベラである。
クイッとリズムが変わり、魔法のように曲の印象が変わる。
メロディーは一本の糸のように続くのだが、
そこにどうリズムを打ち込むかで曲想が変わってくるのはおもしろい。
演奏を聴いてみてエヴァンスがザ・ラスト・トリオで求めた形と音が、
少しばかり実感できたのでよかった。
おそらくエヴァンスは晩年に力強さを求めていたのだろう。
それがマーク・ジョンソンというベーシストとジョー・ラバーベラというドラマーに
つながっていったのと思う。
エヴァンス関係で「ワルツ・フォー・デビィ」と
「ユー・マスト・ビリーブ・イン・スプリング」をやった。
「ワルツ」は、本アルバムと同様最初はスローで後々テンポを上げていった。
「ユー・マスト」は、なかなか本アルバムの静寂感を超えるのは難しかったようだ。
あとセロニアス・モンクの曲も2曲ほど取り上げていた。
僕が聴きに行くライブではモンクの曲がよく取り上げられる。
つまりそれだけ魅力的な曲がそろっているということなのだろう。
『Tokyo TUC』の壁にはモンクの写真があり、
ビル・メイズは冗談でモンクに話しかけ、会話をしていた。
演奏終了後、意を決してジョー・ラバーベラに近づく。
ぜひとも『パリ・コンサート』にサインが欲しかった。
図々しいとは思うが、エヴァンス本人に会うことができない今、
エヴァンスと共演していたミュージシャンに会うということは
僕にとっては重要なことなのだ。
最初にビル・メイズと共演をしているアルバムにサインをしてもらう。
これは礼儀だ。
その後、『パリ・コンサート』を2枚差し出す。
一瞬驚いた表情のジョー・ラバーベラ。
「僕はこのアルバムが好きなんです」とつたない英語で伝えると
「ミー・トゥ」と笑顔でサインをしてくれ、握手をしてくれた。
リップ・サービスであったとしても、そっと握ったあの大きな手は忘れない。
あの手が幾多の日々に、数々の名演を叩き出してきたのだ。
ジャズの世界においてミュージシャンのことを知ろうと思っても
なかなか情報を仕入れるのが難しかったりする。
そもそも興味を持たなければ、ビル・メイズというピアニストの名前に
かすることもなく人生を終えてしまうことだってあるのだ。
『Tokyo TUC』の会場はコンサート会場と比較すると
とても小さい。
ジャズの生演奏をコンサート会場で行うか、
それとも小さなライブ・ハウスで行うかはその演奏の聞こえ方も違ってくる。
今回、僕が座ったのはまさにジョー・ラバーベラの真ん前である。
ドラムセットが目の前に並び、
通るときには本当に数センチの間を抜けていくような場所だ。
目の前でジャズドラムの妙技を見ることができるというのは
コンサートには無い醍醐味である。
今回、ビル・メイズはライブが始まる前からちょくちょくと会場で談笑を楽しんでいた。
こういったフランクな雰囲気が『Tokyo TUC』にはある。
ピアノの前に座ったビル・メイズはすでにテンションが高い。
1曲目はおそらく「モーニン」だった。
あの「蕎麦屋の出前のアンちゃんが口笛で吹いた」というぐらいの有名曲だ。
ライブを始めるにはちょうどイイほどの景気づけだ。
ビル・メイズの演奏は、いい意味で非常にノリがよかった。
テクニックもあるし、自分を鼓舞して演奏を盛り上げようとするところも
ライブならではである。
日本人のジャズの楽しみ方にも通じるのだが、
ジャズは静かに聴くものだという意識があり、ソロ終わりに拍手という
ある種型にはまった聴き方がある。
まぁ、それはそれでいいのだろうが、
ビル・メイズは「もっと食いついてこいよ」といった視線をちらちらと見せていた。
僕も先陣を切ってというタイプではないので、申し訳なく思う。
それでもちゃんと「やっぱり生でジャズを聴くのはいいよなぁ」と思っていましたよ。
さて、ジョー・ラバーベラであるが、かなり力強い印象を受けた。
ブラッシングで緩やかに通せそうな曲でも、
スティックに持ち替えてリズムを叩き出し、強弱の機微がしっかりとしている。
後期のエヴァンスにも通じるのだが、エヴァンスは曲の中で拍を意図的に変えていた。
当然、それにベースとドラムは対応しなくていけない。
ビル・メイズも同様にリズムを引き延ばしたり、縮めたりした。
さすが、ジョー・ラバーベラである。
クイッとリズムが変わり、魔法のように曲の印象が変わる。
メロディーは一本の糸のように続くのだが、
そこにどうリズムを打ち込むかで曲想が変わってくるのはおもしろい。
演奏を聴いてみてエヴァンスがザ・ラスト・トリオで求めた形と音が、
少しばかり実感できたのでよかった。
おそらくエヴァンスは晩年に力強さを求めていたのだろう。
それがマーク・ジョンソンというベーシストとジョー・ラバーベラというドラマーに
つながっていったのと思う。
エヴァンス関係で「ワルツ・フォー・デビィ」と
「ユー・マスト・ビリーブ・イン・スプリング」をやった。
「ワルツ」は、本アルバムと同様最初はスローで後々テンポを上げていった。
「ユー・マスト」は、なかなか本アルバムの静寂感を超えるのは難しかったようだ。
あとセロニアス・モンクの曲も2曲ほど取り上げていた。
僕が聴きに行くライブではモンクの曲がよく取り上げられる。
つまりそれだけ魅力的な曲がそろっているということなのだろう。
『Tokyo TUC』の壁にはモンクの写真があり、
ビル・メイズは冗談でモンクに話しかけ、会話をしていた。
演奏終了後、意を決してジョー・ラバーベラに近づく。
ぜひとも『パリ・コンサート』にサインが欲しかった。
図々しいとは思うが、エヴァンス本人に会うことができない今、
エヴァンスと共演していたミュージシャンに会うということは
僕にとっては重要なことなのだ。
最初にビル・メイズと共演をしているアルバムにサインをしてもらう。
これは礼儀だ。
その後、『パリ・コンサート』を2枚差し出す。
一瞬驚いた表情のジョー・ラバーベラ。
「僕はこのアルバムが好きなんです」とつたない英語で伝えると
「ミー・トゥ」と笑顔でサインをしてくれ、握手をしてくれた。
リップ・サービスであったとしても、そっと握ったあの大きな手は忘れない。
あの手が幾多の日々に、数々の名演を叩き出してきたのだ。













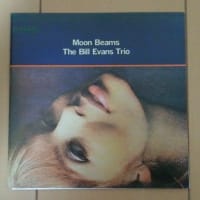
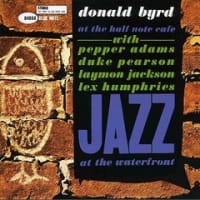

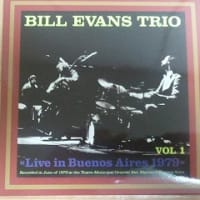


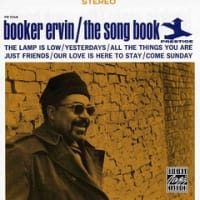
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます