
おはようございます。株式会社ティオ代表、motown21主宰の山本です。
今日は、H23年度整備白書からの報告ー2.点検カバー率は改善したものの、です。
整備白書で私が一番気にしているのが「定期点検」の実績だ。
理由は簡単。対顧客にどれだけの、促進活動が出来ているかを知るバロメーターだからだ。
車検は、期日が来れば受けるか、代替(または廃車)するので、促進活動の差が出にくい。
ところが、定期点検は「義務」ではあるが、罰則がない分、ユーザーが自主的に受けることは、
めったにない。
だからこそ、促進活動によって差がでる。
差ができるもう一つは、整備工場に対する信頼度のバロメーターにもなる。
H23年度では、専業工場の1年点検台数は、前年と同数の29台であった。
ディーラーは、564台で前年比+39台、+7.4%と伸ばした。
この結果、点検カバー率(2年車検1に対して1年点検の割合)は、
専業工場が18.1%(前年比+1.5%)、ディーラーが89.7%(同+0.9%)となった。
専業工場は、1年点検の台数が前年と同じであっても、点検カバー率が上がったのは、2年車検の
台数が減ったからだ。
ディーラーも2年車検の台数は減っているが、
1年点検の台数も増えているので、僅かだがプラスになった。
ご覧のように、専業工場とディーラーの点検カバー率は、約5倍の差がある。
専業工場は、この差をどう感じるのだろうか?
そもそもディーラーは、比較対象としていないのだろうか?
だとしたら、それはおかしなことだ。
専業工場がサービス事業のお手本にしてきたのは、ディーラーである。
そのディーラーは、総合カーサービスを目指し、バリューチェーンを加速している。
このバリューチェーンを支えるのは、「定期点検」なのだ。
定期点検に入庫になれば、車検の脱落は基本的にない。
車検の脱落がなければ、自社代替率は高まる。
自社代替率が高まれば、自社付保率は高くなる。
このように、付加価値は定期点検によって、好循環に勢いがつき高まる。
だからこそ、専業工場はもっと定期点検の入庫促進に、熱心にならなければならないのだ。
ディーラーでは、新車営業マンに車検の予約取から定期点検にチェンジしている。
それは、定期点検を追いかけることで、接触回数が増えユーザーとの絆を太く、長くできる可能性が高いからだ。
兼業工場の点検カバー率は、22.0%(2年車検287台÷1年点検63台)であった。
兼業工場もディーラーと同様に、2年車検台数は前年よりも14台マイナスであったが、
1年点検の台数は同9台増やした。
増やしのか?増えたのか?は定かでない。
問い合わせ先 株式会社ティオ















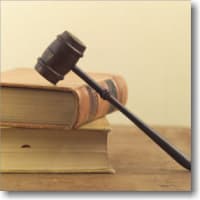




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます