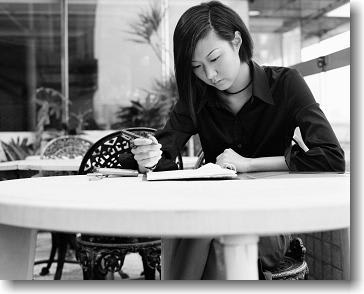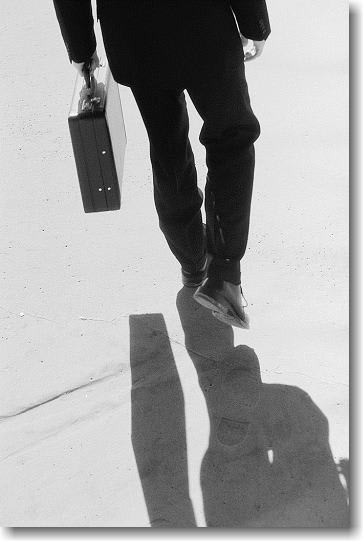おはようございます。株式会社ティオ代表、motown21主宰の山本です。
今日は、自動車整備の安全作業のすすめー2.安全衛生管理は何を管理するのか、です。
怪我や事故、あるいは体調不良を起こす原因の一つが「不安全な行動」、もう一つが
「不安全な状態」である。
労働災害の約95%が不安全な行動によって発生し、約80%が不安全な状態によって発生し、
不安全な行動と不安全な状態によって約80%が発生ているといった、データがある。
整備作業における不安全な行動とは、安全靴・防塵メガネ・作業帽子などの保護具を使わない、
ガレージジャッキでの作業時に車止めを使用しない、絶縁工具を使用しないで作業する、
あるいは誤操作や作業手順を無視するなど、ルールを無視・軽視したりするなどで起きる事故を指す。
ドラムブレーキの分解清掃作業の際に、取り外したドラムを、エアーブローして埃や塵を
飛ばしながら作業していた整備工場があったが、これらは、無知・勘違いからくる不安全な行動といえる。
こうしたことを纏めて、ヒューマンエラーなどという。
不安全な状態とは、摩耗した工具、不具合がある機械設備、工場内の整理整頓が不徹底、定期点検の不履行、
汚れや破損を放置していた、などによって起きる事故である。あるいは、作業にマッチしていない治具や工具
を使って起きる事故などもこれらに属する。
この「不安全な行動」と「不安全な状態」を品質管理でよく使われる「4M」に置き換えると、管理の対象が
見えてくる。
4Mとは、生産の4要素ともいわれるもので「Man=人」「Machine=機械」「Materiaru=材料」「Method=方法」
の頭文字とったものだ。
私はこれを、不安全な行動に対して「Man=人」と「Method=方法」が管理の対象とし、不安全な状態に対して、
「Machine=機械」と「Materiaru=材料」が管理の対象と分類してみた。
不安全な行動の「Man=人」としては、ヒューマンエラーと言われる、思い違い、聞き違いなど人間の
心理的な要因や、間違っていると分かっていても、他の人もやっている、などといったルールを
無視することに対して対策を講じていくこと。
そして、Method=方法では、やり方方法を知らずして行うことや、防護ツールを使用しないで作業することなどに
対して、対策を講じることになる。
不安全な状態の「Machine=機械」では、ハンドツールやリフトなどの省力機器にいたる全ての機械工具および設備
などが、健全な状態であり、健全な状態を維持するための管理が徹底されているかに対して対策を講じる。
「Materiaru=材料」とは、そのまま理解するのではなく、機械工具や部品や液油脂類、塗料などの置き方や
配置、あるいは量などに事故や怪我を起こすような要因が、潜んでいないかに対して対策を講じることである。
この4Mが、PDCAのサイクルで回っているかを見るために、Manezimennto=管理 を別建てとして5Mとして
もいいと思う。
いずれにしても、不安全な行動と不安全な状態を取り除けば、労働災害は限りなく「0」になる。
株式会社ティオ
お問い合わせ