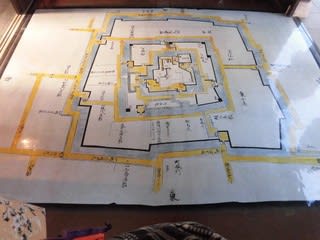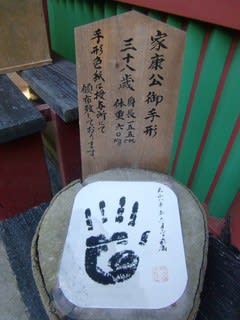歴史的な背景を持つ建物、特に日本人の技術を駆使した洋風建築は私の大好物!・・・食べ以外は本当に好物が多いと揶揄される事にすっかり慣れた私(笑)、今日も静岡市内に残る美しい建物の紹介です。
トップは昭和9年(1934)10月1日に完成した「静岡市庁舎本館」。設計者は浜松市出身の『中村与資平(よしへい)』。『辰野金吾』の事務所に入社し「豊橋市公会堂」等を手がけた人物です。建設費は当時の金額で約66万円。4階建てで床面積は4881平方メートル(坪数にして1476坪強)。

静岡庁舎本館は、昭和61年(1986年)から1989年にかけて、耐震工事と改修工事が行われ、静岡県都市景観賞を受賞。1996年に東京大学安田講堂などとともに我が国最初の登録有形文化財に指定されました。現在は1階を市民ギャラリー及び執務室。2・3階を市議会、4階を傍聴席及び会議室として使用しています。

静岡市庁舎の特徴は建物の上に2層の塔屋を重ねて望楼を置き、塔頂にスペイン風のドームをのせたこの搭。市民の熱意により修復整備された「あおい塔」は、静岡のまちのシンボルとなっています。


建物全体は象牙色のタイル貼りで、随所にテラコッタの美しい装飾が見られるのも特徴。

車寄せの部分を真横から見てみましたが、全体のタイル張りの几帳面さと装飾部分が実に見事。


それではいよいよ玄関から建物の内部へ・・・こんな美しい場所なら毎日でも訪れたい気分(笑)

玄関を入ってすぐに目に付くのは、二階への階段正面に作られた美しい造詣の明り取りの窓。窓は単に日の光を入れるだけではなく「ステンドグラス」によって作られた光の織り成す芸術空間となります。
その時々の気象や時間によって様々に姿を変える空間は、別世界と言っても過言ではありません。


ちなみにその階段は横から見るとこんな感じで、これもまた存分に建築美を堪能させてくれます。

規則正しく区切られた天井部分の細やかな細工も見飽きることなく、気がついたら首痛に(^^;)


『中村與資平』設計の建物は市内にまだ二箇所。さらに、意外な人物の設計建築もあります。 ただ、いずれも外観だけなので、まとめて明日のブログで紹介します。また静岡県内には彼が手がけた「旧三十五銀行本店」や「旧遠州銀行本店」等が現存しており、それはまた折々に紹介の予定(^-^)
訪問日:2011年11月13日