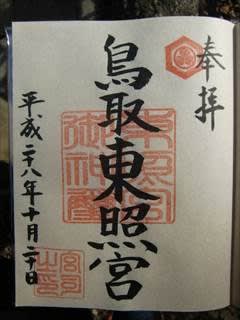鳥取市上町93、鳥取東照宮にほど近くに建つ「樗谿(おうちだに)グランドアパート(旧佐々木邸)」

昭和5年(1930)に竣工。擬洋風の意匠が加えられた建物は、当初、医院となる予定でしたがそのまま個人の住居となり、戦後は進駐軍の宿舎として増築。数少ない戦後の占領期の遺構として、2016年2月、市の指定文化財に登録されました。


和洋折衷の住宅と、進駐軍宿舎が融合した不思議な洋風建築。ネットなどに内部の公開画像があり拝見しましたが・・私は外観だけで充分。

鳥取市二階町、智頭街道と通称二階町通りの交差点角に立つ「五臓圓ビル」。ビル名は、この場所で「三心五臓圓」という薬を売っていた薬業店舗が由来で、 今も一階は五臓圓薬局として営業されています。

「角地に建つ鉄筋コンクリート造3階建、建築面積119㎡で、陸屋根とする。外壁はスクラッチタイル貼で、北隅を四分一円弧の曲面として上下に額縁を付し、パラペットも高めて隅部を強調する。昭和6年(1931)建築。鳥取市内で現存最古の本格的な鉄筋コンクリート造建築である。」文化遺産オンラインより

鳥取市元大工町にある「高砂屋」。城下町とっとり交流館サイトには「明治の中ごろに鳥取市・元大工町の薬研堀(やげんぼり)沿いに移り、綿商いを行ってこられた商家を所有者より鳥取市に寄贈していただき、まちの記憶として活かし続けるよう、「城下町とっとりの交流拠点」として整備を進めてきたものです。」

街道沿いに並ぶ住居棟 店舗棟。鳥取大震災、鳥取大火を経て残された貴重な建物は、奥の三つの蔵とともに、市登録有形文化財に指定されています。



鳥取市西町1丁目に建つ「カトリック鳥取教会」。明治21年(1888)神戸教会の巡回教会として設立されましたが、昭和18年(1943)の鳥取大震災により倒壊。現在の建物は、昭和33年(1958)の再建です。


昭和33年(1958)3月3日、「日本海テレビジョン放送株式会社」が設立。鳥取市田園町、緑地の一画には「JOJX-DTV 日本海テレビ開局の地」碑があります。

開局記念碑の横に「夢を描いて 悔いなき人生 八十二才」と刻まれた鳩のレリーフ。名前もあるのですが、画像が不鮮明で・・誰が何を意図したのか全く不明(-"-)

鳥取市西町3丁目に「童謡・唱歌」「おもちゃ」をテーマとして開館したミュージアム「わらべ館」。ネーミングからはちょっと想像できない外観は、建物の前身が「旧鳥取県立鳥取図書館」であった事に由来します。

昭和5年(1930)、公共建築物を多く手がけ、ネオゴシック様式を好んで用いたという『置塩章(おしお あきら)』氏の設計で建設された「鳥取図書館」。

昭和17年(1952)、鳥取を襲った大火で市街地のほとんどの建物が焼失する中、かろうじて焼失を免れた旧図書館でしたが老朽化により保存困難となり・・。1995年7月7日、山本浩三氏の設計により、旧図書館の外観を復元した状態で、童謡・唱歌をテーマとした博物館として開設される事になりました。

歴史的建造物では無くなったものの、それでも往時の外観をとどめた建物は私の目には時代を彷彿させる歴史的建造物。むしろ何でもかんでも、今風にモダンで現代的で・・とならなかった事に感謝したい気分です。

建物入り口に置かれた“たまごオブジェ”は「誕生」「創造」の象徴。この建物が、新たな命を吹き込まれて今ここに存在する事をも表しているような、そんな気がします。

鳥取城址:久松公園入口に1973年建立の「ふるさと 音楽碑」。文部省唱歌「ふるさと」は鳥取市出身の音楽家『岡野貞一』の作曲。
♪ うさぎ追いし~かの山 こぶな釣りし~かの川 夢は今もめぐりて 忘れ難き~ふるさと ♪・・わすれがたき ふるさと・・・

訪問日:2012年4月16日