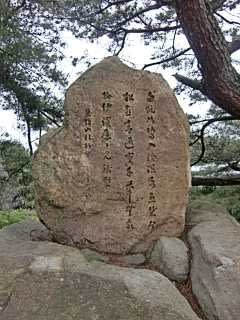丸亀市山北町に鎮座される「山北八幡宮」。御祭神は『品陀和気尊、息長帯姫命、玉依姫命』 『波仁夜須神、水波女神、天照皇大神、大物主神』の四座が合祀され、丸亀市の産土神として崇敬されています。

境内由緒「宝暦の社記によれば当社往昔は、船山に鎮座ありて船山大明神と奉称せられしが、船山後に亀山と称せらるるに至り。よって亀山大明神と称せらるるに至れりとありて、伝うる所によれば、往古亀山は船山又は波越山と称せられ、海潮山のふち迄満ち来りしを以てこの山に於て船を造り又修理せしより船山と称したり。 後年この沖に大亀来たりしを捕らえて朝廷に献ず。以来沖を丸亀沖と称し山を亀山と称するに至れりと言う。~以下略」

二の鳥居前より神域を守護されるのは、昭和10年(1935)9月23日建立のなんともおどけた表情の狛犬さん。

この顔で出迎えられたら、心の憂いなぞ一気に吹き飛んでしまいそうです。


鳥居を潜って神橋・随身門と続きますが、何とそちらにも沢山の狛犬さんが神域の守護を担当されていました。

まずは「山北八幡宮」一番の最年長で、寛政5年(1793)8月吉日建立の狛犬さん一対。出会ったのは2011年ですから当時211歳😲。何ともユニークな表情で頑張っておられます。


続いては文政12年(1829)正月吉日建立の、これもかなりお年を召した狛犬さん一対。吽形さんは頭上に宝珠を頂き、阿形さんは角を持ち、口中に玉を咬んでいます。


随身門前より神域を守護される、昭和5年(1930)1月9日建立の狛犬さん一対。

ちょっと扁平頭で、どんな場所にいても笑顔を誘うムードメーカー的存在。この底抜けに明るい笑い顔を見れば、たいていの悩みは消えるかも。


随身門を潜って参道正面、〆鳥居の向こうに、千鳥破風・唐破風を備えた華麗な拝殿が見えています。こんな鬱陶しい雨の中ですが、だからこそ尚更に神域の澄んだ静けさが心地よく感じられて思わず深呼吸。


参拝を済ませたらそのまま境内の散策。こちらの建物は絵馬殿ですが入り口は閉ざされており、内部は公開されていません。

絵馬殿には、県指定有形民族文化財「山北神社奉納 京極侯参勤交代御船揃絵馬」が収蔵されているとか。実際に見る事は出来ませんが、大きな写真付の説明が添えられています。

神馬舎の格子の隙間からは、奉納された木製の黒馬・白馬の姿を見ることができます。

白馬の優しい優雅な顔立ち、黒馬のいかにも自信に満ちた精悍な体つき・・もしかしてこの一対の御神馬は夫婦馬かもしれません。


神馬が登場したので、こちらはブロンズ製の御神馬、腹掛けには八幡宮の「三つ巴紋」ではなく、「五三の桐紋」が輝いています。

こちらのブロンズ製の犬像は、神馬の横に奉納されていたものですが、特に何かの注釈も無く、何故ここに奉納されているのかわかりません。

広大な「山北八幡宮」の境内、小さな祠も含める境内社は11社にも及び、見所はまだまだ続きますが・・・~続きは明日のブログで
参拝日:2011年6月16日