勝山市(かつやまし)は福井県北東部の嶺北地区に位置する市です。坂井市、福井市、吉田郡永平寺町、大野市に。また県を跨いで石川県加賀市、小松市、白山市に隣接。市名は一向一揆勢が立てこもった御立山を「勝ち山」と呼んだことが由来。日本有数の豪雪地帯で、特別豪雪地帯にも指定されており、西日本の日本海側最大級のスキー場「スキージャム勝山」などを有しています。

古く旧石器時代から九頭竜川の形成した河岸段丘上に人々の居住が確認されており、さらに世界三大恐竜博物館の一つ「福井県立恐竜博物館」があり、勝山市内全域をエリアとする「恐竜渓谷ふくい勝山ジオパーク」のある事でも知られています。「市の木:杉」「市の花:サツキ」を制定。
キャッチフレーズは「白山山系の豊かな自然の中で、市民参加と広域連携が進む-白山文化交流都市・恐竜王国勝山-」。

明治22年(1889)、 町村制の施行により、大野郡勝山町・猪野瀬村・荒土(あらど)村・村岡村・北郷村・北谷村・鹿谷(しかだに)村・遅羽(おそは)村・平泉寺村・野向(のむき)村が発足。
1931年、大野郡勝山町が猪野瀬村を編入。
1954年、大野郡勝山町・荒土村・村岡村・北郷村・北谷村・鹿谷村・遅羽村・平泉寺村・野向村が合併し、勝山市が発足。現在に至っています。
マンホールには「フクイラプトル」をモチーフにした恐竜と、恐竜の足跡、それに「恐竜王国」の文字と市章がデザインされています。







小さいサイズのマンホールには、「恐竜の足跡」がデザインされています。




更に小さいサイズのマンホールには「フクイラプトル」が二匹仲良く並んでいます。このデザインは通信などの大きな蓋のワンポイントにも使われていました。




昭和29年(1954)9月1日制定の市章は、【勝山のカ、ツ、山をイメージして組み合わせたもので、福井、大野、金沢の三方面への発展を三角の各頂点であらわし、丸は和合、三角はどっしりとした安定性を意味し、三角と丸を組み合わせて将来の発展を意味します。】公式HPより



『チャマゴン』がデザインされたタイルプレート。

「市の花:さつき」

勝山市のアイドルキャラクター『チャマゴン』と、ガールフレンドの『チャマリン』。いつでも何処からでも、恐竜のまち”勝山をPRしています。

撮影日:2012年6月13日&2017年9月30日&2018年月日
------------------------00----------------------
2017年4月3日、第3弾として全国42自治体で50種類(計151自治体170種類)の マンホールカードの無料配布が 開始されました。「勝山市」のマンホールカードは「勝山市長尾山総合公園管理事務所」で頂けます。
1999年に設置されたマンホールには、フクイラプトルをモチーフにした恐竜がデザインされています。

【勝山市は日本一の恐竜化石産地で、1989年に始まった福井県恐竜化石発掘事業により、学術的に貴重な恐竜化石が数多く発見されています。 この成果をもとに恐竜を中心とした国内最大級の地質・古生物博物館として、「福井県立恐竜博物館」が2000年にオーブンしました。勝山市の恐竜マンホール蓋は、 肉食恐竜として日本で初めて全身骨格が復元されたフクイラプトルをモチーフにデザインしました。 色違いや恐竜の足跡のみのデザインなど様々なパターンを製作し、恐竜博物館がある「かつやま恐竜の森」敷地内や市街地に設置しています。 皆さんは何種類見つけることができるでしょうか。】
訪問日:2017年9月30日



























































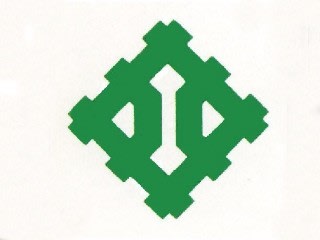




















 、
、













