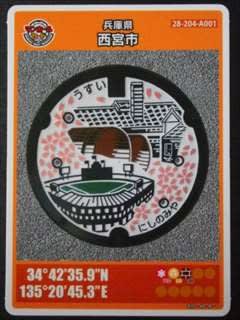尼崎市(あまがさきし)は兵庫県の南東部に位置し、中核市および中枢中核都市に指定。伊丹市、西宮市に、また県を跨いで大阪府大阪市、豊中市に隣接。「尼崎」の地名は、漁業など海に関わる仕事に就く人々を表す「尼」に、地形を表す「崎」を合わせたもので、元は現在の阪神大物駅以南周辺の臨海部を指していたとされます。江戸時代後期の事典『守貞謾稿』にも「摂の尼ヶ崎略て尼とのみも云」と記されており、俗に「尼(あま)」と略して呼ばれます。尼崎藩の城下町を中心に工業都市へと発展を遂げた事から「工都」と号し、立ち並ぶ煙突が町の誇りとされる一方、公害の都市として全国的に有名になりました。しかし近年、工業用排水・生活排水による汚染が著しかった市の中心部を流れる庄下川が、魚の住める状態にまで改善されたとして、2000年度の建設大臣賞「蘇る水100選」を受賞するなど、美化事業に力を入れています。「市の木:ハナミズキ」「市の花:夾竹桃」「市の草花: ベゴニア」を制定。
キャッチフレーズは「ひと咲き まち咲き あまがさき」

明治22年(1889)、町村制の施行により川辺郡尼崎町・立花村・小田村・園田村、武庫郡大庄村・武庫村が発足。
1916年、川辺郡尼崎町と立花村大字東難波・西難波が合併、尼崎市が発足。
1936年、川辺郡小田村と合併し、改めて尼崎市が発足。
1942年、武庫郡大庄村・武庫村・川辺郡立花村を編入。
1947年、 川辺郡園田村を編入。
マンホールには、中央に「尼崎城復元天守閣」、周囲に「市の花:夾竹桃」が描かれています。

尼崎城復元天守閣

市制100周年記念マンホールには「尼崎市市制100周年記念ロゴ」がデザインされています。

以前より設置されていたマンホールには、中央に「庄下川に棲む水辺の生き物」、周囲に「市の花:夾竹桃」が描かれています。

尼崎市役所下水道部経営企画課:展示マンホール





「近松のまち」「あまがさき」の文字と、中心に近松シンボルマークを配したデザイン。近松シンボルマークは、尼崎ゆかりの劇作家・近松門左衛門が生きた時代とその作品を象徴する「マゲ」と尼崎市のローマ字の頭文字「a」を デザイン化したもの。

近松公園の「近松門左衛門:座像」

「やめようポイ捨て」「さわやか運動参加宣言」啓発:デザインストリーマーマンホール。

大正6年(1917)4月26日制定の市章は「尼崎藩の槍印をもとに、工都を象徴する「工」の字と尼崎の「アマ」の字を図案化したものであるとされている。小田村と解消合併した昭和11年(1936)8月3日の市会で新しい市章が決定された。旧市章に小田の「小」の字を組み合せたものであった。」公式HPより



水道用の小型蓋には「市の木:ハナミズキ」と「市の花:夾竹桃」がデザインされています。



側溝蓋

JR西日本:尼崎駅にあったマンホール。中央の知章が何なのか不明です。

右から左の旧書式で「阪急」「下水道」と記されています。

撮影日:2008年5月5日&2009年9月19日
&2017年8月14日&2019年12月14日
------------------------00----------------------
2016年8月1日、第2弾として全国40自治体で44種類(累計64自治体74種類)の マンホールカードの配布が 開始されました。「尼崎市A」のマンホールカードは、「尼崎市役所下水道部経営企画課」でいただけます。(配布を終了)

2016年に設置開始されたマンホールには「尼崎市市制100周年」のロゴがデザインされています。

「尼崎市は、2016年に市政100周年の節目を迎えることを記念し、このマンホール蓋をデザインしました。背景に透かしのように 入れた紋章は尼崎市の市章です。これは、工都を表す「工」と「アマガサキ」の「ア」「マ」を図案化し、さらに小田村との合併(1936年)を 機に丸印を加えたものです。そして前面には「尼崎市政100周年」のロゴを打ち出すとともに、「下水道は浸水防いでます!」のメッセージを 下段にプリントしました。下水道の役割の中で、近年特に重要な浸水対策について、市民や事業者にもっと目を向けていただきたいとの想いから、 雨を連想させるカエルのイラストも添えました。」
配布先マンホール蓋の歴史と種類

訪問日:2017年4月16日
------------------------00----------------------
2019年12月14日、第11弾として全国61自治体で種類(累計自治体種類)の マンホールカードの配布が 開始されました。「尼崎市B」のマンホールカードは、「あまがさき観光案内所」でいただけます。

2019年に設置開始されたマンホールには「尼崎城」と「市の花:キョウチクトウ」がデザインされています。

「尼崎城は戸田氏鉄により1618年から数年の歳月をかけて築城されました。 甲子園球場の約3.5倍にも相当する敷地、3重の堀、4層の天守を据えるなど、5万石の大名にしては大きすぎる城を作らせたことから、江戸幕府は大阪の西の守りとして尼崎をいかに重要視していたかがわかります。 1873年に廃城が決まるまでは、尼崎藩政の中心として、城下町尼崎のシンボルとして威容を誇りました。 尼崎城は尼崎市に縁のある家電量販店の創業者と市民の皆様の寄付によって再び、築城しました。 市で楽しく歴史を学べる施設として整備し、平成31年3月の一般公開を記念してデザインしました。」
訪問日:2019年12月14日