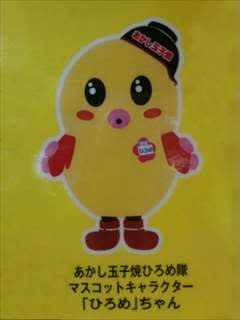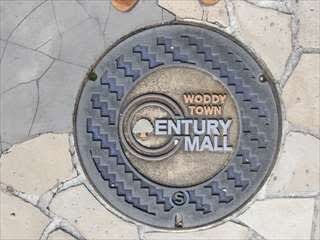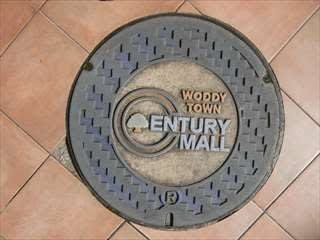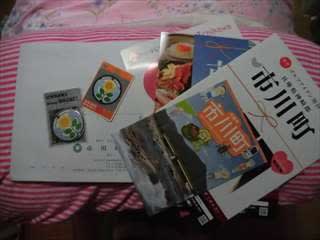昨日に続いての川西市マンホールの紹介。「清和源氏発祥の地 川西」を発信する川西市の駅前に建立された騎馬武者像は『源満仲』。清和源氏とは、清和天皇を起源とする氏族で、その歴史は今から1000年以上前にさかのぼります。清和天皇のひ孫にあたる源満仲公は、川西の多田盆地に移り住み「多田院」を創建しました。この「多田院」は現在の「多田神社」のことで、多くの観光客が訪れる観光スポットとなっています。のちの時代に全国で活躍した源氏の武将たちはこの満仲公の子孫であることから、川西市は清和源氏発祥の地といわれています。

新たに設置されたマンホールには、「多田神社南大門」と「市の花:りんどう」「市の木:さくら」がデザインされています。

池田市マンホールサミット展示蓋

「黒川公民館」と特産品の「一庫炭:菊炭」、「市の花:りんどう」がデザインされたマンホール。

池田市マンホールサミット展示蓋

マスコットキャラクター「きんたくん」がデザインされた、デザインストリーマーマンホール。

清和源氏の祖である源満仲の子・頼光の家来で、四天王の一人『坂田金時』をモデルに誕生した『きんたくん』。3歳の元気いっぱいな男の子です。

撮影日:2019年12月15日
------------------------00----------------------
マンホールカード、頂きました。
2020年12月17日、第13弾として全国50自治体で50種類(累計557自治体717種類)の マンホールカードの配布が 開始されました。「川西市B」のマンホールカードは、「川西市上下水道局経営企画課」でいただけます。
2019年に設置開始されたマンホールには「多田神社南大門」と「市の花:りんどう」と「市の木:さくら」がデザインされています。

「中央に「多田神社」南大門、その横に市花「りんどう」と市木「さくら」を配したデザインマンホール蓋です。 多田神社は、天禄元年(970年)に源満仲公によって前身である多田院として建立されました。 第56代清和天皇の曾孫にあたる満仲公は、川西の多田盆地に移り住み、武家の棟梁としてここを本拠に清和源氏の礎を築きました。 後世に名を馳せた源氏武将たちは、全てこの満仲公の子孫であることから、川西はわが国における源氏と武士団発祥の地と言われています。 毎年4月には、鎧・兜に身を固めた源氏武者が練り歩く懐古行列、川西市源氏まつりのメインイベントとしても催されます。」
------------------------00----------------------
2021年8月17日、第15弾として全国50自治体で22種類(累計557自治体717種類)の マンホールカードの配布が 開始されました。「川西市C」のマンホールカードは、「川西市上下水道局経営企画課 (3階)」でいただけます。
2019年に設置開始されたマンホールには「川西市立黒川小学校」と「市の花:りんどう」と「一庫炭(ひとくらずみ)」がデザインされています。

「川西市北部で、古くから茶席で使用されている高級炭「一庫炭」を生産している黒川地区をモチーフにしたマンホール蓋です。この地区では、一庫炭の原材料であるクヌギを約8年周期で輪伐し、人が常に手をいれることで、パッチワーク状の景観や豊かな生態系を持つ里山を作り上げてきました。また、明治時代に建てられた旧黒川小学校をそのまま利用している黒川公民館は、周辺の里山風景とマッチして、訪れる観光客の郷愁を誘っています。人の生活のために現在も利用されている里山は全国的にも珍しく、黒川地区は「にほんの里100選」や「北摂里山34」に選定されるなど「日本一の里山」と呼ばれています。」