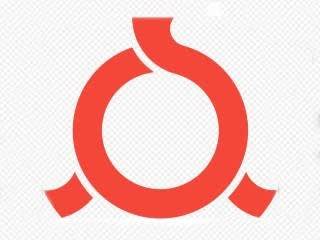福島市御山谷に鎮座される「羽黒(はぐろ)神社」。御祭神は『渟中太命(ぬなかふとのみこと)』

「福島市御山堂殿に鎮座される黒沼神社の摂社とされる。古くは稲倉魂命を祀ったものとされていたが、神仏習合した羽黒権現として信夫山伏の中核をなしてきた。古くは羽黒大権現と言われ、信夫、伊達一帯の総鎮守として信仰を集めてきた。弘化二年上棟の流造本殿は昭和52年の火災で焼失。」

駐車場を出てほんの少し坂道を上がり、石段を登って・・唐突に展開される石の道・・・に、しばし呆然。それでも福島県は遠い・・・ここまで来て引きかえせば多分二度目は無いだろう・・横に鎮座されていた山神社のお社に頭を下げ、私には危なっかし過ぎる石の道を登ります。

追い越し先を行くご亭主殿は、この道が間違っていない事を確認し、半ば不安そうに何度も立ち止まってはふり返り、私が来るのを待っています。

【名月や 物にさわらぬ 牛の角 明月】、御神坂の途中に見かけた歌碑は、江戸後期の信夫山の御山村名主で、高名な俳人でもあった『西坂珠屑(しゅせつ)』の句。嘉永6年、珠屑の弟子達によって羽黒権現の下の大石に刻んで奉納されました。

大変だなと覚悟を決めた参道も、途次途次に奉納された碑などを見ながら、気が付けば石段参道。少し明るく開けた先に朱の色が見えてきました。

広い境内の中央。朱塗りの美しい拝殿に無事に辿り着く事が出来ました。現代医学&ご亭主殿と御祭神のお陰でこうして参拝できた事に深く感謝🙏。

参拝を終えて改めて見渡す境内。中でもひときわ異彩を放つのが、鉄塔から吊り下げられた「日本一の大わらじ」。長さ12m、幅1.2、重さ2t。もうこの単位自体に現実味がわきませんが、これを担ぐのに成人男性100人ほどの力が必要との事😅 とにかく巨大です。

江戸時代から400年にわたって受け継がれ、毎年2月に開催される羽黒神社の例祭「信夫三山暁まいり」。その昔、羽黒神社の仁王門に安置されていた仁王様の足の大きさに合わせた大わらじを奉納したことが由来とされ、稲わら約3,000束を使い、2週間かけて作られます。

「大わらじ奉納の鉄塔建立」の碑。奉納された大わらじは神社脇の大杉に吊るされていましたが、昭和51年8月の羽黒神社の焼失と共に大杉も焼けてしまっい、代わりとなる鉄塔を建立した事が記されています。

境内に奉納されている石祠、二十三夜塔などに並んで中央に、寛永元年(1624)建立の「安江繁家公徳碑」。上杉時代の福島奉行を勤め、良政によって郷民に慕われた人物と伝えられています。

「道祖神碑」「石祠」等々・・

無事に参拝を終えて元来た道を引きかえした所で、最初は目につかなかった「仁王門跡」の碑を見つけました。羽黒神社の仁王門が建っていたのはこのあたりで、いつの頃からか、このわずかな土地を仁王門平とよぶようになったそうです。

駐車場近くまで戻り、見慣れたクロネコさんに何故かしらホッとして、改めて気が付く「一の宮明神」😲。ねぇ・・来るときに見かけた??いや、どうだっただろう?? 礼を失しないように、改めて拝礼🙏🙏。

今更に気が付いて唖然としたこと・・福島県護国神社参拝の際、偶然お見掛けして画像に残した神社の社号標に「縣社 黒沼神社」。権力闘争に敗れ『渟中太命』と共にこの地に逃れてきた『石姫皇后』が配祀されている神社だったという事実😱😱 なぜ、鳥居を潜らなかったのか!!😭

参拝日:2015年6月23日
🌸🍀明日は奥州三名湯に数えられる「飯坂温泉」の紹介です。