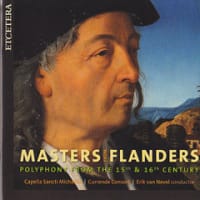ディドロ(1713-84)読書シリーズ第三作目、今度は『ラモーの甥』(本田喜代治氏、平岡昇氏訳、岩波文庫)を読んでみた。この著作は『ダランベールの夢』のさらに前、1761年の執筆とされる。
ここでディドロの著作の出版事情について簡単に記しておくと、『ラモーの甥』も『ダランベールの夢』も『ブーガンヴィール旅行記補遺』も、ディドロの生前には刊行されず、いずれも没後の出版である。これには当時の出版界の事情を知悉したディドロが、余計なトラブルを嫌って出版を避け、友人達に原稿を回覧するだけにとどめたということなどが影響している。ただ『ラモーの甥』に関しては、気ごころの知れた友人達に原稿の存在をほのめかすこともなく、誰の眼にもふれずにいたのが、ディドロの没後、それを書き写したコピーがたまたまゲーテの手に入り、1805年にゲーテのドイツ語訳によってはじめて刊行されたという経緯がある(生前、プロイセンの首都ケーニヒスベルク<現在ロシア領>を一歩も出ることのなかったカント(1724-1804)は、おそらくディドロのこうした作品の存在をほとんど知らなかったとおもわれる。18世紀においては、こうした情報のギャップは現在考えられる以上に大きい)。
さてこの『ラモーの甥』は、18世紀のフランスを代表する作曲家として知られるジャン=フィリップ・ラモー(1683-1764;当初ディドロとも良好な関係にあったが、1753年に起こった音楽論争を機に決別。『百科全書』のなかでラモーが執筆を予定していた音楽関係の記事はルソーが書くこととなった)の甥で、あちこちの金満家やサロンをわたりあるいては食(&職)を乞うという生活をしていた無頼漢の二流音楽家ジャン=フランソワ・ラモー(1716生)をモデルにしている。作品自体は、ある日の午後、パレ・ロワイヤル公園の一画にあるカフェ・ド・ラ・レジャンスでこの通称「ラモーの甥」と会った「私」が、彼と行った対話という形式をとっている。ラモーの甥とディドロは実際に顔見知りであっただけでなく、かなり仲がよかったらしい。『ラモーの甥』という作品は、はじめこの実在するラモーの甥の無頼や風変わりさをいきいきと描写してみようという意図から書き始め、書いているうちに次第に人物像がふくらんで、作中人物である「ラモーの甥」が、実在するラモーの甥を超えた独立した人格として動き出していったというあたりが、成立の経緯ではないだろうか。したがって作中人物「ラモーの甥」のなかには、ディドロ自身の姿や理想もかなり投影されているとおもう。ディドロはこの作品が気に入り、晩年まで細かく手をいれていたという。
ではさっそく、作品をみていこう。二人の出会いの挨拶はこんな感じだ。
私「相変わらず達者かね。」
彼「ええ、ふだんはね。しかし今日は上々とはいきません。」
私「どうしたんだね。まるでシレヌスのような腹をしてるじゃないか、そして顔は…」
彼「そのシレヌスとはあべこべみたいに見えそうな顔だってわけでしょう。そりゃ、わしの伯父貴をひからびさせる悪い体液が、どうやら、甥御さんを丸々と肥らせるからですよ。」
私「伯父さんといえば、時々その伯父さんに会うかね。」
彼「ええ、街を通って行くところを見かけますよ。」
私「伯父さんはなんにも君のためになることをしてくれないかね。」
彼「あの人が誰かにそんなことをしてくれるとすれば、そりゃなんかの間違いでやるんです。あれもそれなりに哲学者ですからな。あれは自分のことだけしか考えちゃいない。」
こうしてはじまった二人の会話は、なんの脈絡もなく延々と続き、その間に話題も転々として、尽きることをしらない。
私「君は、僕が、君の性格について下している判断を疑わないだろうね。」
彼「ちっとも。あんたの眼から見れば、わしはとてもいやしい、ひどく軽蔑すべき奴でさ。時には、わしの眼から見てもそうなんだ。もっとも、そんなことはめったにないですがね。わしは、自分の悪業を自分で責めるよりは得意がるほうが多いんです。あんたはいつも軽蔑ばかりしてるほうでしょう。」
私「そりゃそうだ。しかし、なぜ自分の恥を洗いざらいに僕に見せつけるんだね。」
彼「そりゃ、第一にはあんたが大体それを知ってるからですよ。それに、その残りの部分をあんたに白状しても、わしが損するよりか得するほうが大きいと見たからでさ。」
私「ほう、それはまたどういうわけでかね。」
彼「何か一芸に秀でることが大切だとしたら、そりゃとりわけ悪についてそうですな。ひとは、けちな掏摸には唾をひっかけますが、大罪人には一種の尊敬を感じないではいられないもんでさあ。その勇気にあんた方は驚き、その凶暴さにあんた方は震えあがる。性格の統一が全体として高く買われるわけです。」
最後の「性格の統一が全体として高く買われる」というのはどうやらディドロの口癖らしいが、それはともかく、いたずらに知性派ぶる「私」は、彼(ラモーの甥)のあざやかな弁舌にあっけにとられるばかりだ。そして、社会の通俗的規範や価値観からはずれた「ラモーの甥」に恐いものなどない。かくて、「ラモーの甥」をとおして当時のパリ社交界のさまざまな人物や習慣が次々と批判のやり玉にあげられ、こてんぱんにけなされていく。国王ですらその例外ではない。
ところで作品出版の特殊な事情もあり、この作品の魅力に最初に注目したのはドイツの知識人たちだった。平岡昇氏の文庫本解説によれば、ヘーゲルは、この作品の「私」と「彼」を次のように分析した。
「変革期の社会の文化的頽廃、社会全体の欺瞞の中で、それに受身になり、それに無自覚になり、自意識を喪失し、自己の存在を問題にする能力を失った連中に対して、「彼」は自覚的に明徹なあざやかな自意識の分析を見せる。(中略)真正直な意識(私)は、真と善の諸原理の顛倒に気づかず、その不動性、永遠性を信じているのだから、「思想欠如であり、無教養である」。「私」の説く道徳は徒らに雄弁であり、単調である。しかるに、下賤な意識(彼)は、その混乱と分裂を自覚することによって、自ら分裂を越え、分裂と顛倒を自覚しない真正直な意識を越える。」
そしてこの弁証法は、マルクスをも感心させたという。
しかしわれわれは、ヘーゲル、マルクス流の方向にだけこの作品を読みとる必要はあるまい。いや、そのようにだけ読み取ってしまうには、この作品はあまりにも多面的で、実にいきいきとしているのである。たとえばこの作品からさまざまな人物評や哲学的議論をすべて消し去ったとしても、18世紀後半のフランスにおける音楽事情、演劇事情を知るという観点からだけでも、この作品は実におもしろい。『ラモーの甥』は、ディドロにしか書けなかった、ユニークな傑作というべきであろう。
☆ ☆ ☆
ちなみに、上に引用した『ラモーの甥』本文の共訳者であり、また岩波文庫の作品解説を執筆している平岡昇氏は、澁澤龍彦の旧制浦和高校(現埼玉大学教養学部)におけるフランス語、フランス文学の教師である。
ここでディドロの著作の出版事情について簡単に記しておくと、『ラモーの甥』も『ダランベールの夢』も『ブーガンヴィール旅行記補遺』も、ディドロの生前には刊行されず、いずれも没後の出版である。これには当時の出版界の事情を知悉したディドロが、余計なトラブルを嫌って出版を避け、友人達に原稿を回覧するだけにとどめたということなどが影響している。ただ『ラモーの甥』に関しては、気ごころの知れた友人達に原稿の存在をほのめかすこともなく、誰の眼にもふれずにいたのが、ディドロの没後、それを書き写したコピーがたまたまゲーテの手に入り、1805年にゲーテのドイツ語訳によってはじめて刊行されたという経緯がある(生前、プロイセンの首都ケーニヒスベルク<現在ロシア領>を一歩も出ることのなかったカント(1724-1804)は、おそらくディドロのこうした作品の存在をほとんど知らなかったとおもわれる。18世紀においては、こうした情報のギャップは現在考えられる以上に大きい)。
さてこの『ラモーの甥』は、18世紀のフランスを代表する作曲家として知られるジャン=フィリップ・ラモー(1683-1764;当初ディドロとも良好な関係にあったが、1753年に起こった音楽論争を機に決別。『百科全書』のなかでラモーが執筆を予定していた音楽関係の記事はルソーが書くこととなった)の甥で、あちこちの金満家やサロンをわたりあるいては食(&職)を乞うという生活をしていた無頼漢の二流音楽家ジャン=フランソワ・ラモー(1716生)をモデルにしている。作品自体は、ある日の午後、パレ・ロワイヤル公園の一画にあるカフェ・ド・ラ・レジャンスでこの通称「ラモーの甥」と会った「私」が、彼と行った対話という形式をとっている。ラモーの甥とディドロは実際に顔見知りであっただけでなく、かなり仲がよかったらしい。『ラモーの甥』という作品は、はじめこの実在するラモーの甥の無頼や風変わりさをいきいきと描写してみようという意図から書き始め、書いているうちに次第に人物像がふくらんで、作中人物である「ラモーの甥」が、実在するラモーの甥を超えた独立した人格として動き出していったというあたりが、成立の経緯ではないだろうか。したがって作中人物「ラモーの甥」のなかには、ディドロ自身の姿や理想もかなり投影されているとおもう。ディドロはこの作品が気に入り、晩年まで細かく手をいれていたという。
ではさっそく、作品をみていこう。二人の出会いの挨拶はこんな感じだ。
私「相変わらず達者かね。」
彼「ええ、ふだんはね。しかし今日は上々とはいきません。」
私「どうしたんだね。まるでシレヌスのような腹をしてるじゃないか、そして顔は…」
彼「そのシレヌスとはあべこべみたいに見えそうな顔だってわけでしょう。そりゃ、わしの伯父貴をひからびさせる悪い体液が、どうやら、甥御さんを丸々と肥らせるからですよ。」
私「伯父さんといえば、時々その伯父さんに会うかね。」
彼「ええ、街を通って行くところを見かけますよ。」
私「伯父さんはなんにも君のためになることをしてくれないかね。」
彼「あの人が誰かにそんなことをしてくれるとすれば、そりゃなんかの間違いでやるんです。あれもそれなりに哲学者ですからな。あれは自分のことだけしか考えちゃいない。」
こうしてはじまった二人の会話は、なんの脈絡もなく延々と続き、その間に話題も転々として、尽きることをしらない。
私「君は、僕が、君の性格について下している判断を疑わないだろうね。」
彼「ちっとも。あんたの眼から見れば、わしはとてもいやしい、ひどく軽蔑すべき奴でさ。時には、わしの眼から見てもそうなんだ。もっとも、そんなことはめったにないですがね。わしは、自分の悪業を自分で責めるよりは得意がるほうが多いんです。あんたはいつも軽蔑ばかりしてるほうでしょう。」
私「そりゃそうだ。しかし、なぜ自分の恥を洗いざらいに僕に見せつけるんだね。」
彼「そりゃ、第一にはあんたが大体それを知ってるからですよ。それに、その残りの部分をあんたに白状しても、わしが損するよりか得するほうが大きいと見たからでさ。」
私「ほう、それはまたどういうわけでかね。」
彼「何か一芸に秀でることが大切だとしたら、そりゃとりわけ悪についてそうですな。ひとは、けちな掏摸には唾をひっかけますが、大罪人には一種の尊敬を感じないではいられないもんでさあ。その勇気にあんた方は驚き、その凶暴さにあんた方は震えあがる。性格の統一が全体として高く買われるわけです。」
最後の「性格の統一が全体として高く買われる」というのはどうやらディドロの口癖らしいが、それはともかく、いたずらに知性派ぶる「私」は、彼(ラモーの甥)のあざやかな弁舌にあっけにとられるばかりだ。そして、社会の通俗的規範や価値観からはずれた「ラモーの甥」に恐いものなどない。かくて、「ラモーの甥」をとおして当時のパリ社交界のさまざまな人物や習慣が次々と批判のやり玉にあげられ、こてんぱんにけなされていく。国王ですらその例外ではない。
ところで作品出版の特殊な事情もあり、この作品の魅力に最初に注目したのはドイツの知識人たちだった。平岡昇氏の文庫本解説によれば、ヘーゲルは、この作品の「私」と「彼」を次のように分析した。
「変革期の社会の文化的頽廃、社会全体の欺瞞の中で、それに受身になり、それに無自覚になり、自意識を喪失し、自己の存在を問題にする能力を失った連中に対して、「彼」は自覚的に明徹なあざやかな自意識の分析を見せる。(中略)真正直な意識(私)は、真と善の諸原理の顛倒に気づかず、その不動性、永遠性を信じているのだから、「思想欠如であり、無教養である」。「私」の説く道徳は徒らに雄弁であり、単調である。しかるに、下賤な意識(彼)は、その混乱と分裂を自覚することによって、自ら分裂を越え、分裂と顛倒を自覚しない真正直な意識を越える。」
そしてこの弁証法は、マルクスをも感心させたという。
しかしわれわれは、ヘーゲル、マルクス流の方向にだけこの作品を読みとる必要はあるまい。いや、そのようにだけ読み取ってしまうには、この作品はあまりにも多面的で、実にいきいきとしているのである。たとえばこの作品からさまざまな人物評や哲学的議論をすべて消し去ったとしても、18世紀後半のフランスにおける音楽事情、演劇事情を知るという観点からだけでも、この作品は実におもしろい。『ラモーの甥』は、ディドロにしか書けなかった、ユニークな傑作というべきであろう。
☆ ☆ ☆
ちなみに、上に引用した『ラモーの甥』本文の共訳者であり、また岩波文庫の作品解説を執筆している平岡昇氏は、澁澤龍彦の旧制浦和高校(現埼玉大学教養学部)におけるフランス語、フランス文学の教師である。