「彼らはどんな工合でめぐり合ったのだろう?みんなと同じように、偶然に、だ。彼らの名前は?それが諸君に何の関係があるだろう?彼らはどこからやってきたのか?すぐ近所からだ。彼らはどこへ行くのか?いったい人間はどこへ行くか分かっているものだろうか?彼らはどんなことを話していたのか?主人のほうは何にもしゃべらなかった。ジャックは、彼の隊長がこの世でわれわれの身に起こることは、いいことにしろ、わるいことにしろ、すべて前世の因縁だ、と言っていたと言っていた。」
ディドロ晩年の傑作小説『運命論者ジャックとその主人』は、上に引用したように、小説としてはかなり変わったはぐらかしの調子ではじまる(この作品の引用はすべて小場瀬卓三氏訳<世界文学大系16、筑摩書房>による)。以下、ジャックとその主人は、どこへとも知れぬ旅の途中暇つぶしにジャックの語るその恋物語を聞くという展開になるのだが、この恋物語が陳腐なものであるだけでなく、ジャックが話を始め出すたびにいろいろな邪魔がはいって、話はいっこうに進まない。作者であるディドロ自身、その話をすすめることにはまったく気が向かないというふざけたそぶりだ。
「ジャックは自分の恋の話を始めた。昼下りだった。暑くるしかった。主人は居眠りを始めた。夜が両人を襲ったのは、野原のまんなかでだった。ふたりは道に迷っていた。主人は烈火のごとく憤り、したたかな笞が下僕の上に降り注ぎ、哀れな男はひとつぶたれるごとに「こいつもきっと前世の因縁だったんだ…」と言った。
読者諸君、ごらんのとおり、いま話は佳境に入っているが、ぼくはジャックを主人から引き離して、彼ら両人をそれぞれ、私の気に向いたいろんな偶発事件にめぐり合うことにして、ジャックの恋物語を諸君に一年でも、二年でも、三年でも待たせることができる。主人のほうを結婚させ、彼をコキュにするのに何の差支えがあろう?ジャックをあっちこっちの島に出帆させてもよい。主人をそこへ連れて行ってもいい。両人を同じ船に乗せてフランスに連れ帰ることに、何の差障りがあろう?根も葉もない話を作るのは、なんてやさしいんだ!しかし両人ともありがたからぬ一夜を過ごしただけで無事に事はすみ、諸君もまたこの一夜だけで無事放免だ。
黎明が訪れた。ふたりはふたたび馬に跨がり、その道をつづけた。ーー彼らはどこに行きつつあったんでしたっけ?諸君がぼくにこの問いを発するのは、これで二度目だ。そしてぼくがそれにこう答えるのも二度目だ。「それがどうしたっていうんだ?もしぼくが彼らの旅の話をし始めたら、ジャックの恋の話はおさらばだ…。」ふたりはしばらく黙って道をつづけた。両人がいずれも自分の憂鬱からいささか立ち直った時、主人が下僕にむかって言った。「さあ、ジャック、お前の恋の話はどこまで聞いたっけ?」」
しかし、物語(ジャックの恋の話)はなかなか進展しない。そのうちふたりが宿をとると、今度はその宿屋のおかみさんが自分が知っているある人たちの話を聞いて欲しいと、ジャックの恋物語を中断させる。
おかみさん「侯爵さまは、容赦をしない、かなり変ったご婦人にぶつかられました。そのかたはド・ラ・ポムレー夫人と申しました。身持ちもよく、家柄もりっぱで、財産もあり、身分も高い未亡人でございました。デ・ザルシさまはほかの知合いの女と全部手を切って、ひとえにド・ラ・ポムレー夫人にご執心あそばし、最大の熱心さでお言い寄りになり、およそ考えられるありったけの犠牲を払って、そのおかたを愛しているという証をお示しになり、結婚さえもお申し込みになりました。ところが、このご夫人というのが、最初の旦那さまとはたいそう不幸でございましたので…。(おかみさんは?ーーなあに?ーー燕麦の箱の鍵はどこです?ーー釘を見てごらん。そこになかったら、銭箱を見てごらん。)再婚の危険を冒すよりか、あらゆる不幸にあう危険に身をさらしたほうがよいとお考えになっておりました。」
ジャック「ああ!前世の因縁でそうきまっていたらな!」
おかみさん「このご夫人は世間からはたいそう引きこもって暮らしていらっしゃいました。(中略)侯爵の熱心な求愛ぶりは、そのお人柄の魅力や、若さや、お顔立や、いかにも本当らしい情熱の外見や、夫人のほうの孤独や、やさしさに負けやすいご性質や、ひと言で申しますれば、殿がたの誘惑にあたしたち女をゆだねてしまうすべてのものに助けられて…、(おかみさんは?ーー何だね?ーー飛脚さんですよ。ーー緑の部屋にお入れして、いつもの通りの食事を出しなさい。)効果を現しました。(中略)ところがでございますよ、旦那さま、ほんとに恋のできるのは女だけでございまして、殿がたと申しますものは、まるで恋というものがお分りになりません…。(おかみさんは?ーーなあに?ーー托鉢のお坊さんですよ。ーーここにおいでの旦那さまがたの分として12スー、あたしの分として6スーおあげして、よそに部屋を捜しに行ってもらいなさい。)数年たって、侯爵はド・ラ・ポムレー夫人の生活を、あまりに単調だとお思い始めになりました。(中略)ド・ラ・ポムレー夫人は、もう愛されてはいないという感じがなさいました。それをお確かめになる必要がございました。それをどんな工合におやりあそばしたか…。(おかみさんは?ーー行くよ、行くよ。)」
おかみさんはたびたび話を中断されるのにうんざりして、階下へ降りて行き、明らかにそれをやめさせる手だてを講じた。(中略)読者諸君、包みかくさずお話しなさい。というのは、われわれはごらんのとおり、率直であるということに調子づいているのだから。諸君は、このおかみの優雅で、冗漫なおしゃべりをほったらかして、ジャックの恋の話をふたたび始めることをお望みだろうか?ぼくとしては、どっちだっていいのだ。
とりあえず、おかみさんによるデ・ザルシ侯爵とド・ラ・ポムレー夫人の話は、何度も中断されながら結末に達するが、この挿話が『運命論者ジャックとその主人』という作品とどのような関係をもっているかは、少しも明らかではない。というより、この挿話は、物語全体とはなんの関係ももっておらず、ジャックの恋物語の進行を中断させるために挿入されただけなのだ。
ともかく、さまざまな紆余曲折を経てジャックの恋物語はいちおう完結するが、だからといって特別のことはない。それどころか、ディドロは、最後にこう付け加える。
「そしてぼくは、ここでやめる。というのは、ぼくがこのふたりの人物について知っていることはすべて諸君に話してしまったからだ。ーーでも、ジャックの恋はどうなりました?ジャックは何度も、前世の因縁で、彼の話はいつまでたっても終りにならないことになっていると言った。ぼくはジャックは正しかったことが分った。読者諸君、それが諸君をむくれさせることはよく分る。よろしい。それでは彼の話を、彼が話しやめたところでふたたび取りあげ、諸君の好きなようにつづけたまえ。あるいはアガート嬢を訪ね、ジャックが牢にぶちこまれた村の名を訊きたまえ。ジャックに会い、彼にあれこれと訊ねてみたまえ。彼は催促されるまでもなく諸君を満足させるだろう。それは彼の退屈をまぎらすだろう。ぼくがどうも怪しいと睨む十分な理由のある回想録によって、ぼくはおそらくここに欠けている部分を補うこともできるだろう。しかしそれが何の役に立つのか?ひとは真実だと思うことにしか興味を寄せないものだ。」
これはいったい、どのようなジャンルの、何を主題とした小説というべきなのだろうか?18世紀には小説というジャンルは形式として明確に成立しておらず、現代からみると風変わりな形式の作品が多い。それにしてもこの『運命論者ジャックとその主人』は、小説という形式が未完成だったために風変わりなスタイルになってしまったというより、いかなる形であれ、形式として完成されることを拒んでいる作品としかおもえない。ディドロがここで問うているのは、「物語」もしくは「作品」というもののもつ欺瞞、あるいは「完成」というもののもつ欺瞞なのではないだろうか。
そう考えると、この作品も、『ラモーの甥』などと同様いちおう仕上げられはしたものの出版されなかったという事実(執筆は1771年以降)は、真剣に考えるに値する問題ということになってくる。
ちなみに、作品タイトルの「運命論者(宿命論者)」という言葉も、この作品を読めばそれは逆説であり、ジャックは少しも「運命論者」ではないことがすぐに明らかになる。つまり、普通の意味での運命論者とは、自分の周囲に起こることをすべて運命のせいにして運命を重んじる人間のことだが、ジャックはなにかといえば「運命」を口にするものの、運命を重んじたり、自分に悲観したりしているそぶりは少しもない。ジャックのいう運命というのは、自分が自分の考えでなにかを選択してある行為をしたとしても、その行為は結果としては運命だったのだというもので、この場合、その行為(結果)が運命でそう定まっていたかどうかには少しも意味がない。偶然によって別の結果になれば、はじめからそれが運命だったのだと言うだけのことである。つまり、この作品では、すべてが運命によって決まるということとすべてが偶然によって決まるということに少しも実質的な違いがないのである。
とすると、この作品でいう「運命論者」というのは痛烈な皮肉以外のなにものでもないのだが、ここまで考えてくると、この「運命」と「偶然」にはなんの実質的な違いがないということこそ、(何ら明確な主題があるようにおもえない)この作品の大きな主題ではないかともおもえてくる。すなわち、ディドロに関して再三取り上げている無神論の問題がこれとからんでくるわけで、ここでのディドロの主張は、人間の行為は、どこかに存在する神によって必然的に定められているのではなく、偶然に左右されて決まるものであるということではないだろうか。それを示すためにディドロは、冒頭からしつこいほど作品に介入し、この作品の筋はどのようにでも変えられるのだということを強調している。それは、楽屋落ち的な笑いを狙ったものともいえるのだが、同時に、人間の行為のもつ偶然性を、これほど「リアル」に暴き立てた文学作品も希ではないだろうか。しかしこれも再三繰り返しているように、そこにディドロはいささかの皮肉をこめて読者を韜晦する。そうした偶然の所為をも、後づけで「必然」だったと強弁することはいくらでも可能なのである。であるがゆえに、われわれはそうしたレトリックに欺かれてはならないし、ある出来事が必然であるのか偶然であるのか、すなわち「神」によってあらかじめ定められているのかは、自分で判断していくしかない。作品の陰で、ディドロは、「みなさん、だまされなさんなよ」と複雑な笑い顔をみせる。
このように考えると、『運命論者ジャックとその主人』は、荒唐無稽なドタバタ喜劇の外観を装いながら、非常にすぐれた思想小説であることがわかるのである。
☆ ☆ ☆
【追記】
この『運命論者ジャックとその主人』の記事を書く際に私が読んだのは、上にも記したように小場瀬卓三氏によるかなり古い訳で、こちらは現在ほとんど入手不可能のようだ。ただ、2006年に王寺賢太、田口卓臣氏による新しい訳が出ているので(白水社)、この作品に興味をもたれた方はぜひどうぞ↓。
http://www.hakusuisha.co.jp/detail/index.php?pro_id=02758
また、この王寺・田口両氏による新訳には、丸谷才一氏の書評(毎日新聞、2007月1月21日)があるので、そちらもご紹介しておく↓。
http://mainichi.jp/enta/book/hondana/archive/news/2007/01/20070121ddm015070049000c.html
ディドロ晩年の傑作小説『運命論者ジャックとその主人』は、上に引用したように、小説としてはかなり変わったはぐらかしの調子ではじまる(この作品の引用はすべて小場瀬卓三氏訳<世界文学大系16、筑摩書房>による)。以下、ジャックとその主人は、どこへとも知れぬ旅の途中暇つぶしにジャックの語るその恋物語を聞くという展開になるのだが、この恋物語が陳腐なものであるだけでなく、ジャックが話を始め出すたびにいろいろな邪魔がはいって、話はいっこうに進まない。作者であるディドロ自身、その話をすすめることにはまったく気が向かないというふざけたそぶりだ。
「ジャックは自分の恋の話を始めた。昼下りだった。暑くるしかった。主人は居眠りを始めた。夜が両人を襲ったのは、野原のまんなかでだった。ふたりは道に迷っていた。主人は烈火のごとく憤り、したたかな笞が下僕の上に降り注ぎ、哀れな男はひとつぶたれるごとに「こいつもきっと前世の因縁だったんだ…」と言った。
読者諸君、ごらんのとおり、いま話は佳境に入っているが、ぼくはジャックを主人から引き離して、彼ら両人をそれぞれ、私の気に向いたいろんな偶発事件にめぐり合うことにして、ジャックの恋物語を諸君に一年でも、二年でも、三年でも待たせることができる。主人のほうを結婚させ、彼をコキュにするのに何の差支えがあろう?ジャックをあっちこっちの島に出帆させてもよい。主人をそこへ連れて行ってもいい。両人を同じ船に乗せてフランスに連れ帰ることに、何の差障りがあろう?根も葉もない話を作るのは、なんてやさしいんだ!しかし両人ともありがたからぬ一夜を過ごしただけで無事に事はすみ、諸君もまたこの一夜だけで無事放免だ。
黎明が訪れた。ふたりはふたたび馬に跨がり、その道をつづけた。ーー彼らはどこに行きつつあったんでしたっけ?諸君がぼくにこの問いを発するのは、これで二度目だ。そしてぼくがそれにこう答えるのも二度目だ。「それがどうしたっていうんだ?もしぼくが彼らの旅の話をし始めたら、ジャックの恋の話はおさらばだ…。」ふたりはしばらく黙って道をつづけた。両人がいずれも自分の憂鬱からいささか立ち直った時、主人が下僕にむかって言った。「さあ、ジャック、お前の恋の話はどこまで聞いたっけ?」」
しかし、物語(ジャックの恋の話)はなかなか進展しない。そのうちふたりが宿をとると、今度はその宿屋のおかみさんが自分が知っているある人たちの話を聞いて欲しいと、ジャックの恋物語を中断させる。
おかみさん「侯爵さまは、容赦をしない、かなり変ったご婦人にぶつかられました。そのかたはド・ラ・ポムレー夫人と申しました。身持ちもよく、家柄もりっぱで、財産もあり、身分も高い未亡人でございました。デ・ザルシさまはほかの知合いの女と全部手を切って、ひとえにド・ラ・ポムレー夫人にご執心あそばし、最大の熱心さでお言い寄りになり、およそ考えられるありったけの犠牲を払って、そのおかたを愛しているという証をお示しになり、結婚さえもお申し込みになりました。ところが、このご夫人というのが、最初の旦那さまとはたいそう不幸でございましたので…。(おかみさんは?ーーなあに?ーー燕麦の箱の鍵はどこです?ーー釘を見てごらん。そこになかったら、銭箱を見てごらん。)再婚の危険を冒すよりか、あらゆる不幸にあう危険に身をさらしたほうがよいとお考えになっておりました。」
ジャック「ああ!前世の因縁でそうきまっていたらな!」
おかみさん「このご夫人は世間からはたいそう引きこもって暮らしていらっしゃいました。(中略)侯爵の熱心な求愛ぶりは、そのお人柄の魅力や、若さや、お顔立や、いかにも本当らしい情熱の外見や、夫人のほうの孤独や、やさしさに負けやすいご性質や、ひと言で申しますれば、殿がたの誘惑にあたしたち女をゆだねてしまうすべてのものに助けられて…、(おかみさんは?ーー何だね?ーー飛脚さんですよ。ーー緑の部屋にお入れして、いつもの通りの食事を出しなさい。)効果を現しました。(中略)ところがでございますよ、旦那さま、ほんとに恋のできるのは女だけでございまして、殿がたと申しますものは、まるで恋というものがお分りになりません…。(おかみさんは?ーーなあに?ーー托鉢のお坊さんですよ。ーーここにおいでの旦那さまがたの分として12スー、あたしの分として6スーおあげして、よそに部屋を捜しに行ってもらいなさい。)数年たって、侯爵はド・ラ・ポムレー夫人の生活を、あまりに単調だとお思い始めになりました。(中略)ド・ラ・ポムレー夫人は、もう愛されてはいないという感じがなさいました。それをお確かめになる必要がございました。それをどんな工合におやりあそばしたか…。(おかみさんは?ーー行くよ、行くよ。)」
おかみさんはたびたび話を中断されるのにうんざりして、階下へ降りて行き、明らかにそれをやめさせる手だてを講じた。(中略)読者諸君、包みかくさずお話しなさい。というのは、われわれはごらんのとおり、率直であるということに調子づいているのだから。諸君は、このおかみの優雅で、冗漫なおしゃべりをほったらかして、ジャックの恋の話をふたたび始めることをお望みだろうか?ぼくとしては、どっちだっていいのだ。
とりあえず、おかみさんによるデ・ザルシ侯爵とド・ラ・ポムレー夫人の話は、何度も中断されながら結末に達するが、この挿話が『運命論者ジャックとその主人』という作品とどのような関係をもっているかは、少しも明らかではない。というより、この挿話は、物語全体とはなんの関係ももっておらず、ジャックの恋物語の進行を中断させるために挿入されただけなのだ。
ともかく、さまざまな紆余曲折を経てジャックの恋物語はいちおう完結するが、だからといって特別のことはない。それどころか、ディドロは、最後にこう付け加える。
「そしてぼくは、ここでやめる。というのは、ぼくがこのふたりの人物について知っていることはすべて諸君に話してしまったからだ。ーーでも、ジャックの恋はどうなりました?ジャックは何度も、前世の因縁で、彼の話はいつまでたっても終りにならないことになっていると言った。ぼくはジャックは正しかったことが分った。読者諸君、それが諸君をむくれさせることはよく分る。よろしい。それでは彼の話を、彼が話しやめたところでふたたび取りあげ、諸君の好きなようにつづけたまえ。あるいはアガート嬢を訪ね、ジャックが牢にぶちこまれた村の名を訊きたまえ。ジャックに会い、彼にあれこれと訊ねてみたまえ。彼は催促されるまでもなく諸君を満足させるだろう。それは彼の退屈をまぎらすだろう。ぼくがどうも怪しいと睨む十分な理由のある回想録によって、ぼくはおそらくここに欠けている部分を補うこともできるだろう。しかしそれが何の役に立つのか?ひとは真実だと思うことにしか興味を寄せないものだ。」
これはいったい、どのようなジャンルの、何を主題とした小説というべきなのだろうか?18世紀には小説というジャンルは形式として明確に成立しておらず、現代からみると風変わりな形式の作品が多い。それにしてもこの『運命論者ジャックとその主人』は、小説という形式が未完成だったために風変わりなスタイルになってしまったというより、いかなる形であれ、形式として完成されることを拒んでいる作品としかおもえない。ディドロがここで問うているのは、「物語」もしくは「作品」というもののもつ欺瞞、あるいは「完成」というもののもつ欺瞞なのではないだろうか。
そう考えると、この作品も、『ラモーの甥』などと同様いちおう仕上げられはしたものの出版されなかったという事実(執筆は1771年以降)は、真剣に考えるに値する問題ということになってくる。
ちなみに、作品タイトルの「運命論者(宿命論者)」という言葉も、この作品を読めばそれは逆説であり、ジャックは少しも「運命論者」ではないことがすぐに明らかになる。つまり、普通の意味での運命論者とは、自分の周囲に起こることをすべて運命のせいにして運命を重んじる人間のことだが、ジャックはなにかといえば「運命」を口にするものの、運命を重んじたり、自分に悲観したりしているそぶりは少しもない。ジャックのいう運命というのは、自分が自分の考えでなにかを選択してある行為をしたとしても、その行為は結果としては運命だったのだというもので、この場合、その行為(結果)が運命でそう定まっていたかどうかには少しも意味がない。偶然によって別の結果になれば、はじめからそれが運命だったのだと言うだけのことである。つまり、この作品では、すべてが運命によって決まるということとすべてが偶然によって決まるということに少しも実質的な違いがないのである。
とすると、この作品でいう「運命論者」というのは痛烈な皮肉以外のなにものでもないのだが、ここまで考えてくると、この「運命」と「偶然」にはなんの実質的な違いがないということこそ、(何ら明確な主題があるようにおもえない)この作品の大きな主題ではないかともおもえてくる。すなわち、ディドロに関して再三取り上げている無神論の問題がこれとからんでくるわけで、ここでのディドロの主張は、人間の行為は、どこかに存在する神によって必然的に定められているのではなく、偶然に左右されて決まるものであるということではないだろうか。それを示すためにディドロは、冒頭からしつこいほど作品に介入し、この作品の筋はどのようにでも変えられるのだということを強調している。それは、楽屋落ち的な笑いを狙ったものともいえるのだが、同時に、人間の行為のもつ偶然性を、これほど「リアル」に暴き立てた文学作品も希ではないだろうか。しかしこれも再三繰り返しているように、そこにディドロはいささかの皮肉をこめて読者を韜晦する。そうした偶然の所為をも、後づけで「必然」だったと強弁することはいくらでも可能なのである。であるがゆえに、われわれはそうしたレトリックに欺かれてはならないし、ある出来事が必然であるのか偶然であるのか、すなわち「神」によってあらかじめ定められているのかは、自分で判断していくしかない。作品の陰で、ディドロは、「みなさん、だまされなさんなよ」と複雑な笑い顔をみせる。
このように考えると、『運命論者ジャックとその主人』は、荒唐無稽なドタバタ喜劇の外観を装いながら、非常にすぐれた思想小説であることがわかるのである。
☆ ☆ ☆
【追記】
この『運命論者ジャックとその主人』の記事を書く際に私が読んだのは、上にも記したように小場瀬卓三氏によるかなり古い訳で、こちらは現在ほとんど入手不可能のようだ。ただ、2006年に王寺賢太、田口卓臣氏による新しい訳が出ているので(白水社)、この作品に興味をもたれた方はぜひどうぞ↓。
http://www.hakusuisha.co.jp/detail/index.php?pro_id=02758
また、この王寺・田口両氏による新訳には、丸谷才一氏の書評(毎日新聞、2007月1月21日)があるので、そちらもご紹介しておく↓。
http://mainichi.jp/enta/book/hondana/archive/news/2007/01/20070121ddm015070049000c.html











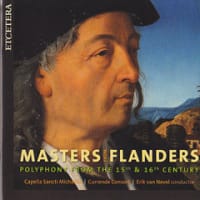


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます