ヘミングウェイ『武器よさらば』(新潮文庫、高見浩氏訳)を読んだ。先日同じくヘミングウェイの『日はまた昇る』を読んで非常に感激したということを書いたばかりなのだが、同じヘミングウェイの小説でも、『武器よさらば』は、私からするとまったくいただけない。今回はそのあたりを少し書いてみよう。
さてこの作品は、前作『日はまた昇る』を1926年に刊行したあと、その勢いをかって28年に書き始め、29年に刊行したものだ。
物語は、第一次世界大戦でイタリア軍に志願したアメリカ人フレドリック・ヘンリーと従軍看護婦キャサリン・バークリーの恋物語だが、『日はまた昇る』の女性主人公ブレットとことなり、キャサリンの性格描写があまりにもとおりいっぺんで、しかもヘンリーとキャサリンの性格のからみや対立といったものがまったく描かれていないため、作品全体は極めて単調だ。
その単調さを救うのが、戦争の描写、なかでもフレドリックの逃亡の描写なのだが、私には、この描写が物語全体とうまく結びついているようにはどうしても考えられない。戦争の場面とくらべると、全体の大枠である恋物語があまりにも牧歌的過ぎるのだ。
フレドリックとキャサリンが最初に出会った瞬間からなんのトラブルもなくスムーズにつきあい始めるのも、私がこの恋物語のなかにうまく入っていけない原因の一つとなっている。新潮文庫巻末の作品解説によれば、この恋物語はヘミングウェイ自身の19歳のときの失恋を下敷きにしているというが、よく解釈すれば、このときヘミングウェイはあまりにも若すぎて、恋愛といっても、一方通行の未熟なものだったのではないだろうか。
いずれにしても、私は『武器よさらば』という作品に対して非常に大きな不満があるのだが、こうした不満を、新潮文庫で『老人と海』訳している福田恆存氏がうまく指摘しているようにおもわれるので、以下に紹介しておく。
「ヨーロッパ文学のように、精神を精神によって、あるいは自意識を自意識によって否定するとすれば、そこに意識が意識をうたう抒情が出てくるでしょうが、肉体的行動という外面的なものによって否定すれば、どうしてもハードボイルド・リアリズムにならざるをえないでしょう。かれの作品がアメリカ文学の伝統たる通俗性をもっている理由も、またそこにあります。いかに内面意識のなかにもぐりこんでいったとしても作品の主題を展開していくモメントとして、ヘミングウェイはつねに肉体的行動にたよっているからです。
結論はこういうことになります。心理や意識の委曲を深く描きわけるという点では、たしかに第一次大戦後のヨーロッパ文学に似ているのですが、しかもなお私がアメリカ文学に不満を感じるわけは、それらがいかにヨーロッパの『意識の流れ』派や『自意識の文学』に学ぼうとも、ヨーロッパ文学においてはその現象の根底をなしていたはずの精神というものが、そこにはないからであります。絶望とか虚無的色調とかいう点では、両者共通でありますが、それはあくまで表面的、現象的な類似にすぎず、本質的にはたいへんちがっているように思われます。精神がないということは、倫理がないということであります。文学的にいえば詩がないといえましょう。」(『老人と海』新潮文庫、164~5頁)
福田氏の文章だけでは充分納得できないという方のために、『武器よさらば』のなかでヘミングウェイの文章がいかに平板なものに堕しているか、適当な箇所を抜き出して例示しておこう。ぜひ『日はまた昇る』の引用と比較していただきたい。
★ ★ ★
はるか遠くには山並みが見え、木立ちや畑の向こうにミラノも望まれた。
「さっきよりずっと爽やかな気持よ」キャサリンが言った。全身、汗で濡れた馬が、次々にケートを抜けてもどつてくる。騎手たちが彼らの気持を鎮め、木陰まで乗りつけて、そこで降りていた。
「ねえ、一杯やらない?ここで飲みながら、レースを見ましょうよ」
「よし、持ってくる」
「ボーイが持ってきてくれるわよ」キャサリンが手をあげると、厩舎の隣りのパゴダ・バーからボーイがやってきた。ぼくらは鉄の円形のテーブルに向かって腰を下ろした。
「わたしたち二人きりのほうがいいと思わない?」
「ああ」
「あの人たちにとりまかれていたら、すごく孤独な気分だった」
「ここにいると、気持が晴れ晴れとするね」
「ええ、本当にきれいなコースね」
「素晴らしいよ」
「わたし、あなたの楽しみを損ないたくないの。そう言ってくれれば、いつでもあっちにもどるわよ」
「いや」ぼくは言った。「ここにいて、飲もうじゃないか。それから水濠のところまでいって、障害レースを見よう」
「あなたって、本当にこちらの気持を汲んでくれるのね」
しばらく二人きりですごしたあとは、またみんなのところに引き返しても不快な気分にはならなかった。楽しいひとときだった。(同書218~9頁)
★ ★ ★
同じように簡潔な文体でありながら、『日はまた昇る』の文章が生き生きしているのに対し『武器よさらば』が間延びして感じられるのは、『武器よさらば』の文章や言葉のやりとりが、あまりにも情況説明に堕しているからではないだろうか。
もしかすると、『武器よさらば』の表現のなかでは、『日はまた昇る』には欠如していた「精神」や「倫理」が情緒的なものとして描かれているという反論があるかもしれないが、そうした情緒的な表現を、福田氏は、「表面的、現象的」といって批判しているのだとおもう。こうした手垢にまみれた情感は、やはり、福田氏のいう「精神」や「倫理」の対極にあるものなのではないだろうか。あるいは、「絶望」の底が浅いといってもいい。
その点をもうすこし具体的にみていくと、『日はまた昇る』のなかのブレットのキスやホテルに入っていく行動は、いろいろな動機が省略されて行動だけが端的に描写されているだけなのに対し、『武器よさらば』では、ヘミングウェイが、会話をとおしてキャサリンとフレドリックのあいだの情感や思いやりを伝えようとしているために、緊張感が感じられないのである。引用末尾の「楽しいひとときだった」の一文などは、言わずもがなの表現というべきであろう。『日はまた昇る』の記事のなかで用いた「映画のシナリオのような」という表現を用いるならば、「楽しいひとときだった」という表現は、映画的表現の対局にあるものだ。
こうした表現過剰が、簡潔な文体であるにもかかわらず、結果的に『武器よさらば』を「ソフトボイルド」な作品にしてしまっているのだ。
作品の結末であるキャサリンの死も唐突で、作品構成としては疑問。ヒロインが死ねば読者が同情し悲劇になると考えていたとすれば、ヘミングウェイはあまりにも甘い。
さてこの作品は、前作『日はまた昇る』を1926年に刊行したあと、その勢いをかって28年に書き始め、29年に刊行したものだ。
物語は、第一次世界大戦でイタリア軍に志願したアメリカ人フレドリック・ヘンリーと従軍看護婦キャサリン・バークリーの恋物語だが、『日はまた昇る』の女性主人公ブレットとことなり、キャサリンの性格描写があまりにもとおりいっぺんで、しかもヘンリーとキャサリンの性格のからみや対立といったものがまったく描かれていないため、作品全体は極めて単調だ。
その単調さを救うのが、戦争の描写、なかでもフレドリックの逃亡の描写なのだが、私には、この描写が物語全体とうまく結びついているようにはどうしても考えられない。戦争の場面とくらべると、全体の大枠である恋物語があまりにも牧歌的過ぎるのだ。
フレドリックとキャサリンが最初に出会った瞬間からなんのトラブルもなくスムーズにつきあい始めるのも、私がこの恋物語のなかにうまく入っていけない原因の一つとなっている。新潮文庫巻末の作品解説によれば、この恋物語はヘミングウェイ自身の19歳のときの失恋を下敷きにしているというが、よく解釈すれば、このときヘミングウェイはあまりにも若すぎて、恋愛といっても、一方通行の未熟なものだったのではないだろうか。
いずれにしても、私は『武器よさらば』という作品に対して非常に大きな不満があるのだが、こうした不満を、新潮文庫で『老人と海』訳している福田恆存氏がうまく指摘しているようにおもわれるので、以下に紹介しておく。
「ヨーロッパ文学のように、精神を精神によって、あるいは自意識を自意識によって否定するとすれば、そこに意識が意識をうたう抒情が出てくるでしょうが、肉体的行動という外面的なものによって否定すれば、どうしてもハードボイルド・リアリズムにならざるをえないでしょう。かれの作品がアメリカ文学の伝統たる通俗性をもっている理由も、またそこにあります。いかに内面意識のなかにもぐりこんでいったとしても作品の主題を展開していくモメントとして、ヘミングウェイはつねに肉体的行動にたよっているからです。
結論はこういうことになります。心理や意識の委曲を深く描きわけるという点では、たしかに第一次大戦後のヨーロッパ文学に似ているのですが、しかもなお私がアメリカ文学に不満を感じるわけは、それらがいかにヨーロッパの『意識の流れ』派や『自意識の文学』に学ぼうとも、ヨーロッパ文学においてはその現象の根底をなしていたはずの精神というものが、そこにはないからであります。絶望とか虚無的色調とかいう点では、両者共通でありますが、それはあくまで表面的、現象的な類似にすぎず、本質的にはたいへんちがっているように思われます。精神がないということは、倫理がないということであります。文学的にいえば詩がないといえましょう。」(『老人と海』新潮文庫、164~5頁)
福田氏の文章だけでは充分納得できないという方のために、『武器よさらば』のなかでヘミングウェイの文章がいかに平板なものに堕しているか、適当な箇所を抜き出して例示しておこう。ぜひ『日はまた昇る』の引用と比較していただきたい。
★ ★ ★
はるか遠くには山並みが見え、木立ちや畑の向こうにミラノも望まれた。
「さっきよりずっと爽やかな気持よ」キャサリンが言った。全身、汗で濡れた馬が、次々にケートを抜けてもどつてくる。騎手たちが彼らの気持を鎮め、木陰まで乗りつけて、そこで降りていた。
「ねえ、一杯やらない?ここで飲みながら、レースを見ましょうよ」
「よし、持ってくる」
「ボーイが持ってきてくれるわよ」キャサリンが手をあげると、厩舎の隣りのパゴダ・バーからボーイがやってきた。ぼくらは鉄の円形のテーブルに向かって腰を下ろした。
「わたしたち二人きりのほうがいいと思わない?」
「ああ」
「あの人たちにとりまかれていたら、すごく孤独な気分だった」
「ここにいると、気持が晴れ晴れとするね」
「ええ、本当にきれいなコースね」
「素晴らしいよ」
「わたし、あなたの楽しみを損ないたくないの。そう言ってくれれば、いつでもあっちにもどるわよ」
「いや」ぼくは言った。「ここにいて、飲もうじゃないか。それから水濠のところまでいって、障害レースを見よう」
「あなたって、本当にこちらの気持を汲んでくれるのね」
しばらく二人きりですごしたあとは、またみんなのところに引き返しても不快な気分にはならなかった。楽しいひとときだった。(同書218~9頁)
★ ★ ★
同じように簡潔な文体でありながら、『日はまた昇る』の文章が生き生きしているのに対し『武器よさらば』が間延びして感じられるのは、『武器よさらば』の文章や言葉のやりとりが、あまりにも情況説明に堕しているからではないだろうか。
もしかすると、『武器よさらば』の表現のなかでは、『日はまた昇る』には欠如していた「精神」や「倫理」が情緒的なものとして描かれているという反論があるかもしれないが、そうした情緒的な表現を、福田氏は、「表面的、現象的」といって批判しているのだとおもう。こうした手垢にまみれた情感は、やはり、福田氏のいう「精神」や「倫理」の対極にあるものなのではないだろうか。あるいは、「絶望」の底が浅いといってもいい。
その点をもうすこし具体的にみていくと、『日はまた昇る』のなかのブレットのキスやホテルに入っていく行動は、いろいろな動機が省略されて行動だけが端的に描写されているだけなのに対し、『武器よさらば』では、ヘミングウェイが、会話をとおしてキャサリンとフレドリックのあいだの情感や思いやりを伝えようとしているために、緊張感が感じられないのである。引用末尾の「楽しいひとときだった」の一文などは、言わずもがなの表現というべきであろう。『日はまた昇る』の記事のなかで用いた「映画のシナリオのような」という表現を用いるならば、「楽しいひとときだった」という表現は、映画的表現の対局にあるものだ。
こうした表現過剰が、簡潔な文体であるにもかかわらず、結果的に『武器よさらば』を「ソフトボイルド」な作品にしてしまっているのだ。
作品の結末であるキャサリンの死も唐突で、作品構成としては疑問。ヒロインが死ねば読者が同情し悲劇になると考えていたとすれば、ヘミングウェイはあまりにも甘い。











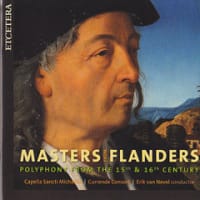


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます