久しぶりにディドロ(1713-84)の著作を読んだらおもしろくなり、勢いで『ブーガンヴィール旅行記補遺』の少し前に書かれた『ダランベールの夢』も読んでみた(最近は新しい仕事と職場環境にもだいぶ慣れたので、こうして読書する余裕が出てきた)。『補遺』が1772年頃の執筆、『ダランベールの夢』が1769年の執筆だ。
『ダランベールの夢』は、タイトルからもわかるとおり、ディドロと共同で『百科全書』の編集を行った数学者・物理学者ダランベール(1717-83)を主人公にし、その夢にかこつけて、ディドロ自身の物質観、生命観を記した著作である。
作品の形式はこれもかなり風変わりで、導入部でディドロ自身とダランベールが物質と生命についての短い対話を行い、ディドロと別れた後のダランベールが、その対話を反芻しながら夢でうなされるのを恋人レスピナス嬢がききつけ、たまたま居合わせた医師ボルドゥと、その夢を題材に対話を行う(その対話に、目を覚ましたダランベールもときどきくわわる)という構造になっている(登場人物はすべて実在)。
小場瀬卓三氏によれば、この著作は、盟友ダランベールとのあいだにある生命観(生物観)の違いを明らかにしながら、無機的な物質に生命を付与し生物とするのは、目に見えないとある要素(感性)のはたらきであるとするダランベールを、そうした要素は存在せず生命のはたらきはすべて物理的に説明可能であるとする自己の唯物論的思考の陣営に引き入れることにあったとされる。
ディドロの生命観(生物観)には、現在のわれわれからすると不十分で奇妙なところも多いが、それでも、18世紀としては最新の生物学、物理学の知見をとりいれて、「人間の思考器官の物質性を説き明かし、神の存立する余地をあますところなくうばっている」(小場瀬氏)ことは疑いない。「生命(生物)」とはなにかという問題が、神学から切り離されて科学上の問題とされていく過程を記した証言として、貴重なものといえるのではないだろうか。なかでも、神経と脳の機能についての叙述や、身体の各部分の発生についての記述は読み応えがある。ただそれを寝言として記したのは、ディドロ自身、その問題が未だ解明過程にあり、明確なこたえを与えられていないということを自覚していたためであるとも考えられる(以下の抜き書きは、「ディドロ著作集」第一巻<法政大学出版局>収載の杉捷夫氏の訳による)。
☆ ☆ ☆
まずは、冒頭のディドロとダランベールの対話。生命(生物)とは物質に過ぎず、また現在存在している生物の「種」も偶然の産物に過ぎない(別の条件下では別の「種」が誕生する可能性がある)というディドロ自身の仮説が大胆に述べられる(=神による生物の創造の否定)。
ディドロ「太陽を消したとしたら、何が起こると思うかね?植物は滅びるし、動物も滅びるだろう。さあ淋しい物音のしない地上が現出する。太陽をもう一度燃やすのだ。途端に無数の新たな出生に必要な原因を復活することになる。けれどもその間から、幾世紀の後に、今日あるわれわれの植物や動物が再び生まれるか、それとも生まれないか、僕は保証できない。」
ダランベール「なぜ、散らばっていた同じ要素が再び結合してきて、同じ結果を生み出さないのかね?」
ディドロ「それは自然においては、すべての物が相互に依存しているからだ。」
続いてディドロは、鳥の卵の孵化を思い浮かべる。
ディドロ「君にはこの二つの態度のうちどれか一つを採るよりほかに方法はないよ。すなわち卵の生気のない塊の中に、自分の存在を現わすための発展を待っていたかかくされた要素を想像するか、それともその眼に見えない要素は発展のある特定の時期に、殻を透して忍びこまれたと想像することだ。だがこの要素とは何か?空間を占めているか、それとも全然占めていないか?自分で動くことなしに、どうして来たのか、あるいはどうして出てきたのか?どこにいたのか?どこかで何をしていたのか?必要な時に創り出されたのか?存在していたのか?住居を求めていたのか?同質とすれば、物質的なものだったし、異質とすれば、発展以前における無力も、発展した結論の動物の中におけるその力も、理解することができない。自分の言葉によく耳を傾けて見たまえ。自分がかわいそうになるぜ。君はこういうことを感じるだろう。すべてを説明する単純な仮定、すなわち感性を、物質の一般的特質とするか、ないしは有機体の産物とする、この仮定を許容しないためには、君は常識と縁を絶つこととなり、神秘と矛盾と荒唐無稽の深淵の中に落ち込むことになるのだ。」
ダランベール「仮定だって!そう言うのは君の勝手だ。だが、もしそれが本質的に物質と相容れない性質だったらどうだろう?」
ディドロ「どうして感性が本質的に物質と相容れないということが君にわかるのかね。物質だって、感性だって、何だってその本質を知っていない君にわかるのかね?運動の本質、一物体の中におけるその存在、一物体から他の物体へのその伝達を、君の方がよく理解しているというのかね?」
ダランベール「感性の本質も、物質の本質も考えているわけじゃないが、感性というものは単純な、単一な、不可分な性質で、分割可能の対象ないし基体と相容れないことを知っているよ。」
ディドロ「形而上学的・神学的寝言だ。」
このように問題を提起したのち、ディドロはダランベールを眠らせる。
レスピナス(ダランベールの寝言の報告)「動物類の各時代の継続のいかなる瞬間にいまわれわれがいるのか誰が知っていよう?極地の近くでまだ人間と呼んでいる4ピエ足らずの片輪の二足獣、もう少し片輪になれば、やがて人間という名前を失うかも知れないんだが、これが過ぎ行く種族の姿でないかどうか、誰が知っていよう?動物のあらゆる種族がこれと同じことでないかどうか、誰が知っていよう?すべてが無気力な動かない一大沈殿に還元される傾向をもっていないとどうして言えるか?この無力状態の継続期間がどのくらいか、誰が知っているか?いかなる新しい種族が再び感覚あり生命のある点をもった等量の集積から生まれるか誰が知っていよう?なぜ動物が一匹もできないことがあろう?象はその原始状態においては何であったか?おそらくはいまと同じ巨大な動物だったかも知れない。おそらくはまた一原子であったかも知れない。両方の場合とも等しく可能ではないか。」
ここでぼんやりと述べられているのは、人間を含めて現存する生物の「種」はつねに変化・流転(「進化」ではない!)を続けており、それを過去に遡らせると「原子」や「沈殿」からの生命(種)の誕生となり、未来に投影すると新しい種族の誕生となるという思想だ。
ダランベールの夢想は続く。
レスピナス「また夢の続きを始めたのかしら?」
ボルドゥ「きいてみましょう。」
ダランベール「なぜ私はこういうものなのだ?それは私がこういうものでなければならなかったからだ…ここではそうだ。だが別の場所では?極地では?赤道直下では?いや土星ではどうだろう?…もし幾千里かの距離が私の種を変えるとするならば、地球直径の数千倍の距離に何ができないだろうか?…そしてもしも、この世界の光景が至るところ示しているように、万物ことごとく流転であるとしたなら、数百万世紀の継続と転変はここまたはかしこに何を生み出さないであろうか?土星上の考えたり感じたりする生物がどんなものか誰が知っていよう?…だが土星上に感情や思想があるだろうか?…なぜあってはならないか?…土星上の思考し感覚する生物は私以上の感官を持っているだろうか?…もしそうなら、土星人はかわいそうだな!…感官多ければ、欲望多しだ。」
人間が現在のような人間であるのは偶然に過ぎず、なんの必然性もない(=神による「種」の創造の否定)ということが、これもぼんやりと述べられる。
ただしデカルトを批判する文章のなかで、ディドロは、生物は(デカルトの考えたような)単純な機械ではないとしており、生物と単なる物質の違いを率直に認めている。そこから転じてディドロが関心を集中させるのは、ではその違いはそもそも何に由来するかということであり、それゆえ彼は、生命(種)の発生、個々の生命の誕生、あるいは食物摂取という無機物が有機物に変化する瞬間にこだわる。その瞬間の解明こそが、生命とは何かという問題への解答につながると考えるからだ。
しかしこの問題に明確なこたえを与えることは容易ではない。この難問にこだわりながら、その変化を神に帰すのではなく、物質そのものの問題としてどこまで即自的に解明できるか追求したのが、この『ダランベールの夢』という作品といえるだろう。すなわち、この著作全体をつらぬく基本的態度は、自然界の外ではなく、自然そのものおよび物質(実体)のなかに自然を解明する原理が内包されているとするもので、それは、「神即実体即自然」を唱えたスピノザの態度を批判的に継承したものとすることも可能だろう。
(作品の最後で、医師ボルドゥの口を借りてディドロは同性愛を否定しているが、性行為のもつ生殖としての意味を重視するディドロからすれば、それはやむをえない結論であり、それだけをもってディドロを非難しようというつもりは、私にはまったくない。こうした点を問題とするならば、むしろ、彼が自慰行為を肯定している点を評価すべきであろう。為念。)
『ダランベールの夢』は、タイトルからもわかるとおり、ディドロと共同で『百科全書』の編集を行った数学者・物理学者ダランベール(1717-83)を主人公にし、その夢にかこつけて、ディドロ自身の物質観、生命観を記した著作である。
作品の形式はこれもかなり風変わりで、導入部でディドロ自身とダランベールが物質と生命についての短い対話を行い、ディドロと別れた後のダランベールが、その対話を反芻しながら夢でうなされるのを恋人レスピナス嬢がききつけ、たまたま居合わせた医師ボルドゥと、その夢を題材に対話を行う(その対話に、目を覚ましたダランベールもときどきくわわる)という構造になっている(登場人物はすべて実在)。
小場瀬卓三氏によれば、この著作は、盟友ダランベールとのあいだにある生命観(生物観)の違いを明らかにしながら、無機的な物質に生命を付与し生物とするのは、目に見えないとある要素(感性)のはたらきであるとするダランベールを、そうした要素は存在せず生命のはたらきはすべて物理的に説明可能であるとする自己の唯物論的思考の陣営に引き入れることにあったとされる。
ディドロの生命観(生物観)には、現在のわれわれからすると不十分で奇妙なところも多いが、それでも、18世紀としては最新の生物学、物理学の知見をとりいれて、「人間の思考器官の物質性を説き明かし、神の存立する余地をあますところなくうばっている」(小場瀬氏)ことは疑いない。「生命(生物)」とはなにかという問題が、神学から切り離されて科学上の問題とされていく過程を記した証言として、貴重なものといえるのではないだろうか。なかでも、神経と脳の機能についての叙述や、身体の各部分の発生についての記述は読み応えがある。ただそれを寝言として記したのは、ディドロ自身、その問題が未だ解明過程にあり、明確なこたえを与えられていないということを自覚していたためであるとも考えられる(以下の抜き書きは、「ディドロ著作集」第一巻<法政大学出版局>収載の杉捷夫氏の訳による)。
☆ ☆ ☆
まずは、冒頭のディドロとダランベールの対話。生命(生物)とは物質に過ぎず、また現在存在している生物の「種」も偶然の産物に過ぎない(別の条件下では別の「種」が誕生する可能性がある)というディドロ自身の仮説が大胆に述べられる(=神による生物の創造の否定)。
ディドロ「太陽を消したとしたら、何が起こると思うかね?植物は滅びるし、動物も滅びるだろう。さあ淋しい物音のしない地上が現出する。太陽をもう一度燃やすのだ。途端に無数の新たな出生に必要な原因を復活することになる。けれどもその間から、幾世紀の後に、今日あるわれわれの植物や動物が再び生まれるか、それとも生まれないか、僕は保証できない。」
ダランベール「なぜ、散らばっていた同じ要素が再び結合してきて、同じ結果を生み出さないのかね?」
ディドロ「それは自然においては、すべての物が相互に依存しているからだ。」
続いてディドロは、鳥の卵の孵化を思い浮かべる。
ディドロ「君にはこの二つの態度のうちどれか一つを採るよりほかに方法はないよ。すなわち卵の生気のない塊の中に、自分の存在を現わすための発展を待っていたかかくされた要素を想像するか、それともその眼に見えない要素は発展のある特定の時期に、殻を透して忍びこまれたと想像することだ。だがこの要素とは何か?空間を占めているか、それとも全然占めていないか?自分で動くことなしに、どうして来たのか、あるいはどうして出てきたのか?どこにいたのか?どこかで何をしていたのか?必要な時に創り出されたのか?存在していたのか?住居を求めていたのか?同質とすれば、物質的なものだったし、異質とすれば、発展以前における無力も、発展した結論の動物の中におけるその力も、理解することができない。自分の言葉によく耳を傾けて見たまえ。自分がかわいそうになるぜ。君はこういうことを感じるだろう。すべてを説明する単純な仮定、すなわち感性を、物質の一般的特質とするか、ないしは有機体の産物とする、この仮定を許容しないためには、君は常識と縁を絶つこととなり、神秘と矛盾と荒唐無稽の深淵の中に落ち込むことになるのだ。」
ダランベール「仮定だって!そう言うのは君の勝手だ。だが、もしそれが本質的に物質と相容れない性質だったらどうだろう?」
ディドロ「どうして感性が本質的に物質と相容れないということが君にわかるのかね。物質だって、感性だって、何だってその本質を知っていない君にわかるのかね?運動の本質、一物体の中におけるその存在、一物体から他の物体へのその伝達を、君の方がよく理解しているというのかね?」
ダランベール「感性の本質も、物質の本質も考えているわけじゃないが、感性というものは単純な、単一な、不可分な性質で、分割可能の対象ないし基体と相容れないことを知っているよ。」
ディドロ「形而上学的・神学的寝言だ。」
このように問題を提起したのち、ディドロはダランベールを眠らせる。
レスピナス(ダランベールの寝言の報告)「動物類の各時代の継続のいかなる瞬間にいまわれわれがいるのか誰が知っていよう?極地の近くでまだ人間と呼んでいる4ピエ足らずの片輪の二足獣、もう少し片輪になれば、やがて人間という名前を失うかも知れないんだが、これが過ぎ行く種族の姿でないかどうか、誰が知っていよう?動物のあらゆる種族がこれと同じことでないかどうか、誰が知っていよう?すべてが無気力な動かない一大沈殿に還元される傾向をもっていないとどうして言えるか?この無力状態の継続期間がどのくらいか、誰が知っているか?いかなる新しい種族が再び感覚あり生命のある点をもった等量の集積から生まれるか誰が知っていよう?なぜ動物が一匹もできないことがあろう?象はその原始状態においては何であったか?おそらくはいまと同じ巨大な動物だったかも知れない。おそらくはまた一原子であったかも知れない。両方の場合とも等しく可能ではないか。」
ここでぼんやりと述べられているのは、人間を含めて現存する生物の「種」はつねに変化・流転(「進化」ではない!)を続けており、それを過去に遡らせると「原子」や「沈殿」からの生命(種)の誕生となり、未来に投影すると新しい種族の誕生となるという思想だ。
ダランベールの夢想は続く。
レスピナス「また夢の続きを始めたのかしら?」
ボルドゥ「きいてみましょう。」
ダランベール「なぜ私はこういうものなのだ?それは私がこういうものでなければならなかったからだ…ここではそうだ。だが別の場所では?極地では?赤道直下では?いや土星ではどうだろう?…もし幾千里かの距離が私の種を変えるとするならば、地球直径の数千倍の距離に何ができないだろうか?…そしてもしも、この世界の光景が至るところ示しているように、万物ことごとく流転であるとしたなら、数百万世紀の継続と転変はここまたはかしこに何を生み出さないであろうか?土星上の考えたり感じたりする生物がどんなものか誰が知っていよう?…だが土星上に感情や思想があるだろうか?…なぜあってはならないか?…土星上の思考し感覚する生物は私以上の感官を持っているだろうか?…もしそうなら、土星人はかわいそうだな!…感官多ければ、欲望多しだ。」
人間が現在のような人間であるのは偶然に過ぎず、なんの必然性もない(=神による「種」の創造の否定)ということが、これもぼんやりと述べられる。
ただしデカルトを批判する文章のなかで、ディドロは、生物は(デカルトの考えたような)単純な機械ではないとしており、生物と単なる物質の違いを率直に認めている。そこから転じてディドロが関心を集中させるのは、ではその違いはそもそも何に由来するかということであり、それゆえ彼は、生命(種)の発生、個々の生命の誕生、あるいは食物摂取という無機物が有機物に変化する瞬間にこだわる。その瞬間の解明こそが、生命とは何かという問題への解答につながると考えるからだ。
しかしこの問題に明確なこたえを与えることは容易ではない。この難問にこだわりながら、その変化を神に帰すのではなく、物質そのものの問題としてどこまで即自的に解明できるか追求したのが、この『ダランベールの夢』という作品といえるだろう。すなわち、この著作全体をつらぬく基本的態度は、自然界の外ではなく、自然そのものおよび物質(実体)のなかに自然を解明する原理が内包されているとするもので、それは、「神即実体即自然」を唱えたスピノザの態度を批判的に継承したものとすることも可能だろう。
(作品の最後で、医師ボルドゥの口を借りてディドロは同性愛を否定しているが、性行為のもつ生殖としての意味を重視するディドロからすれば、それはやむをえない結論であり、それだけをもってディドロを非難しようというつもりは、私にはまったくない。こうした点を問題とするならば、むしろ、彼が自慰行為を肯定している点を評価すべきであろう。為念。)











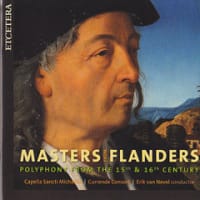


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます