人形浄瑠璃を鑑賞しながら、死と愛について考えていたら、はからずも渋沢龍彦『神聖受胎』(現代思潮社、1962年)のなかに、同趣の文章を発見した。となるとこれは、「人間の美徳とはなにか?」という現在進行中の小テーマとも直結する問題だということになるので、その辺を意識しながら、渋沢の文章を引用・紹介してみる(その一部は、引用のさらなる引用であるけれども)。渋沢はそれを、生産性と対立する「消費の哲学」としてまとめているが、もちろんこれは、渋沢のサド観(サディズム観ではないので要注意!<笑>)とも結びついた問題である。
☆ ☆ ☆
「なぜ「性的人間」と「政治的人間」とが対立するように見えるのか、という素朴な疑問に立ちかえってみるならば、それは前者が徹頭徹尾、消費の原理に立ち、後者が徹頭徹尾、生産の原理に立つからであろう。
「生殖のための性行為は有性動物と人間とに共通しているが、明かに人間だけが、性行為からエロティックな行為をみちびき出した。すなわち、性行為とエロティックな行為を区別するものは、生殖や子孫に対する配慮につながる自然目的とは関係のない、ある心理的な探求なのだ。この基本的な定義から、わたしはただちに、わたしが最初に提出した公式へ立ちもどる。その公式とは、エロティシズムは死にまで高められた生の讃美である、ということだ。たしかに、エロティックな行為はまず第一に生の横溢であるにしても、前述のように、生の生殖に対する配慮とは関係のない、この心理的探求の目的は、死とも無縁ではないのである。そこには、大きな逆説がある。」(ジョルジュ・バタイユ『エロティシズム』序論)(『神聖受胎』~「テロオルについて」<初出は『日本読書新聞』1960年>)
☆ ☆ ☆
渋沢が引用・紹介しているバタイユのエロティシズム論のなかの、「エロティシズムは自然目的とは関係のないある心理的探求」という定義には、私もほぼ全面的に賛成である。つまり、世の中には、「異性愛=自然、同性愛=反自然もしくは不自然」という定義が一方にあり、それに対する同性愛の政治運動は、「同性愛も異性愛同様自然な行為であり、ただそれが少数者によって実践されているという違いがあるだけである」という定義を軸に動いているようにおもわれるのだが、私からすると、そもそも「異性愛=自然」という定義そのものに問題があるのであって、私がいつも感じているのは、人間の性愛は男女の間で行われるものも究極的には一種のフェティシズムや幻想の投影であって、こと人間に関する限り、自然な性愛はほとんど存在しないのではないかということだ。そう考えない限り、たとえばこのところしつこく取り上げている男女間の肛門性交やフェラチオなど、なぜそうした行為が心理的快感と繋がるか、どのようにしても説明できないのではないだろうか。また敢えて同性愛ということに関して言えば、異性愛そのものが自然なものでない以上、殊更それを反自然もしくは不自然とする理由はなにもなく、むしろ人間独自のフェティッシュな性愛のあり方からすると、「自然に」生じてくる性愛の形態なのではないだろうか。
実はこのフェティシズムの問題は、渋沢言うところの「人形愛」とも関連してくる問題なのだが、人間がなぜ人形を愛するのか、あるいは直前の記事のようになぜ人形芝居に人間が動く芝居以上に感動するのかといったことは、人間の本質、芸術の本質に深くかかわってくるとおもう。リアルなものがつねに最もすばらしいなど、ありえないのではないだろうか。さらに言えば、われわれが音楽を素晴らしいとおもったり感動したりするとき、そこにどのような「リアリティ」や「自然」があるというのだろうか。
話しを元に戻せば、ゆえに、自然と反自然を峻別し、「自然な行動」のなかに人間主義を見いだそうとするのは、渋沢的に言えば、特権階級の抑圧的な態度に他ならないということになってくるだろう。
☆ ☆ ☆
「マルクスは自然を生産的歴史の下位に置いたが、消費の哲学は、むしろ人間をひとつの自然物であるとする見方から、積極的な意義を引き出すであろう。それはあらゆる特権的状態から、人間を共通の類概念、すなわち自然のなかに引きずり込むはたらきをする。このとき、人間主義を標傍するのはプロレタリアでなくて、必ずや特権階級であろう。ひとたび自然の原理に立てば、あらゆる権力は人間にとって偶有的な状態にすぎない。技術さえ、それが社会と生産性を代表する限りにおいては、ひとつの特権的な状態としてあらわれるであろうから、消費の哲学はこれをしも警戒する。生産性の哲学が存在の権利要求と、前時代からの遺産相続に終始することによって、ともすれば永遠の権力主義とテルミドオルの反復におちいる危険があるのに対し、消費の哲学は、その本来の自然主義が、逆に権利という概念そのものを破壊し、人間に何ら特別の尊厳をも認めることを拒否する。つまり、みずからを自然物と知る人間は、じつは特権階級によってつくられ、特権階級によって与えられたにすぎないアプリオリの制度や道徳を、決して信じたりはしないのだ。」(『神聖受胎』~「生産性の倫理をぶちこわせ」<初出は『外語文化』1961年>)
☆ ☆ ☆
引用の最後の部分、「みずからを自然物と知る人間は、じつは特権階級によってつくられ、特権階級によって与えられたにすぎないアプリオリの制度や道徳を、決して信じたりはしない」という箇所に、私は、異性愛者と同性愛者が同じ地平に立って、一つの行動を行うことを可能にする論理を見いだす。
愛とエロティシズムの問題に戻ろう。今まで読んできた議論からすれば当然のことだが、実は、究極のエロティシズムには、異性愛と同性愛の違いなど存在しない。それが対立するのは、社会的生活感情の原理にべったり密着している「生活技術としてのエロティシズム」であり、渋沢の論を待つまでもなく、われわれはそうしたものをことごとしく論じる必要がどこにあるのだろうか。
☆ ☆ ☆
「最高のエロティシズムとは、死を幻視する術のことだ、とわたしは考えている。だからそれは、芸術表現として、必然的に反社会的契機を内包して育てて行かなければならない。またそれこそ、つねに芸術の拠って立つ原理でもあろう。一方、「好色」とは、ややもすると凝視しなければならない死を避け、恐怖を笑い、その他共同体的慣習で糊塗することによって成立する、低次の、約束化されたエロティシズムの形式ではなかろうか。とすれば、それは社会的生活感情の原理にべったり密着している。いったい、抵抗のないエロティシズム、生活技術としてのエロティシズムに、わたしたちはどんな価値を置いたらよいのであろう。そんなものが、かりに芸術作品のなかに紛れこんでいたからといって、これを芸術上の問題として、ことごとしく論じ立てる必要がどこにあろう。」(『神聖受胎』~「「好色」と「エロティシズム」ーー西鶴と西欧文学」<初出は『國文学・解釈と鑑賞1961年』>)
☆ ☆ ☆
ここで渋沢が論じているのは、直接的には井原西鶴文学のエロティシズムについてなのだが、誤解なきよう付け加えておけば、渋沢は西鶴文学を日常の延長線上にある好色文学のなかに組み込んではいない。作品タイトルこそ「好色」であるが、それは好色という日常を突き抜けてしまっているというのが、渋沢の西鶴観である。
☆ ☆ ☆
「「男色ほど美なる翫ひはなし」と言いつつ、西鶴はいかにも近世自由思想家(リベルタン)らしい無道徳(アナーキイ)の立場から、封建主義の倫理的衰弱のうちに最もはげしい光輝を示すエロティシズムの、極北的世界を嘆賞しているかのごとくだ。」(「「好色」と「エロティシズム」ーー西鶴と西欧文学」)
☆ ☆ ☆
「なぜ「性的人間」と「政治的人間」とが対立するように見えるのか、という素朴な疑問に立ちかえってみるならば、それは前者が徹頭徹尾、消費の原理に立ち、後者が徹頭徹尾、生産の原理に立つからであろう。
「生殖のための性行為は有性動物と人間とに共通しているが、明かに人間だけが、性行為からエロティックな行為をみちびき出した。すなわち、性行為とエロティックな行為を区別するものは、生殖や子孫に対する配慮につながる自然目的とは関係のない、ある心理的な探求なのだ。この基本的な定義から、わたしはただちに、わたしが最初に提出した公式へ立ちもどる。その公式とは、エロティシズムは死にまで高められた生の讃美である、ということだ。たしかに、エロティックな行為はまず第一に生の横溢であるにしても、前述のように、生の生殖に対する配慮とは関係のない、この心理的探求の目的は、死とも無縁ではないのである。そこには、大きな逆説がある。」(ジョルジュ・バタイユ『エロティシズム』序論)(『神聖受胎』~「テロオルについて」<初出は『日本読書新聞』1960年>)
☆ ☆ ☆
渋沢が引用・紹介しているバタイユのエロティシズム論のなかの、「エロティシズムは自然目的とは関係のないある心理的探求」という定義には、私もほぼ全面的に賛成である。つまり、世の中には、「異性愛=自然、同性愛=反自然もしくは不自然」という定義が一方にあり、それに対する同性愛の政治運動は、「同性愛も異性愛同様自然な行為であり、ただそれが少数者によって実践されているという違いがあるだけである」という定義を軸に動いているようにおもわれるのだが、私からすると、そもそも「異性愛=自然」という定義そのものに問題があるのであって、私がいつも感じているのは、人間の性愛は男女の間で行われるものも究極的には一種のフェティシズムや幻想の投影であって、こと人間に関する限り、自然な性愛はほとんど存在しないのではないかということだ。そう考えない限り、たとえばこのところしつこく取り上げている男女間の肛門性交やフェラチオなど、なぜそうした行為が心理的快感と繋がるか、どのようにしても説明できないのではないだろうか。また敢えて同性愛ということに関して言えば、異性愛そのものが自然なものでない以上、殊更それを反自然もしくは不自然とする理由はなにもなく、むしろ人間独自のフェティッシュな性愛のあり方からすると、「自然に」生じてくる性愛の形態なのではないだろうか。
実はこのフェティシズムの問題は、渋沢言うところの「人形愛」とも関連してくる問題なのだが、人間がなぜ人形を愛するのか、あるいは直前の記事のようになぜ人形芝居に人間が動く芝居以上に感動するのかといったことは、人間の本質、芸術の本質に深くかかわってくるとおもう。リアルなものがつねに最もすばらしいなど、ありえないのではないだろうか。さらに言えば、われわれが音楽を素晴らしいとおもったり感動したりするとき、そこにどのような「リアリティ」や「自然」があるというのだろうか。
話しを元に戻せば、ゆえに、自然と反自然を峻別し、「自然な行動」のなかに人間主義を見いだそうとするのは、渋沢的に言えば、特権階級の抑圧的な態度に他ならないということになってくるだろう。
☆ ☆ ☆
「マルクスは自然を生産的歴史の下位に置いたが、消費の哲学は、むしろ人間をひとつの自然物であるとする見方から、積極的な意義を引き出すであろう。それはあらゆる特権的状態から、人間を共通の類概念、すなわち自然のなかに引きずり込むはたらきをする。このとき、人間主義を標傍するのはプロレタリアでなくて、必ずや特権階級であろう。ひとたび自然の原理に立てば、あらゆる権力は人間にとって偶有的な状態にすぎない。技術さえ、それが社会と生産性を代表する限りにおいては、ひとつの特権的な状態としてあらわれるであろうから、消費の哲学はこれをしも警戒する。生産性の哲学が存在の権利要求と、前時代からの遺産相続に終始することによって、ともすれば永遠の権力主義とテルミドオルの反復におちいる危険があるのに対し、消費の哲学は、その本来の自然主義が、逆に権利という概念そのものを破壊し、人間に何ら特別の尊厳をも認めることを拒否する。つまり、みずからを自然物と知る人間は、じつは特権階級によってつくられ、特権階級によって与えられたにすぎないアプリオリの制度や道徳を、決して信じたりはしないのだ。」(『神聖受胎』~「生産性の倫理をぶちこわせ」<初出は『外語文化』1961年>)
☆ ☆ ☆
引用の最後の部分、「みずからを自然物と知る人間は、じつは特権階級によってつくられ、特権階級によって与えられたにすぎないアプリオリの制度や道徳を、決して信じたりはしない」という箇所に、私は、異性愛者と同性愛者が同じ地平に立って、一つの行動を行うことを可能にする論理を見いだす。
愛とエロティシズムの問題に戻ろう。今まで読んできた議論からすれば当然のことだが、実は、究極のエロティシズムには、異性愛と同性愛の違いなど存在しない。それが対立するのは、社会的生活感情の原理にべったり密着している「生活技術としてのエロティシズム」であり、渋沢の論を待つまでもなく、われわれはそうしたものをことごとしく論じる必要がどこにあるのだろうか。
☆ ☆ ☆
「最高のエロティシズムとは、死を幻視する術のことだ、とわたしは考えている。だからそれは、芸術表現として、必然的に反社会的契機を内包して育てて行かなければならない。またそれこそ、つねに芸術の拠って立つ原理でもあろう。一方、「好色」とは、ややもすると凝視しなければならない死を避け、恐怖を笑い、その他共同体的慣習で糊塗することによって成立する、低次の、約束化されたエロティシズムの形式ではなかろうか。とすれば、それは社会的生活感情の原理にべったり密着している。いったい、抵抗のないエロティシズム、生活技術としてのエロティシズムに、わたしたちはどんな価値を置いたらよいのであろう。そんなものが、かりに芸術作品のなかに紛れこんでいたからといって、これを芸術上の問題として、ことごとしく論じ立てる必要がどこにあろう。」(『神聖受胎』~「「好色」と「エロティシズム」ーー西鶴と西欧文学」<初出は『國文学・解釈と鑑賞1961年』>)
☆ ☆ ☆
ここで渋沢が論じているのは、直接的には井原西鶴文学のエロティシズムについてなのだが、誤解なきよう付け加えておけば、渋沢は西鶴文学を日常の延長線上にある好色文学のなかに組み込んではいない。作品タイトルこそ「好色」であるが、それは好色という日常を突き抜けてしまっているというのが、渋沢の西鶴観である。
☆ ☆ ☆
「「男色ほど美なる翫ひはなし」と言いつつ、西鶴はいかにも近世自由思想家(リベルタン)らしい無道徳(アナーキイ)の立場から、封建主義の倫理的衰弱のうちに最もはげしい光輝を示すエロティシズムの、極北的世界を嘆賞しているかのごとくだ。」(「「好色」と「エロティシズム」ーー西鶴と西欧文学」)











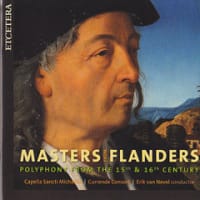


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます