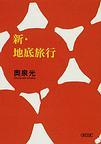「新・地底旅行」 奥泉 光 朝日文庫
「新」とは何に対しての新なのか。
言うまでもなく、ジュール・ヴェルヌが1864年に発表した「地底旅行」ですね。
この本の舞台は明治42年(1909年)日本。
ヴェルヌ作中のリーデンブロック博士の残した記録を実在のものとしてそれに習い、地底旅行に旅立つということで、この物語はまさしく元祖あってのストーリーとなっています。
しかし、ヴェルヌの地底世界を踏襲しながらも、やはりそこに現れるのは紛れもなく奥泉ワールド。
文体は夏目漱石風。セピア色の時代色を感じさせます。
富士の樹海のなかに、その洞窟の入り口はあります。
この物語の舞台が現代でないのは、地底旅行という冒険が、現在ではあまりにも立派な装備がそろいすぎて、ちっともそのおどろおどろしさをかき立てないからに違いありません。
食料は乾パンと干し肉。
銅の水筒。
ゴム底の足袋。
油紙に包んだマッチ。ろうそく。
かろうじて懐中電灯はあったようだ。でも、無論十分な光量ではないでしょう。電池もすぐ切れるし。
このようないささか心もとない装備であるが故に、なぜか余計にわくわくとした冒険心を掻き立てられるような気がします。
さて、ところがこの探検隊のメンバーがなんとも心もとない。
主人公といいますか、この物語の語り手は画家の野々村鷺舟。
その友人、口先ばかりが達者な洒落者、富永丙三郎。
天才科学者、水島鶏月。
何しろ肉体派とは全くかけ離れたこの3人。
マジ???と、思ってしまうのですが。
彼らは、先に地底探検に出て、行方不明となっている理学者稲峰博士とその令嬢都美子を探すため、(そして、もしかしたらあるかもしれない伊達家の財宝を探すため)、長い地底旅行に旅立つのでした。
最後に1人加わったのは、稲峰博士宅で働いていた女中のサト。
この娘がなんと機転のきく働き者で、体力も根性も並以上。
もっとも頼りになるのでした・・・。
大変な苦労の末、たどり着いたところは・・・
地底に広がる海。
恐竜や恐竜人のいる島。
まさに、冒険ですねえ。
そして、更なる異世界へ行く方法が実はある。
これは読んでのお楽しみ・・・ということで。
この作品は、『「我輩は猫である」殺人事件』、「鳥類学者のファンタジア」と、わずかに接点を有していて、奥泉さん自身3部作といっています。
でも、この作品だけでも十分に楽しめます。
何しろ、おかしくて、ドキドキして、ファンタジックで、深遠。
このような作品に接する事が出来たことに感謝!