最近気になる話題のひとつが、英国・ウェールズ南部の小さな町、ブリッジエンドで起きている若者による連続自殺。昨年1月からですでに17人。15歳から27歳の若者たちの早すぎる死。警察等はお互いの関連性を否定しているようですが、さて、どうなのでしょう。日本でも自殺サイトで知り合った人たちの集団自殺が後を絶たないようですし・・・ブリッジエンドでも自殺した若者の少なくとも10人が同じソーシャルネットワーキングシステムを利用していたという報道もあります・・・若者とネット利用。
フランスでも、インターネットの影響を心配する父兄が多いようで、その調査結果が22日のフィガロ紙に紹介されていました。
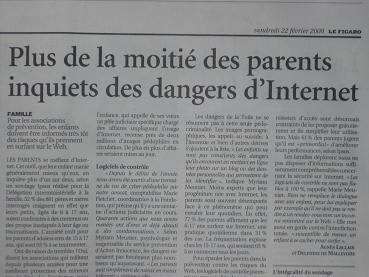
6歳から17歳までの子どもを持つ父兄にアンケートをし、801人から回答を得たそうです。その内65%がネットの好ましくない影響を恐れ、52%は子どもたちが年齢に相応しくないサイトへアクセスしているのではないかと心配しているそうです。ポルノ、小児性愛、自殺、拒食症・・・さまざまな誘惑が待ち構えているネットの世界。フランスのマス・メディアはあまり社会面的出来事を細かく紹介しないので、詳しくは分からないのですが、子どもの写真や名前を集めては公開したり、ネットを通して子どもを実際に呼び出すようなことも起こっている・・・ネット犯罪に取り組む団体によると、今年になってからだけでも30件前後のネット上での小児性愛事件がすでに報告されているそうです。しかも子どものネットへのアクセスは増える一方で、父兄たちはさらに気が気でない状況になっているようです。

(イメージ写真で、内容とは関係ありません)
77%の父兄が自分の子どもがネットサーフィンしていることを知っており、しかも毎日アクセスしている子どもは、15-17歳で65%、6-17歳全体でも31%に達しているそうです。こうした問題に取り組んでいる団体関係者曰くは、問題は親の目の届かないところで、子どもが勝手にさまざまなサイトにアクセスしていることだとか。つまり、親の監督が不十分・・・今でもお尻をぶったり、しつけには厳しそうなフランス社会ですが、それでも忙しい親が多いのかネット利用に関しては自由放任になっている家庭が多いようです。
さらに、好ましくないサイトへのアクセスを制限しようにも、親よりも子供のほうがコンピューターやインターネットに詳しい場合が多く、どうしたものかと悩んでいる父兄も多いとか。確かに、コンピューターやインターネットの普及はフランス、いわゆる先進国としては遅かったですものね。そこで、アクセスを制限できるソフトに頼るわけですが、そのソフトがまた信用できない・・・ソフトのこともよく分からないけれど、でも信用できない、という親が多いそうです。61%の親が、もっと性能の良いものが必要だ! なんとなくフランス人らしいなと思えてきますね。新しいものへの懐疑、あるいは、新しいものを作った側が提示する対策への不信感、特に「有料」への嫌悪感・・・どこの国にも、愛すべき点はありますものね。

(これもイメージ、内容とは関係ありません)
では、解決策はないのでしょうか・・・有害サイトを訴えたり、啓蒙キャンペーンなどを行なっている団体関係者が言うには、親子の対話に勝るものはない。要は、親と子の会話が十分で、親が有害サイトへのアクセスがなぜいけないのかをきちんと説明し、かつ時々はそうしたサイトへアクセスしていないか様子を見てみることが大切だということのようですね。コンピューター・ソフトよりも、親子の対話・触れ合いを。機械というハードよりも、ソフト、親子の関係が希薄にならないようにすることで解決できる! ただし、子どものネットへのアクセスを全面的に禁止するのはよくないとも言っているそうです。どうしてか・・・全面禁止すれば、親の目の全く届かないところでこっそり見るようになり、問題をいっそう見えにくく、解決しにくくするだけだから。
新しい科学技術の誕生は、人間社会に新たな問題をひき起こします。でも、それを解決するのも、人間の叡智。人間の考え付いた技術ですから、人間に解決できないわけはない・・・そう思いたいのですが、さて、どうでしょうか。
↓「励みの一票」をお願いします!
すぐ下の文字をクリックすると、ランキングにアクセスし、投票になります。
人気blogランキングへ
フランスでも、インターネットの影響を心配する父兄が多いようで、その調査結果が22日のフィガロ紙に紹介されていました。
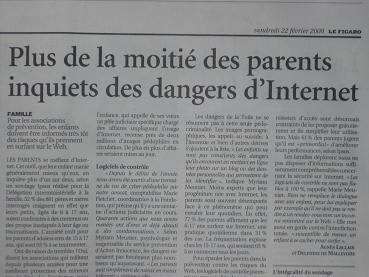
6歳から17歳までの子どもを持つ父兄にアンケートをし、801人から回答を得たそうです。その内65%がネットの好ましくない影響を恐れ、52%は子どもたちが年齢に相応しくないサイトへアクセスしているのではないかと心配しているそうです。ポルノ、小児性愛、自殺、拒食症・・・さまざまな誘惑が待ち構えているネットの世界。フランスのマス・メディアはあまり社会面的出来事を細かく紹介しないので、詳しくは分からないのですが、子どもの写真や名前を集めては公開したり、ネットを通して子どもを実際に呼び出すようなことも起こっている・・・ネット犯罪に取り組む団体によると、今年になってからだけでも30件前後のネット上での小児性愛事件がすでに報告されているそうです。しかも子どものネットへのアクセスは増える一方で、父兄たちはさらに気が気でない状況になっているようです。

(イメージ写真で、内容とは関係ありません)
77%の父兄が自分の子どもがネットサーフィンしていることを知っており、しかも毎日アクセスしている子どもは、15-17歳で65%、6-17歳全体でも31%に達しているそうです。こうした問題に取り組んでいる団体関係者曰くは、問題は親の目の届かないところで、子どもが勝手にさまざまなサイトにアクセスしていることだとか。つまり、親の監督が不十分・・・今でもお尻をぶったり、しつけには厳しそうなフランス社会ですが、それでも忙しい親が多いのかネット利用に関しては自由放任になっている家庭が多いようです。
さらに、好ましくないサイトへのアクセスを制限しようにも、親よりも子供のほうがコンピューターやインターネットに詳しい場合が多く、どうしたものかと悩んでいる父兄も多いとか。確かに、コンピューターやインターネットの普及はフランス、いわゆる先進国としては遅かったですものね。そこで、アクセスを制限できるソフトに頼るわけですが、そのソフトがまた信用できない・・・ソフトのこともよく分からないけれど、でも信用できない、という親が多いそうです。61%の親が、もっと性能の良いものが必要だ! なんとなくフランス人らしいなと思えてきますね。新しいものへの懐疑、あるいは、新しいものを作った側が提示する対策への不信感、特に「有料」への嫌悪感・・・どこの国にも、愛すべき点はありますものね。

(これもイメージ、内容とは関係ありません)
では、解決策はないのでしょうか・・・有害サイトを訴えたり、啓蒙キャンペーンなどを行なっている団体関係者が言うには、親子の対話に勝るものはない。要は、親と子の会話が十分で、親が有害サイトへのアクセスがなぜいけないのかをきちんと説明し、かつ時々はそうしたサイトへアクセスしていないか様子を見てみることが大切だということのようですね。コンピューター・ソフトよりも、親子の対話・触れ合いを。機械というハードよりも、ソフト、親子の関係が希薄にならないようにすることで解決できる! ただし、子どものネットへのアクセスを全面的に禁止するのはよくないとも言っているそうです。どうしてか・・・全面禁止すれば、親の目の全く届かないところでこっそり見るようになり、問題をいっそう見えにくく、解決しにくくするだけだから。
新しい科学技術の誕生は、人間社会に新たな問題をひき起こします。でも、それを解決するのも、人間の叡智。人間の考え付いた技術ですから、人間に解決できないわけはない・・・そう思いたいのですが、さて、どうでしょうか。
↓「励みの一票」をお願いします!
すぐ下の文字をクリックすると、ランキングにアクセスし、投票になります。
人気blogランキングへ






























