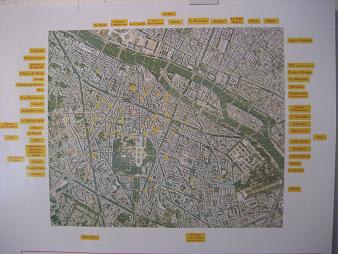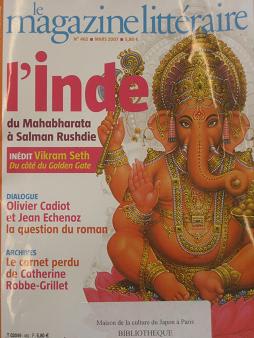13日のパリは、さすが13日の金曜日、よく外れる天気予報が珍しく当たって、快晴、気温も25度を超え、暑い夏の天気になりました。14日の革命記念日も快晴、気温はさらに上がるとか。革命記念日を快晴にするあたり、サルコジ大統領の強運でしょうか。こんな迷信のようなことを考えるのは日本人なればこそで、合理性のフランス人は考えもしないでしょうが・・・
さて、夏。日本の夏といえば、金鳥、というCMが昔ありましたが、広告といえば、夏休み前になると、出版各社が文庫本の広告キャンペーンをやっていたのを思い出します。三四郎の夏、とかいろいろなキャッチフレーズがありました。今でも続いているのでしょうか。夏休みを読書で過ごそう、あるいは、文庫本を友に夏休みの旅行へ、というメッセージだったと思いますが、同じような意図だと思われる文庫本のポスターが、今パリのメトロの駅などに数多く貼り出されています。Folio(ガリマール・フォリオ文庫)が広告主です。まずは、写真をご覧あれ。

(推薦しているのは、“Entre les murs”“Partir”“Neige”という3冊の本です。)

(このポスターでは、“Le Cercle ferme”“Ourania”“Un homme heureux”の3冊が推薦されています。)

(もう1点、このポスターは、“Le reve Botticelli”“Magnus”“Trois jours chez ma mere”を勧めています。3冊目の本は、2005年のゴンクール賞受賞作です。)
これらがフォリオ文庫オススメの、この夏の9冊。読んでみたい方は、夏休み用に、書店に問い合わせてみてはいかがですか。
この広告シリーズが目に付いたのは、そのアイデアが日本のキャンペーンに似ていることと、もう1点、デザインアイデアです。いずれのポスターにも、落書きのようなものがありますね。駅などに貼られている大型ポスターにはよく落書きがされていますので、これらも気の毒に落書きされてしまったのだろうと思っていたのですが、どこで見ても同じ書き込み! よく見ると、印刷されています。3点シリーズ、それぞれ紹介している3冊の本の特徴をしっかりデザイン化しています。しかも、キャッチフレーズもシリーズ化しつつ、単語一つを変えることによって、それぞれの特徴を端的に表現しています。
最初の、探偵物のような作品には、クルマの上にパトカーがつけるランプを描き込んで、「フォリオ文庫ほど、あなたに警戒心を抱かせるものはない」。2番目が、冒険心あふれる作品でしょうか、船の絵とともに「フォリオ文庫ほど、あなたを運び去るものはない」。3点目は、誰かの過去が明らかになるような作品かもしれないですね、思い出の階段を登っていくような描き込みで、「フォリオ文庫ほど、あなたに暴露するものはない」。そして、3点共通のスローガンが、「フォリオ文庫で、あなたは想像の翼を遠くへと広げるだろう」。
夏休み・・・家で、旅先で、あるいは旅の途上で、1冊の本とともに、想像の翼を大きく広げてみましょうか。でも、悲しいかな、原書ではまだ、広げるのが辞書になってしまうのが、残念です。
↓アクセスランキングへ「励みの一票」をお願いします!
人気blogランキングへ
さて、夏。日本の夏といえば、金鳥、というCMが昔ありましたが、広告といえば、夏休み前になると、出版各社が文庫本の広告キャンペーンをやっていたのを思い出します。三四郎の夏、とかいろいろなキャッチフレーズがありました。今でも続いているのでしょうか。夏休みを読書で過ごそう、あるいは、文庫本を友に夏休みの旅行へ、というメッセージだったと思いますが、同じような意図だと思われる文庫本のポスターが、今パリのメトロの駅などに数多く貼り出されています。Folio(ガリマール・フォリオ文庫)が広告主です。まずは、写真をご覧あれ。

(推薦しているのは、“Entre les murs”“Partir”“Neige”という3冊の本です。)

(このポスターでは、“Le Cercle ferme”“Ourania”“Un homme heureux”の3冊が推薦されています。)

(もう1点、このポスターは、“Le reve Botticelli”“Magnus”“Trois jours chez ma mere”を勧めています。3冊目の本は、2005年のゴンクール賞受賞作です。)
これらがフォリオ文庫オススメの、この夏の9冊。読んでみたい方は、夏休み用に、書店に問い合わせてみてはいかがですか。
この広告シリーズが目に付いたのは、そのアイデアが日本のキャンペーンに似ていることと、もう1点、デザインアイデアです。いずれのポスターにも、落書きのようなものがありますね。駅などに貼られている大型ポスターにはよく落書きがされていますので、これらも気の毒に落書きされてしまったのだろうと思っていたのですが、どこで見ても同じ書き込み! よく見ると、印刷されています。3点シリーズ、それぞれ紹介している3冊の本の特徴をしっかりデザイン化しています。しかも、キャッチフレーズもシリーズ化しつつ、単語一つを変えることによって、それぞれの特徴を端的に表現しています。
最初の、探偵物のような作品には、クルマの上にパトカーがつけるランプを描き込んで、「フォリオ文庫ほど、あなたに警戒心を抱かせるものはない」。2番目が、冒険心あふれる作品でしょうか、船の絵とともに「フォリオ文庫ほど、あなたを運び去るものはない」。3点目は、誰かの過去が明らかになるような作品かもしれないですね、思い出の階段を登っていくような描き込みで、「フォリオ文庫ほど、あなたに暴露するものはない」。そして、3点共通のスローガンが、「フォリオ文庫で、あなたは想像の翼を遠くへと広げるだろう」。
夏休み・・・家で、旅先で、あるいは旅の途上で、1冊の本とともに、想像の翼を大きく広げてみましょうか。でも、悲しいかな、原書ではまだ、広げるのが辞書になってしまうのが、残念です。
↓アクセスランキングへ「励みの一票」をお願いします!
人気blogランキングへ