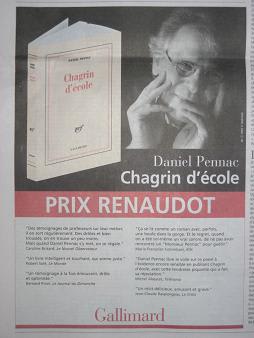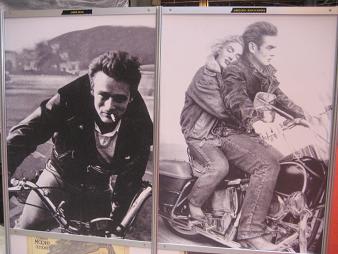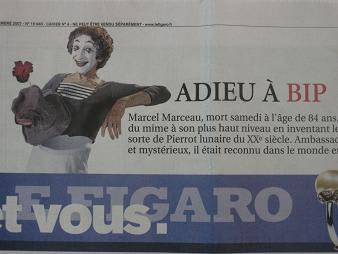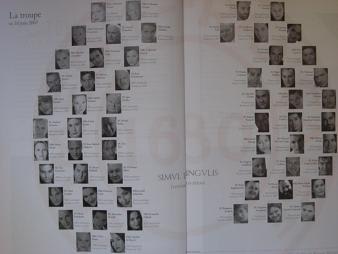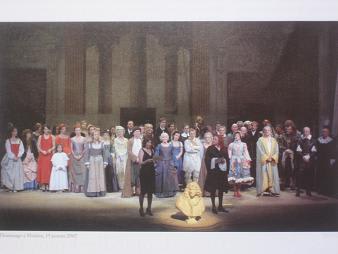“More”(『モア』)などで有名な映画監督、Barbet Schroeder(バーベット・シュローダー:フランス語読みでなきゃ嫌だという方用にはバルベ・シュレデール)が昨年後半、日本で新作の撮影を行なっていたそうですが、日本では報道されていたでしょうか。

2日付のル・モンド紙です。一面を使って、66歳にして日本で撮影を敢行! という挑戦の模様を伝えています。
バーベット・シュローダー・・・1941年にイランのテヘランで生まれる。フランス国籍のスイス人。父親はコロンビア人。教育はパリで受け、名門・アンリ四世高校からソルボンヌへ。哲学を専攻し、その後『カイエ・デュ・シネマ』に参加。批評からスタートし、制作、監督、出演と映画全般に関わる。
そのシュローダー監督がメガフォンを取り日本で撮影した作品は、『陰獣』。江戸川乱歩の原作で、すでに1977年に加藤泰監督の手により映画化され、カルト映画の傑作と言われています。個人的には、加藤泰監督の作品では『車夫遊侠伝 喧嘩辰』が記憶に残っています。それも、作品云々より、桜町弘子と藤純子がきれいだったという、至ってミーハーな印象によるものですが・・・関係なかったですね。
さて、何がシュローダー監督の挑戦なのかというと、日本で撮影すると言うことそのこと自体! 日本へ発つ前にシュローダー監督は、映画人仲間のシェリー・ランシングなどと食事を共にしたそうです。ランシングといえば、松田勇作の劇場公開映画としては遺作となった『ブラック・レイン』の制作担当者。彼女曰くは、『ブラック・レイン』の撮影は、日本で行なわれていましたが、文化、風土、システム・・・さまざまな相違から、日米スタッフが共に苛立ち、とうとう日本を撤退しアメリカなどで撮影を続けたと言う、パラマウント映画最悪の経験と言われているそうです。そうした経験などを直接聞いたシュローダー監督なのですが、それでも敢えて日本ロケを敢行。しかも、予定通り一日も遅れず12月16日に終了し、公開日も今年9月24日と早くも決定しているそうです。
では、シュローダー監督は実際にどんな苦労に遭遇したのでしょうか。
まずは、日本人の細部へのこだわり。どんな些細なことでも、現実と異なることには妥協しない日本スタッフ。いかに全てが真実らしく見えるか・・・特に外国人の思い描く日本的イメージには、間違いがあれば正さないと気がすまない。例えば、芸者役をパリに5年住みモデルもしている日本人女性が演じたそうですが、日本人ぽくないという意見が日本サイドから出たり、サドマゾ的シーンもあるそうなのですが、真実らしくするために、その道の専門家にコンサルタントとして立ち会ってもらったり・・・日本では、細部の積み上げで捉えることが多いですよね。細部までよく描けている小説、細部まで寸分のミスもない文章、細部まで時代考証の行き届いた映画・・・しかし、テーマ、主張となると、あまり論じられなかったりします。正確な細部を積み上げていって、言いたい事は忖度する。これが日本式かもしれないですね。観念、思想を大切にする欧米流に対し、現場の細部積み上げ式の日本。その影響か、先日もアメリカ人ジャーナリストが、日本の生産現場は世界一だが、経営はひどい、と言っていたそうですが、その傾向は認めざるをえないかもしれませんね。経営理念、経営思想を語れる経営者は少ないような気がします。現場で優秀な社員が経営者になる。だから、「後は、任せた」と現場丸投げの管理職が多いですよね。一方の欧米には、哲学、理念を語る経営者が多く、そのことが経営者の資格でもあるようです。その一方で、時間から時間までただ職場にいれば良いという現場。ボトム・アップの日本と、トップ・ダウンの欧米・・・
時間厳守・・・ホテルを早朝借り切って撮影したそうですが、絶対に時間オーバーをしてはいけない。以前ソフィア・コッポラ監督が東京で撮影した際、朝の7時半までに撤収しなければいけないところ、30分遅くなったことがあるそうですが、そのホテルはそれ以降一切の撮影を受け入れていないそうです。どんなことがあっても絶対に遅刻をしない日本人、というのは『世界の日本人ジョーク集』にも良く出てきます。時間に几帳面(過ぎる)日本人というのは、定説になっているのでしょうね。
周囲への配慮・・・屋外ロケの際、欧米では、撮影の邪魔にならないよう歩行者に遠回りしてもらったりするそうですが、日本では、歩行者のために撮影を中断し、迷惑を詫びながらその舗道を通ってもらう。また、屋外ロケを許可しない街もあり、そのひとつが京都。『陰獣』の舞台はその京都なのですが、許可が下りず、東京に屋外セットを組み、ロケを行なったそうです。一方、欧米では・・・例えば、パリでは、いたるところで屋外ロケが行なわれています。日本では、映画という文化よりも、市民の日常生活優先なのかもしれないですね。あるいは、映画が文化としての市民権を得ていない、たんなる娯楽なのでしょうか・・・
スタッフの熱意と待遇・・・撮影は旧知のイタリア人Luciano Tovoli(ルチアーノ・トヴォリ)で、最初英語のできるスタッフを要求したそうですが、撮影や照明などのスタッフで英語ができる人は見つからない(日本の英語教育・・・)。そこで、通訳を介しながら、英語・フランス語・日本語が飛び交う環境での作業となったものの、数週間もすると日本の若いスタッフの熱意が実って、いちいち指示しなくても、撮影監督の意図をある程度汲めるようになった。しかし、この可能性を秘めたスタッフの待遇たるや・・・日本の大手映画会社はスタッフに残業代を払わず、年金などの福利厚生も全くない。将来への不安から、せっかくキャリアを積んでもみな辞めていく。でも、会社にとっては、そのほうがありがたい。ベテランは給与が高くなるから、安い若手に切り替えたい! ・・・これで映画産業の伝統は保たれるのでしょうか・・・
融通性・・・日本では一端決まったものを変更するのが大変。絵コンテが決まると、一部たりとも変更させない。実際にカメラの前に立つと新しいアイディアだって沸いてくる。それでも、その変更を日本人スタッフに納得させるには、なぜ、どうしてを事細かに説明しないと聞き入れてくれない。オーソライズされたことに対しては、頑固で、融通性が全くない・・・確かに表面はそうでしょうけれど、そこのところを何とかお願いしますよ、ということがまかり通るのがアジアの日本。正論で理解してもらおうとするよりも、相手の目をじっと見て困った顔で、お願いしますよ、後生ですから、のほうが有効かもしれないですね。
他にも日本ならではの特徴に、行く手を妨げられたことも度々あったようですが、シュローダー監督は、最終的に、スケジュールどおりに完成させてしまった。どこが『ブラック・レイン』との違いなのでしょう。
シュローダー監督は次のように言っています・・・「監督の才能などは20年もすれば枯渇してしまう。それを避ける方法は、ルイス・ブニュエルやヒッチコックのように撮影する国、舞台になる国などを、固定せず移動することだ」。確かに、シュローダー監督は今までにニューギニアやコロンビアで制作した経験も持っています。そして、今回は日本。未知なるものとの出会いが、新たなる創造性やアイディアの泉になる・・・このことは、映画監督だけに限らないかもしれないですね。
そうした未知なるものとの出会いから、シュローダー監督は異なる文化との対応の仕方を学んでいるのでしょう。撮影の途中からは、こうした場合日本はどう言ってくるか予想できるようになり、先回りして対応を考えることができるようになったそうです。一方の『ブラック・レイン』は・・・世界にアメリカの価値観・システムを広げることが正義である! の一翼を担ってしまったのかもしれないですね。ひたすら日本のやり方を否定し、アメリカ・スタイルで押し通す。その結果の、破綻。
国を跨ぐことによって起きる軋轢とその相克。フランス人監督とイタリア人撮影監督の日本での数ヶ月の撮影というひとつの事をとっても、考えさせられることがたくさんあります。ただ、もちろん、国によるさまざまな違いは、あくまで違いであって、優劣があるわけではないのは、言うまでもないですね。
↓「励みの一票」をお願いします!
すぐ下の文字をクリックすると、ランキングにアクセスし、投票になります。
人気blogランキングへ

2日付のル・モンド紙です。一面を使って、66歳にして日本で撮影を敢行! という挑戦の模様を伝えています。
バーベット・シュローダー・・・1941年にイランのテヘランで生まれる。フランス国籍のスイス人。父親はコロンビア人。教育はパリで受け、名門・アンリ四世高校からソルボンヌへ。哲学を専攻し、その後『カイエ・デュ・シネマ』に参加。批評からスタートし、制作、監督、出演と映画全般に関わる。
そのシュローダー監督がメガフォンを取り日本で撮影した作品は、『陰獣』。江戸川乱歩の原作で、すでに1977年に加藤泰監督の手により映画化され、カルト映画の傑作と言われています。個人的には、加藤泰監督の作品では『車夫遊侠伝 喧嘩辰』が記憶に残っています。それも、作品云々より、桜町弘子と藤純子がきれいだったという、至ってミーハーな印象によるものですが・・・関係なかったですね。
さて、何がシュローダー監督の挑戦なのかというと、日本で撮影すると言うことそのこと自体! 日本へ発つ前にシュローダー監督は、映画人仲間のシェリー・ランシングなどと食事を共にしたそうです。ランシングといえば、松田勇作の劇場公開映画としては遺作となった『ブラック・レイン』の制作担当者。彼女曰くは、『ブラック・レイン』の撮影は、日本で行なわれていましたが、文化、風土、システム・・・さまざまな相違から、日米スタッフが共に苛立ち、とうとう日本を撤退しアメリカなどで撮影を続けたと言う、パラマウント映画最悪の経験と言われているそうです。そうした経験などを直接聞いたシュローダー監督なのですが、それでも敢えて日本ロケを敢行。しかも、予定通り一日も遅れず12月16日に終了し、公開日も今年9月24日と早くも決定しているそうです。
では、シュローダー監督は実際にどんな苦労に遭遇したのでしょうか。
まずは、日本人の細部へのこだわり。どんな些細なことでも、現実と異なることには妥協しない日本スタッフ。いかに全てが真実らしく見えるか・・・特に外国人の思い描く日本的イメージには、間違いがあれば正さないと気がすまない。例えば、芸者役をパリに5年住みモデルもしている日本人女性が演じたそうですが、日本人ぽくないという意見が日本サイドから出たり、サドマゾ的シーンもあるそうなのですが、真実らしくするために、その道の専門家にコンサルタントとして立ち会ってもらったり・・・日本では、細部の積み上げで捉えることが多いですよね。細部までよく描けている小説、細部まで寸分のミスもない文章、細部まで時代考証の行き届いた映画・・・しかし、テーマ、主張となると、あまり論じられなかったりします。正確な細部を積み上げていって、言いたい事は忖度する。これが日本式かもしれないですね。観念、思想を大切にする欧米流に対し、現場の細部積み上げ式の日本。その影響か、先日もアメリカ人ジャーナリストが、日本の生産現場は世界一だが、経営はひどい、と言っていたそうですが、その傾向は認めざるをえないかもしれませんね。経営理念、経営思想を語れる経営者は少ないような気がします。現場で優秀な社員が経営者になる。だから、「後は、任せた」と現場丸投げの管理職が多いですよね。一方の欧米には、哲学、理念を語る経営者が多く、そのことが経営者の資格でもあるようです。その一方で、時間から時間までただ職場にいれば良いという現場。ボトム・アップの日本と、トップ・ダウンの欧米・・・
時間厳守・・・ホテルを早朝借り切って撮影したそうですが、絶対に時間オーバーをしてはいけない。以前ソフィア・コッポラ監督が東京で撮影した際、朝の7時半までに撤収しなければいけないところ、30分遅くなったことがあるそうですが、そのホテルはそれ以降一切の撮影を受け入れていないそうです。どんなことがあっても絶対に遅刻をしない日本人、というのは『世界の日本人ジョーク集』にも良く出てきます。時間に几帳面(過ぎる)日本人というのは、定説になっているのでしょうね。
周囲への配慮・・・屋外ロケの際、欧米では、撮影の邪魔にならないよう歩行者に遠回りしてもらったりするそうですが、日本では、歩行者のために撮影を中断し、迷惑を詫びながらその舗道を通ってもらう。また、屋外ロケを許可しない街もあり、そのひとつが京都。『陰獣』の舞台はその京都なのですが、許可が下りず、東京に屋外セットを組み、ロケを行なったそうです。一方、欧米では・・・例えば、パリでは、いたるところで屋外ロケが行なわれています。日本では、映画という文化よりも、市民の日常生活優先なのかもしれないですね。あるいは、映画が文化としての市民権を得ていない、たんなる娯楽なのでしょうか・・・
スタッフの熱意と待遇・・・撮影は旧知のイタリア人Luciano Tovoli(ルチアーノ・トヴォリ)で、最初英語のできるスタッフを要求したそうですが、撮影や照明などのスタッフで英語ができる人は見つからない(日本の英語教育・・・)。そこで、通訳を介しながら、英語・フランス語・日本語が飛び交う環境での作業となったものの、数週間もすると日本の若いスタッフの熱意が実って、いちいち指示しなくても、撮影監督の意図をある程度汲めるようになった。しかし、この可能性を秘めたスタッフの待遇たるや・・・日本の大手映画会社はスタッフに残業代を払わず、年金などの福利厚生も全くない。将来への不安から、せっかくキャリアを積んでもみな辞めていく。でも、会社にとっては、そのほうがありがたい。ベテランは給与が高くなるから、安い若手に切り替えたい! ・・・これで映画産業の伝統は保たれるのでしょうか・・・
融通性・・・日本では一端決まったものを変更するのが大変。絵コンテが決まると、一部たりとも変更させない。実際にカメラの前に立つと新しいアイディアだって沸いてくる。それでも、その変更を日本人スタッフに納得させるには、なぜ、どうしてを事細かに説明しないと聞き入れてくれない。オーソライズされたことに対しては、頑固で、融通性が全くない・・・確かに表面はそうでしょうけれど、そこのところを何とかお願いしますよ、ということがまかり通るのがアジアの日本。正論で理解してもらおうとするよりも、相手の目をじっと見て困った顔で、お願いしますよ、後生ですから、のほうが有効かもしれないですね。
他にも日本ならではの特徴に、行く手を妨げられたことも度々あったようですが、シュローダー監督は、最終的に、スケジュールどおりに完成させてしまった。どこが『ブラック・レイン』との違いなのでしょう。
シュローダー監督は次のように言っています・・・「監督の才能などは20年もすれば枯渇してしまう。それを避ける方法は、ルイス・ブニュエルやヒッチコックのように撮影する国、舞台になる国などを、固定せず移動することだ」。確かに、シュローダー監督は今までにニューギニアやコロンビアで制作した経験も持っています。そして、今回は日本。未知なるものとの出会いが、新たなる創造性やアイディアの泉になる・・・このことは、映画監督だけに限らないかもしれないですね。
そうした未知なるものとの出会いから、シュローダー監督は異なる文化との対応の仕方を学んでいるのでしょう。撮影の途中からは、こうした場合日本はどう言ってくるか予想できるようになり、先回りして対応を考えることができるようになったそうです。一方の『ブラック・レイン』は・・・世界にアメリカの価値観・システムを広げることが正義である! の一翼を担ってしまったのかもしれないですね。ひたすら日本のやり方を否定し、アメリカ・スタイルで押し通す。その結果の、破綻。
国を跨ぐことによって起きる軋轢とその相克。フランス人監督とイタリア人撮影監督の日本での数ヶ月の撮影というひとつの事をとっても、考えさせられることがたくさんあります。ただ、もちろん、国によるさまざまな違いは、あくまで違いであって、優劣があるわけではないのは、言うまでもないですね。
↓「励みの一票」をお願いします!
すぐ下の文字をクリックすると、ランキングにアクセスし、投票になります。
人気blogランキングへ