 創価学会二世の結婚問題3
創価学会二世の結婚問題3 「宗教教育」の影響は簡単には消えない
「宗教教育」の影響は簡単には消えない☆創価学会は、脱会にかんし、現在では認める方向に変化しているとも聞く
*学会活動をしない会員は、「未活」と呼ばれ、未活は脱会者ではない
☆自分(末活)はもう創価学会はやめたと考えている
*受けた影響は簡単に消滅しせず、そこが信仰の難しいところでもある
*「三つ子の魂百まで」ということわざもある
☆子どもが重大な病気にかかる
*思わず、「南無妙法蓮華経」と唱題をしているかもしれない
☆長い期間宗教教育を受けなければ、信仰はその人間のものにはならない
*その対策として、創価学会が、未来部という組織を作る
*未来部には、大人の会員による教育部という組織もある
 結婚すると、冠婚葬祭をめぐってもめ事が起こりやすい
結婚すると、冠婚葬祭をめぐってもめ事が起こりやすい☆「親が創価学会」の人間が結婚した後の問題
*熱心な家庭で育った人間は、学会活動をすべてに優先する
*さほど熱心には活動してこなかった家庭で育てば、仕事を優先する
☆子どもが生まれたときに、問題が起こりやすい
*「初参り」夫婦と赤ん坊だけではなく、赤ん坊の祖父母も加わる
*初参りの際に、多くの場合、神社に行く
*創価学会の会員は、神社に行くことを好まない
☆現在の日本の葬式
*仏教式でという感覚は依然として強い
*葬式には導師として、その家の宗派の僧侶を呼び、読経してもらう
*一周忌や三回忌といった「年忌法要」、「法事」の場合も同じ
*創価学会の会員、自分たちの信仰とは合わな他の宗派の葬式や法事
(参列することを好まない)
 冠婚葬祭をどうするのか
冠婚葬祭をどうするのか☆冠婚葬祭をめぐる争い事は、夫婦二人だけなら、なんとかなるかもしれない
*お互いの両親、あるいは兄弟や親戚がかかわってくると厄介なものになる
☆創価学会の葬式は現在、「友人葬」と呼ばれる独自の方法でおこなう
*創価学会の友人葬では、僧侶は葬式には呼ばない
*「儀典長」と呼ばれる会員が来る
*会場に「南無妙法蓮華経」などと記された本尊を掲げ、その前で勤行をおこなう
*参列者も、会員であれば、勤行に加わる
*葬式に、会員以外の人間が参列すると戸惑うこともある
☆創価学会では、仏典に根拠を持たない戒名は不要であるとの考え
☆創価学会は、僧侶を呼ばず、戒名を授からない形の新しい葬式のやり方
☆友人葬の導入は、創価学会にとって極めて重要な意味を持った
*現在では、友人葬を扱う一般の葬儀社も増えている
*友人葬で葬ってもらうことを依頼する一般の人間もいる
☆友人葬が同志葬としてはじまった時代
*一般の参列者に違和感を持たれることが多かった
☆今では、葬式のことでトラブルが生まれることは少なくなっている
 墓守りの意識
墓守りの意識☆創価学会の場合、もともと先祖を供養することには関心が薄い
*地方出身者で、都市の家には先祖にあたる存在がいなかったことが影響している
☆日蓮系の新宗教、霊友会や立正佼成会
*祖供養の重要性を強調していた
*それに必要性を感じる人間は、そうした教団を選んだ
☆創価学会の会員、墓を守り続けていくという意識はあまり強くない
*葬式や墓については、 一般の人間以上に関心は薄いと言えるのでは
 知識・意欲の向上目指し、記事を参考・引用し、自分のノートとしてブログに記載
知識・意欲の向上目指し、記事を参考・引用し、自分のノートとしてブログに記載 出典内容の知識共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介しました
出典内容の知識共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介しました☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
 私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います 詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください
詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください 出典、『親が創価学会』
出典、『親が創価学会』
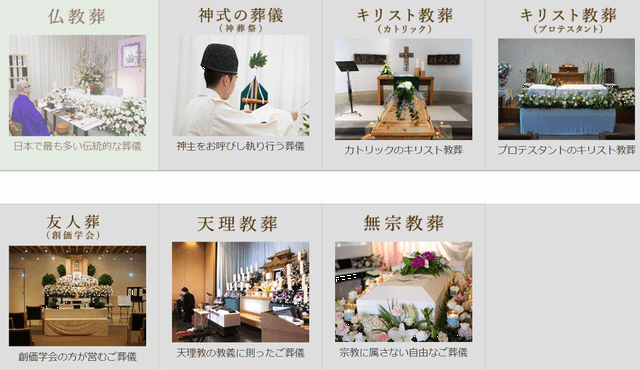


未活、友人葬、墓(花葬儀HP、ネットより画像引用)


















 Have you finished your lunch ?(食べ終わったか?)
Have you finished your lunch ?(食べ終わったか?) 復習
復習





