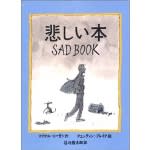犬飼いがお薦めする、ネコの絵本ですが、
これはもー、誰もがご存知、敢えてご紹介も何もないもんですがね。
でも、ご紹介しましょうかね。
実は、毎日うちのルッくんが逢わないと気が済まないネコちゃんがおりましてね、
彼女は推定20歳のおばあちゃんなんですが、三毛の長毛です。
お顔は…どちらかというとぺちゃんこで、可愛いという言葉は似合わないかもしれません。
まあお年を重ねていることもありますし。
彼女は、大きなお屋敷の庭に棲みついていた由緒正しい野良さんです。
去年このお屋敷が取り壊されてしまい、駐車場になってしまいました。
今は、ねぐらは右隣のお宅の庭で、ご飯は左隣のお宅でいただいています。
左隣のお宅は、お屋敷のご親戚で、ネコちゃんとも20年来の知り合いなので、
おうちに入れようとするのですが、
長い野良暮らしは気が楽なのか、外に行ってしまうのだそうです。
そこのオタクの奥様が、夕方「ミーちゃん、ミーちゃん」と呼ぶと、やってきます。
ルッくんはミーちゃん、いやミーおばあちゃんにとても興味があるらしくて、
ねぐらのオタクを必ずのぞきます。
日向ぼっこをしているミーちゃんに逢った日は満足して帰ります。
ミーちゃんも、母が声をかけると、ミャ、ミャとお返事してくれます。
時には、ボールをくわえて興奮するルッくんを横目で見ながら、
いっしょに歩いてくれたりもします。
あら?これがなんで「100万回生きたねこ」のナビなのかしら?
まあ、こじつければ絵本の主人公のネコ(こちらは彼ですが)に
ミーちゃんが少々似ていることでしょうか。
天真爛漫で喜怒哀楽がすぐわかるワンに比べて、
何を考えているのかじっとうずくまるミーちゃんを見ていると、
ネコは奥が深いのう…と思う母でございます。
まあ、イヌが浅いというわけでもありませんが。( ̄▽ ̄)
へへッ僕は天真爛漫!! なに?奥が浅い?いやー、そうですかねぇ。 (ルック)