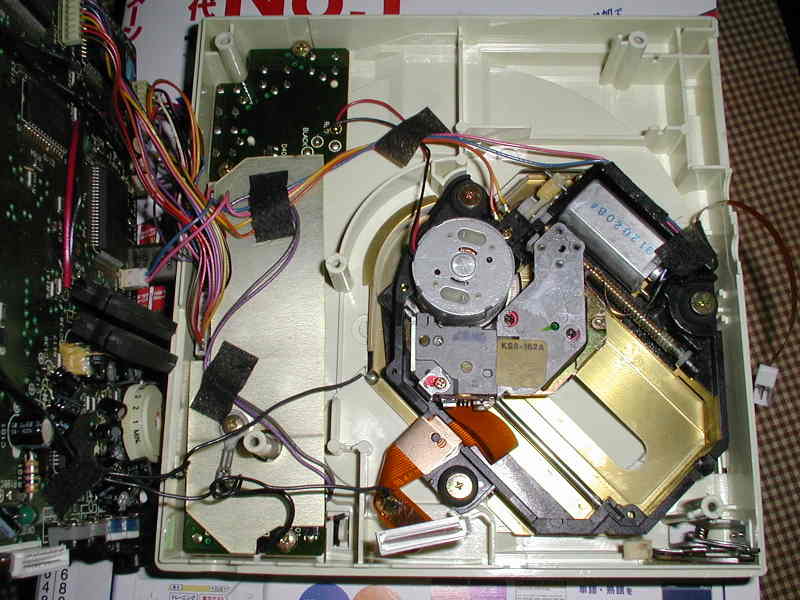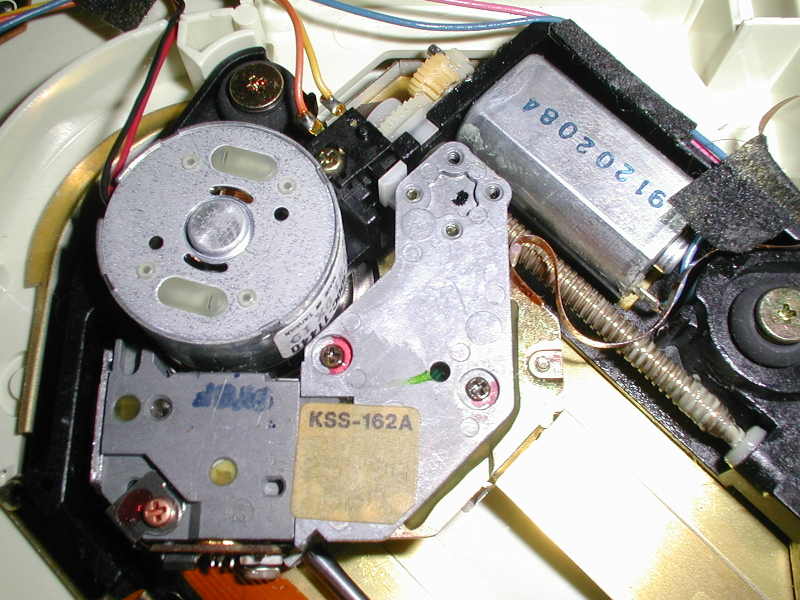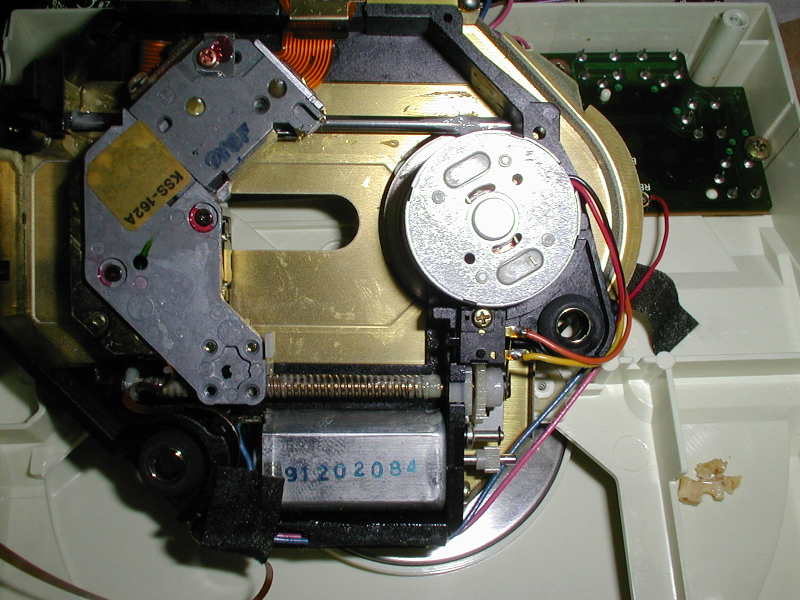ふと、CPS2/3の電池切れが気になったので、久々に起動チェックを行ってみる。かなりしばらくぶりになるので、何だか立ち上げるのが嫌だなぁ。(汗)
…とりあえず、両システムとも無事に起動を確認。「虹色町の奇跡」だけは昔からコネクタ接触不良ぎみなので、なかなか起動せずに一色画面を見せてくれるのでいつもハラハラする。(^-^; 電池切れと判断したヴァンパイアハンター(1枚目)も念のため確認したけど、何度差し直しても画面が一色のまま。やっぱり死んでるよなぁ。2枚目を大事にするか。
今のところCPS2の相場はあまり変わってないけど、タイトルによっては高めになってるのもあるだろうか。逆にCPS3は最近価格が上がってる感じなので、ジョジョはDC版あるけどちょっと注意しないと… 何か当時の購入価格から1.5~2倍ぐらいになってるし。唯一スト3だけはROM入手なので、今回は交換してまで確認してないのだけど大丈夫だろうか。500円で買ったやつだからそれほど困るわけではないのだけど。
などと試しプレイをしていると、ジョイスティックのレバー左が突然反応しなくなる。コネクタを差し直しても改善されないので、ネジをゆるめてカバーを取ってみると、ケーブルからスティック左のスイッチにハンダ付けしてた配線が、途中でレバー軸に引っかかって擦れて切断されたらしい。
基板用に改造したSFCファイティングスティックを作ったのは10年以上も前の事。当時は行き当たりばったりな改造で作ったので、中の配線の余裕が殆ど無く張りつめていて、何時切れてもおかしくなかったり、どういう経路で配線したのかサッパリ判らない状態。(汗)
せっかくの機会なので、今回の修理ついでに中の配線を奇麗に繋ぎ直してメンテナンスしやすいようにしてみる事に。以前に自作ローリングスイッチにレバー軸のバネを部品取りした同じSFCファイティングスティックもちょうど余ってるし、それらの部品も再利用して連射SW辺りも改善してみた。
レバーやボタン、連射SW基板からの配線は、SFC用基板に付いてたコネクタとケーブルを再利用して別途用意した中間基板に移植。これだけでもかなり配線が以前よりかなりスッキリと配線できたかと。写真では裸の中間基板は、最後にカバーを閉める前にエアキャップで梱包して絶縁済み。
ボタンだけはそのまま元のHORIボタンを使用してるけど、現状では特に使い心地に問題はなし。ただしファストン端子での接続が使えないので、配線は直接ハンダ付け。
レバーは8-4方向切替ガイドを取っ払ったコンボAV付属のサンワ製。こちらはファストン端子で取り外し可能。元のHORIレバーは改造に用いたものと部品取りに使ってたものでロットが違うのか、レバー土台の色も違うし斜め方向の入りがしっかり入るように改善されてる、みたいに感じるような気も。
連射SWの基板は共通GNDを通常とシンクロ連射用に分けるため、6ボタン個別とスタート・セレクトでパターンカットして配線。連射SW部分の基板だけは比較用に手直し前のも撮影してみた。作業前の内部写真はあまりに拙くて恥ずかしい配線状態のため撮らなかったけど、もうちょっとマシな配線が出来なかったもんだろうかと、つくづく自分で思ってしまった。(汗)
元のスローSW(スタートボタン連射によるポーズ)は、未使用・コイント・スタートの3段階に振り分けて、ボタン1と共用で連射できるように配線。基板でコイン・スタートのシンクロ連射なんてもちろん意味は無いのだけど、後ほど某コンシューマ機に繋げた時に使う予定。
自作コントロールボックスとの接続にはD-SUB15Pを使用して、独自の自分配列規格で接続。今思えばNEO-GEOスティック配列の方がよかったかなとも思ったけど、NEO-GEO用スティックコネクタも持ってないから、まぁいいや。以下、自分メモ用の配線内容。
- ボタン1
- ボタン2
- ボタン3
- ボタン4
- ボタン5
- ボタン6
- コイン
- スタート
- 未使用
- GND(シンクロ連射基板へ)
- GND(通常)
- 上
- 下
- 左
- 右
今回改めてこのファイティングスティックを再確認したけど、今の筐体用コンパネや家庭用のRAP・ファイティングスティック等と比べたらレバーとボタン間は離れてるし、レバーがボタンより下がり気味だから、初めて使う人には違和感を感じるかも。それでもSFC版スト2が大ブームの当時、パッドを使うよりキャラ操作が全然違ったんだよなぁ。
とりあえずこのスティックを10年以上使ってる自分には何の問題も無いので、これからも出来るだけ末永く使っていきたいと思ってみたり。