
熊本市民病院の橋本洋一郎先生は脳卒中の世界では知らない人がいないほど有名な方です。
先日の阪神脳卒中セミナーは私達が企画したものですが、先生のご講演ということで多くの参加者をお迎えすることができました。
一般講演は熊本大学神経内科出身で、橋本先生のお弟子さんである当科の進藤先生に「ステントリトリーバーの初期成績」を発表してもらいました。
その後、橋本先生には「心原性脳塞栓症の治療・予防戦略」と題するご講演を頂きました。いつもながら先生のご講演はとても面白く、しかも実地医療で患者さんに役立つ情報が満載で、引き込まれてしまいました。ご講演を拝聴すると、先生ご自身が患者さんを直接診療されているご様子が伝わってきます。素晴らしい内容に感激しました。
橋本先生は地域完結型の脳卒中診療システムを構築されたことで有名です。
この連携システムは、脳卒中で倒れた時、その地域のどこの病院も断らないで引き受け、その後もリハビリテーションや在宅医療まで一貫して質の高い医療を提供するシステムとのことで、「熊本方式」と呼ばれています。
この素晴らしいシステムが実際に運用されている熊本では脳卒中医からの電話一本で迅速にリハビリ病院への転院が実現するそうですので、私たちを含め全国の脳卒中医はうらやましい限りです。
しかし実はこのシステムの構築には大変なご苦労があったとのことです。会の後は遅くまでそのようなお話を詳しくお聞きすることが出来ました。
阪神地区でも熊本のような理想的なシステムを構築出来るよう頑張っていきたいと思います。橋本先生、本会の関係者の皆様に心から御礼申し上げます。
先日の阪神脳卒中セミナーは私達が企画したものですが、先生のご講演ということで多くの参加者をお迎えすることができました。
一般講演は熊本大学神経内科出身で、橋本先生のお弟子さんである当科の進藤先生に「ステントリトリーバーの初期成績」を発表してもらいました。
その後、橋本先生には「心原性脳塞栓症の治療・予防戦略」と題するご講演を頂きました。いつもながら先生のご講演はとても面白く、しかも実地医療で患者さんに役立つ情報が満載で、引き込まれてしまいました。ご講演を拝聴すると、先生ご自身が患者さんを直接診療されているご様子が伝わってきます。素晴らしい内容に感激しました。
橋本先生は地域完結型の脳卒中診療システムを構築されたことで有名です。
この連携システムは、脳卒中で倒れた時、その地域のどこの病院も断らないで引き受け、その後もリハビリテーションや在宅医療まで一貫して質の高い医療を提供するシステムとのことで、「熊本方式」と呼ばれています。
この素晴らしいシステムが実際に運用されている熊本では脳卒中医からの電話一本で迅速にリハビリ病院への転院が実現するそうですので、私たちを含め全国の脳卒中医はうらやましい限りです。
しかし実はこのシステムの構築には大変なご苦労があったとのことです。会の後は遅くまでそのようなお話を詳しくお聞きすることが出来ました。
阪神地区でも熊本のような理想的なシステムを構築出来るよう頑張っていきたいと思います。橋本先生、本会の関係者の皆様に心から御礼申し上げます。











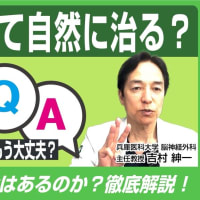
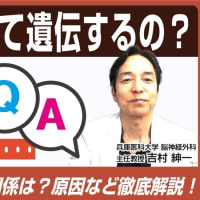





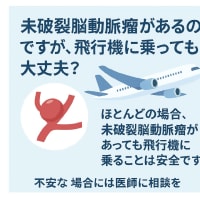






「脳卒中をやっつける!」ための最新治療や諸課題について、
有益な情報を数多くいただけるとともに、素晴らしい先生方をご紹介いただけるのが、
吉村先生のブログの魅力ではないでしょうか。
今回ご紹介いただいた熊本市民病院の橋本洋一郎先生は、
「地域完結型の脳卒中診療システム」を構築なさった、ご著名な脳神経内科医で
いらっしゃるとのこと。
「熊本方式」は、
「脳卒中で倒れた時、その地域のどこの病院も断らないで引き受け、その後も
リハビリテーションや在宅医療まで一貫して質の高い医療を提供するシステム」で、
「脳卒中医からの電話一本で迅速にリハビリ病院への転院が実現するそうですので、
私たちを含め全国の脳卒中医はうらやましい限りです。」
との「熊本方式」は、大勢の患者さんご自身とご家族の皆さんにとっても、
たいへん心強いシステムですよね。
脳卒中で倒れてしまったら、まずは一刻も早く治療を受け、病状の安定後は早期に
リハビリが開始できる――救命から快復までのプロセスにおいて、それぞれの病院で
「質の高い」治療に専念できるということは、患者と家族にとって、本当にどんなに
心強いことでしょう。
・・・そのありがたさが、しみじみと実感されます。
*
「しかし、実はこのシステムの構築には大変なご苦労があったとのことです。」
吉村先生がご紹介くださっている「ドリップ・シップ(点滴と搬送)連携システム」
でも、病院間の連携において多々困難が伴うことをうかがっておりましたので、
役割の異なる病院・施設間での調整・連携がどんなに大変であるか・・・
素人ながら推測させていただいている次第です。
橋本洋一郎先生の筆舌に尽しがたいお骨折りがうかがえる
「総合メディカルマネジメント」(ラジオNIKKEI) 2008年5月8日放送
「地域連携システムの作り方 その2 脳卒中を例に」という記事を見つけました。
九州大学の信友浩一先生によるインタビューに応えての橋本先生のお言葉――
「救急部、集中治療部、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、循環器
内科などの多くの科を持ち、多数の脳卒中患者さんを24時間いつでも受け入れて、
かつ高度先進医療を提供できる急性期脳卒中治療所が少ないという現状が15年前
でした。そういうなかで私たちは神経内科医として、頭痛・めまい・しびれの
外来診療をやりつつ、脳卒中などの救急神経疾患を診て、難病・認知症・リハビリ
テーション、これだけの領域をやりながら、少ない人数で脳卒中を断らずに診る
ために脳外科・神経内科の連携、あるいは多科・多職種のチーム医療のなかで
クリニカルパスの開発、あるいはストロークユニット化といった院内システム構築を
やりつつ、かつ地域の医療資源の有効活用、すなわちかかりつけ医やリハビリ専門
病院との医療連携のなかで脳卒中診療ネットワークを構築して、自分たちの得意な
分野でしっかり仕事ができて、かつ患者さん・家族にも満足してもらうような地域
完結型の脳卒中診療体制を目指しました。」
熊本の先生方が、過酷な条件下で最大限の(文字通り超人的な)奮闘をなさって
こられたことが、素人なりに拝察されます。
素晴らしいシステムの開発・構築は、想像を絶する多くの困難を乗り越え、さまざまの
調整過程・試行錯誤を経て実現なさったのですね。
橋本先生はじめ、「熊本方式」を樹立なさり実践なさっていらっしゃる、
おひとりおひとりの先生方に、心よりの敬意と感謝の念を表しないではいられません。
*
「阪神地区でも熊本のような理想的なシステムを構築出来るよう頑張っていきたいと
思います。」
吉村先生の<有言実行>――既に成果を挙げていらっしゃることは、
直前のブログ記事 ★「神戸新聞」(2014年7月18日)の新聞記事でも紹介されて
いましたよね。
兵庫医科大学病院では、本年4月に、
「24時間365日対応する脳卒中センターを開設」され、
「tPAに加え必要な場合には血管内治療も、一連の流れで迅速にできるようにする
ため、周辺の合志病院(尼崎市)と三田市民病院(三田市)、千船病院(大阪市
西淀川区)などと連携」し、「「ドリップ・シップ(点滴と搬送)連携システム」
を構築した。」
「同センターは脳神経外科、神経内科、救命救急センター、リハビリエテーション
部がチームをつくり、脳卒中の患者にいつでも対応できる人員を確保。救急から
リハビリまで一貫した診療に取り組む。」
「7月からは、急性期の患者を集中的に治療する専用病床「脳卒中ケアユニット」
(SCU)」の設置が厚生労働省に認められ、9床を設けた。」
――このような環境整備を進めてこられた、
吉村先生はじめ兵庫医科大学病院の先生方のご活躍はとどまることなく、
「連携する病院をさらに増やしたい。この診療体制が他の地域でも整備されるように、
有効性を示していく。」
との吉村先生の熱意あふれるお言葉が実現されますよう、心より応援しています。
*
今回のブログ記事でご教示いただいた
病院内の「チーム医療」、地域病院間の「連携ネットワーク」――
「ネットワーク」とは、<結節点>と<経路>から成り、<流れ>のあるもの。
人と人が結びつき、協力・連繋によって、困難な道程を切り拓いてゆく――
「熊本方式」「阪神方式」・・・全国津々浦々の、それぞれの地域ならではの
「方式」が開発され、確立され、運用されてゆきますように。
今日の日もまた、大勢の患者さんとご家族の皆さんとともに、
先生方のますますのご活躍にエールをお送りしてやみません。
心よりの敬意と感謝とともに――。