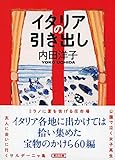『イタリアの引き出し(朝日文庫)』
60篇のショートショート、ミラノを中心にイタリア各地でのエピソードが語られる。著者の付き合いの広さやニュースソース(ジャーナリストだが、取り上げる記事に関連していたのかしていなかったのか不明だが)がうかがえる。彼女のショートショートを通じてイタリアのビビッドな人々の暮らしをうかがい知ることができる。
どの作品も興味深いのだが、最後の一言(一文)が必要だったのか?と感じる作品があった。ない方が良い(蛇足)、あるいは、別の表現が良い(読者である私の理解とのズレ)、ということなのだが、これは、おそらく、著者が作品を書いたときの感性と読者の読みかた(あるいは理解)に齟齬があるからしょうがないのかもしれない。作品というのはそういうものである、ということか。
たまたまだが、著者は今朝(2025-07-26)の日経新聞文化欄の「交友抄」にイタリアの詩人というヴェネチアのゴンドラ乗りのことを書いている。彼との交流はたしか、別の著書『対岸のヴェネツィア』で書いていたはずだ。これは、著者がヴェネツィアで居住(といって、対岸の島)して、ヴェネツィアのことについて書いていて、ベタなヴェネツィアではなく、対岸からみた(角度をかえてみた)作品となっていた。ゴンドラ乗りの親方であると同時に詩人でもあるという人物とであえたという意外性が対岸から眺めたおかげとも言うべきか。
どの作品も興味深いのだが、最後の一言(一文)が必要だったのか?と感じる作品があった。ない方が良い(蛇足)、あるいは、別の表現が良い(読者である私の理解とのズレ)、ということなのだが、これは、おそらく、著者が作品を書いたときの感性と読者の読みかた(あるいは理解)に齟齬があるからしょうがないのかもしれない。作品というのはそういうものである、ということか。
たまたまだが、著者は今朝(2025-07-26)の日経新聞文化欄の「交友抄」にイタリアの詩人というヴェネチアのゴンドラ乗りのことを書いている。彼との交流はたしか、別の著書『対岸のヴェネツィア』で書いていたはずだ。これは、著者がヴェネツィアで居住(といって、対岸の島)して、ヴェネツィアのことについて書いていて、ベタなヴェネツィアではなく、対岸からみた(角度をかえてみた)作品となっていた。ゴンドラ乗りの親方であると同時に詩人でもあるという人物とであえたという意外性が対岸から眺めたおかげとも言うべきか。