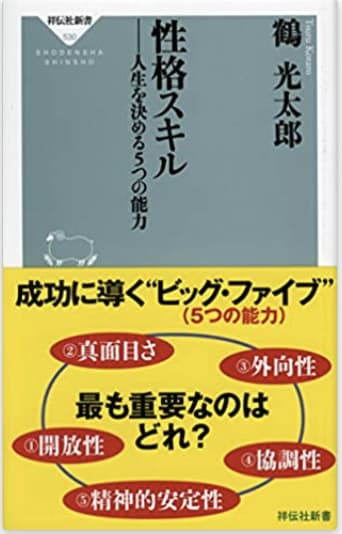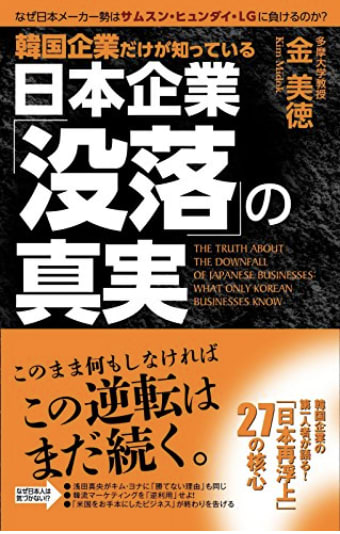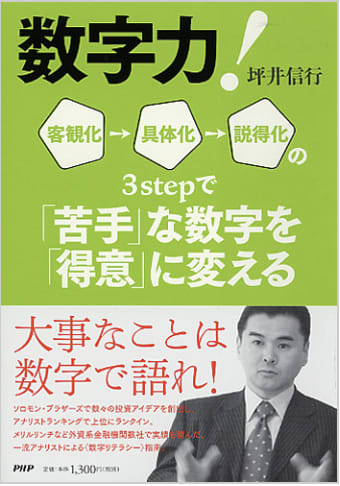@「何も考えていないばかりか行き当たりばったり」がコロナ禍での政府対応策が目立った。しかるに現代、「考えない方が楽」と言う意識も多く、「長いものには巻かれろ」意識が多くなり、自然と「任せっきり」で自分自身で考えない「思考力停止」状態になっている気もする。ここにある「対話」こそその思考力を高める方法かも知れない。
『なぜ、今思考力が必要なのか』池上彰
「概要」思考力がつくと、仕事も、人間関係も、人生も、よりよく変わっていきます。
それは、「自分の可能性に気づくことができる」からです。
⇒「なぜ、いま思考力が必要なのか?」
第1章 戦争・パンデミック・東京五輪──日本が失敗するときの共通点
⇒日本社会が抱える問題のひとつは、失敗を教訓とせず、失敗したときに備えての「プランBを考えない」こと。もうひとつは「精神論に支配される」という点。
NASAvs経済産業省:失敗を恐れず挑戦できるvs 一度の失敗でも出世に関わる
日本は失敗に備えない基本計画を描くのが下手で行き当たりばったりになりがち
日本企業はいざという時株主の言うことを聞かない(資本主義ではない国)
日本は「自分の頭で考える」をしないから次の展開ができない(どこぞの国のまねばかり)
失敗すると「思考停止」となり、「答えがない」となる(精神論だけで突っ込んで行く)
「出る杭は打たれる文化」「空気を読め」など「負の文化」が率先する日本社会
ー知識偏重教育、正解を求める教育が「思考力」を低下させている
思考力でこれまでとは違った視点で自分を見つめ直し、自分をよりよく知ることができる
第2章 自分の頭で考える授業――さあ、一緒に考えましょう
⇒2022年度より高校の社会科が、従来の知識重視から思考力重視へと大きくリニューアル。「地理」や「近現代史」「公共」の紙上模擬授業を行います。
「高度成長経済」は教育水準の高さと人口が要因
戦後の教育から世界史、日本史、地理等が置き去りになる
「地理総合」「歴史総合」により思考力の基礎知識が着くようになる
ーアクティブラーニング「主体的・対話的深い学び」への移行
第3章 折れないしなやかな自分をつくる――乗り越える力
⇒次元の違う道を見つけられるのも、思考の持つ力。「自分の強みを知る」「逆境で腐らない」「斜めの関係」など
「自分だけじゃない」という感覚・視点をもつ
「自分の強み」を見つける
忖度せず「自由にものが言える」環境を見つける
ー「乗り越える力」を得るためには「問いを立てる力」を養うこと
第4章 ステレオタイプ思考は脱却できる――問いを立てる力
⇒ステレオタイプ思考に陥ると頭がこり固まります。それを打ち破るには「問いを立てる力」が有効です。
「何のために」等原点に立ちかえる
「メンターはどう考えるのか」を自分に問いかける
人生には「正解のない社会」が溢れ、「考えない方が楽」と言う傾向がち
ー思考力とは「問いを立てる力」となる
第5章 思考が深まる、新しい発想が湧く――対話の力
⇒思考力を鍛えるための対話実践法です。対話の達人である著者が、「聞き方」「疑問文にすると相手は考える」「対話型リーダーシップ」など、相手を理解し自分もよりよい発想を生み出す「対話の力」
弁証法「「正」「反」の意見の対立を試みる:まず話を聞く
「対話的リーダーシップ」適正をみた役割を与える
ー「疑問文」で話すことで「相手に自分の頭で考えてもらいたい」と言う意志
終章 思考の方程式――9つの考えるヒント
⇒思考力を鍛える実践法。
知的好奇心をくすぐる事実を見つけ、事実を収集して真実に近づける
自分の頭で冷静に考える「定義」「根拠」、作用・反作用の力学で考える
国際スタンダードで物事を考え、3次元で立体的に見て、現実の最新情報を収集
ー「考える癖」をつけ「無知の知」を自覚しながら考えを深める訓練をする