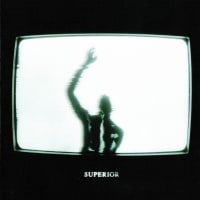ヴィジュアル系とネオ・ヴィジュアル系の境界線はどこに引かれるべきか。この問題は非常に深刻かつゆゆしき問題である。「ネオV系」の存在については、すでにかつてから僕は問題にしてきた(HERE)。最近では、普通に「ネオV系」という言葉が使われているが、僕自身、ずっとこの問題を引きずってきた。(僕自身、2005年からネオV系という言葉を使っているし、また、ドイツの有名サイト「neo tokyo」でもneoという言葉が使用されている)
とりわけ、98年のヴィジュアル系ブームの後、一気にマスコミ、メディアはV系を排除し、若い人々の間でも一気に熱が冷めていった。そして、一時は差別用語として、ヴィジュアル系は語られるようになった。スタジオやメンボ(メンバー募集のチラシ)でも、「ヴィジュアル系NG」といった言葉がいたるところで見られた。ヴィジュアル系バンドをやっていることが「恥ずかしいこと」と思われた時代に入った。20世紀末はV系にとっては本当に受難の時代であった。(Vivid、Fatima、ラムール、S、デュールクォーツ、Phobia、RONDE、Vanillaなどはその時代に頑張っていた)
しかし、その後不死鳥の如く、ヴィジュアル系は蘇り、いつの間にかかつて以上の盛り上がりを見せている。そして、07年のバンド復活ブーム。yoshikiの復活は非常に示唆的である。デランジェの復活もネオV系にとって大きな起爆剤となっている。さらに海外でのV系ムーブメントもまだまだ勢いがある。旧世代、新世代、あらゆる方向からこの動きに勢いを与えているのだ。遂には、NHKで9月1日にネオV系の特番まで放送されることになった!(Music Japanの特番)
この新しい動き(ネオV系ムーブメント)の源泉はいったいどこにあるのか。誰がどのような仕方で新しい方向を見出したのか?
僕は、この問いについて、一つの強い仮説を立てている。それは、上記したディルアングレイの一枚のアルバムから始まった、という仮説だ。ネオV系発生の源は、ディルアングレイの【six Ugly】に帰している。なんじゃそりゃ?と思う人もいるかもしれない。このアルバムは当時かなりの問題作となった。従来のファンの多くがこのアルバムを聞いて去っていった、というのもフリークの間では有名な話。
ディルアングレイは、かつて超コテコテのV系バンドだった。髪の毛の色も赤や青や金。派手で、メタルチックな衣装に身を包み、妖しい歌にマイナーコード中心の暗い楽曲。スカートも着用していた。京は明らかに清春の影響を受けているようなボーカリストだった。事務所はフリーウィル。デビューシングルでは、yoshikiプロデュースによる三枚同時リリース。まさに旧ヴィジュアル系の最後の後継者として華々しくデビューした。Cageという曲は黒夢に触発されたようなエッジの効いたV系王道の切ない名曲だった。98年組の勢いがどんどん衰えていく中、次世代のV系の王者として名を上げようとしていた矢先・・・
上の問題作をリリースした。2002年7月31日だった。このアルバムは全6曲入りで、どの曲もかつての雰囲気を全く感じさせない「奇妙なアルバム」だった。僕自身、当時、6曲全部気に入らなかった(苦笑)。「なんじゃこりゃ、ダメじゃん」と思ったことを今でも覚えている。だが、聴いていくうちになんか魔法にかけられたかのように引きつけられていった。どの曲もすごいこだわっていて、曲の構成やコードワークなど、どれも不可解で魅力的だった。一つ言えることは、どれも過激で激しくて凶暴で暴力的で破壊的だ、ということだ。デカダントな香りがプンプンする。当時、メンバーは、「自分達が育ててきた音楽性を押し殺し、特定の音楽ジャンルを徹底的に突き詰めることで、その音楽ジャンル(このアルバムなら、ミクスチャーやヘヴィネスサウンド)を、ナチュラルに吸収し、昇華することが出来る」、と言っていたそうだ(引用元)。この「昇華」こそ、新たな地平へのきっかけとなったのだ。
このアルバムは実際それほど世の中で話題になったわけではなかった。だが、このディルアングレイの「変身(メタモルフォーゼ)」こそ、後のV系バンドマンたちに革命的変革をもたらした。現在活躍するV系バンドの音を聴いてみると、その節々にこのアルバム(そしてそれ以降のディルアングレイ)の影響を見てとれる。ガゼット、蜉蝣、D'espairs Ray、ギルガメッシュ、サディなどなど。海外で評価されたのも、まずはディルや蜉蝣やディスパだった。新たなV系バンドは、重圧な音と凶暴なイメージを表現することで、新たな新鮮さを手に入れた。一時は厳しい状況に立たされたディルも武道館2デイズを即日完売させるにまで至った。
ディルアングレイのこの変身にこそ、ネオV系の発端ではなかったか。2002年、奇しくも「Visual系」という言葉が誕生してから10年後、新たにV系は生まれ変わり、再び音楽業界を暴れまわろうとしている。第一世代のアーチストたちのバックアップ(や理解)もあり、この勢いはますます加速していきそうだ。まずは、9月1日のNHK特番をしっかりと見たいところだ。
*こうした「変身」は、BUCK-TICKにも確認することができる。「悪の華」、「six nine」、この二枚の「変身」、「変貌」は、ファンのみならず多くの人々に驚きを与えた。