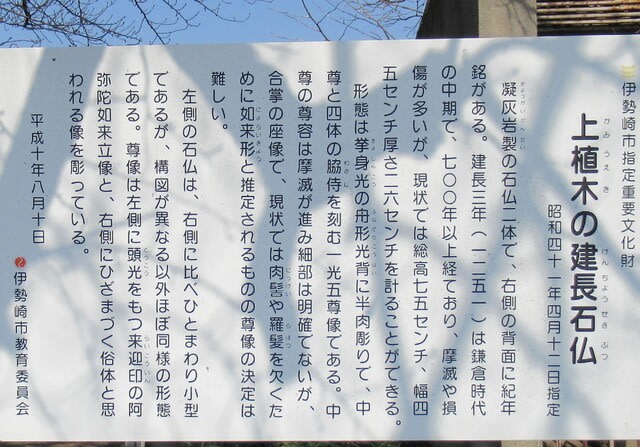夕方、今にも泣き出しそうな空です
ひめちゃんとタバサねーちゃんは、南の方にお散歩です。
小次郎パパも、そこらまでのちい散歩です。

後ろ足が退化して思うように歩けませんけど、まだしっかり食べています。
パパ、ガンバだよ

娘達は、無量寺まで足を延ばします。
無量寺は、僅かの石造物と墓地を残して、一見廃寺です
でも、新川の善昌寺が兼務という形でお寺としては存続しているそうです
垣根の隙間から、ちょっと失礼します。

あの無量寺の記憶は、しっかり民家の庭の中です。
今夕は、雨に濡れずに帰宅できました
あちこちのカテゴリーに散らばった、上野国山上の行仙上人著『念仏往生伝』関係の記事を、集めて編集中です。
「念仏往生伝」第27話は、上野国淵名庄波志江市小中次太郎母 です。
第廿七 上野国淵名庄波志江市小中次太郎母
年八十二。建長六年(甲寅)春往生。兼十七日。高声念仏不懈。最後臨終。端座合掌。金色光明。遙自四方。徹葦墻二重而照。又人々見紫雲瑞 。莫不稱美。
2020年 8月15日、波志江の大シイに逢いに行きました。
シイの木公園に入る路地は狭く、車のすれ違いは難しそうです。
折悪しく、車が出るところで、左折不能、やむなく直進しました。
すると、右に神社が、更に行くとお寺がありました
でも、第一目的地の、大シイに逢いにいこう。
お寺と神社は後回し。
なんとかUターンして、今度はシイの木公園の路地に入れました。
大シイの後は、まずお寺に寄ってみます
ここも波志江のはずです
門柱の間を入ります。
念仏供養塔の文字が見えます
奇縁ですね


かなりクラシックな石造物もありそうです。
山門前が駐車場になってます。


天台宗金蔵寺です。
金蔵寺は「こんぞうじ」と読むようです。
隣はお寺経営の幼稚園です。
せっかちなおじさんは、もうクラシックな山門を通り過ぎて本堂の方に向かってます。

りっぱな本堂です。

見事な向拝です
鶴が目立ちます
このあたりの沼に来ていたことがあるのかな?


名のある彫刻師の作品かもしれませんね
天井絵もあります


鳥、それも鶴がいっぱいいるような感じです
合掌
左手に石仏とお堂があります。


失礼します。
お堂の中は、薬師様?
合掌
おや、お外のお首のないお地蔵様に、「念仏請中」の文字があります

御朱印をと声を掛けてみようとも思いましたけど、8月15日なので遠慮しました。
『上野国郡村誌』に「上野国佐位郡波志江邨」に、金蔵寺があります。
天台宗近江国比叡山延暦寺ノ末派ナリ、村ノ中央ニアリ、開基創建年度詳ナラズ
ここが波志江村の中央だったのです
『ぐんまのお寺 天台宗Ⅰ』(上毛新聞社 平成11)に、
寺伝では平安時代初期、慈覚大師円仁の開山としている。・・・(中略)・・・『念仏往生伝』に、「波志江の市の小中の次太郎母、年八十二、建長六年(1254)春往生」の記事があり、古くから念仏信仰などの盛んなところであったことが知られる。
なんと波志江の老女の記憶が語られています
不思議な御縁で、寄らせていただきました