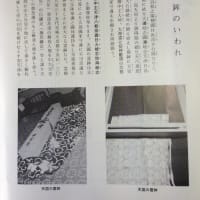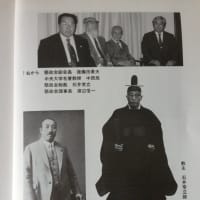「おい、メシ食ったか」田中角栄の人間観が面白い。漆原直行さんが書く。
以下、要約し記す。
⇒
1976年(昭和51年)7月、田中角栄氏は受託収賄罪ならびに外国為替・外国貿易管理法違反の容疑で東京地検特捜部に逮捕されt。全日空の新型機導入選定に絡み、田中は5億円ものリベートを受け取った、とされる「ロッキード事件」です。
この事件は、首相経験を持つ現役国会議員の逮捕事案として世間から注目を集めただけでなく、“金満政治家”として批判されることの多かった田中の悪漢っぷりを端的に示す、シンボリックな出来事として人々に記憶されることになる。
しかしながら、一方では100を超える議員立法(国会議員の発案によって成立した法律)を実現させるなど、常人では真似できないような才覚で、精力的に政務にあたった人物でもあった。
そんな田中は、有り体にいってしまえば、善事から悪事まであらゆるベクトルにおいて規格外の仕事人だった。貶されるときはこれ以上ないくらいの罵詈雑言で貶される一方、褒められたり感謝されたりするときは激賞され、熱狂的なまでに慕われる。その振れ幅の大きさは、そのまま田中氏の懐の深さであり、人間力の高さを表しているようにも感じる。
田中の人間的魅力を示すエピソードとして、次の証言が伝えられている。23年にも渡り、田中氏の秘書を務めた早坂茂三氏の著書にある一節である。。
田中角栄の発想は、すべてわれわれ人間がメシを食い、クソをたれ、失敗したり、泣きわめいたり、笑ったり──という具体的な生活から出ている。田中は「政治とは生活だ」と私に言った。簡潔明快。卓見だと思う。建前と身づくろいの後ろに生身の人間がいる。
だから田中角栄は、人が彼のところにやってくると、まずこう言う。
「おい、メシ食ったか」
大袈裟に言うなら、私はこの一言に、田中角栄の本質がすべて込められていると思う。
(早坂茂三『田中角栄 頂点をきわめた男の物語』より)
めし食ったか──何気ない一言だが、生きることの要諦を集約したかのような力を放っている言葉である。配慮、慈しみ、労い、たくましさ、郷愁感……さまざまな感情を呼び起こしてくれるフレーズとしても心に響いてくるす。
早坂氏は、このような田中氏の発言も紹介している。
メシ時になったら、しっかりメシを食え。シャバにはいいことは少ない。いやなことばっかりだ。それを苦にしてメシが食えないようではダメだ。腹が減って、目が回って、大事な戦はできん。
田中は、極端な偏食家だったそうである。高級店のステーキはクチにしようともせず、猛烈に塩辛い塩鮭一切れを丸ごと入れたおにぎりを求めたり、上質なキャビアには見向きもせず、筋子を欲しがったりしたのだとか。何にでもドバドバとしょうゆをかけるのが好きで、好物のうな重にもしょうゆをかけて食べていたそうである。味の濃いみそ汁、漬け物、甘辛い煮物などを好んで食べていた、という証言もある。要するに、田舎のおふくろの味しか受け付けないような御仁だったわけである。
人によっては、「品のない悪食」「田舎者」と揶揄したくもなるが、事実、田中は新潟の貧しい豪雪地帯出身であり、田舎から立身出世を果たした自身に向けられる偏見を重々承知していた。しかし、そんな泥臭さを隠すこともなく、むしろおのれの武器としてしたたかに立ち回り、高度経済成長の時代にあった日本の政界で猛烈な求心力を放ち続けた。毀誉褒貶はあるにせよ、その圧倒的なまでの存在感は現代においても強い輝きを放ち、その言動はいまでも変わることなく人々の感情を突き動かしている。
ここ数年、田中氏を再評価する気運が高まり、関連書籍が何冊も刊行されたり、ネットで名言が紹介されたりしている。
そうした現象について、たとえば「閉塞感が漂い、将来への不安感ばかりが高まっている現代の日本において、田中はとても魅力的に映るのではないか」とか、「いまの混迷する政治への不満の表れとして、圧倒的な実行力、推進力、求心力を備えた田中角栄のようなリーダーを人々は求めているのだ」といった形で説明されることが多いのだが、その大元にあるのはもっとシンプルな、田中の素朴な人間性であるように思えてならない。田中氏の言動から滲み出てくるまなざしの温かさ、人間という存在そのものを肯定するような姿勢が人々を魅了しているのではないのか。
最後に、田中氏の人間観、政治観がしみじみと伝わってくる発言に触れておく。
人間は、やっぱり出来損ないだ。みんな失敗もする。その出来損ないの人間そのままを愛せるかどうかなんだ。政治家を志す人間は、人を愛さなきゃダメだ。東大を出た頭のいい奴はみんな、あるべき姿を愛そうとするから、現実の人間を軽蔑してしまう。それが大衆軽視につながる。それではダメなんだ。そこの八百屋のおっちゃん、おばちゃん、その人たちをそのままで愛さなきゃならない。そこにしか政治はないんだ。政治の原点はそこにあるんだ。
(大下英治『田中角栄秘録』より)
“第二の田中角栄”と評されるような政治家は、今後、現れてくるのか。