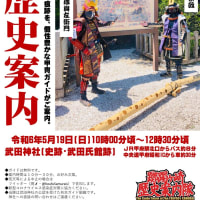信玄ミュージアム内、旧堀田古城園は、1933年(昭和8)に料亭として開業しました。
第二次世界大戦中の休業を経て、1946年(昭和21)に旅館として営業を再開。
1971年(昭和46)の閉館後は、堀田家の方々の住まいに。
そして、2015年(平成27)、甲府市に寄付されます。
開業当時は、「上府中名物の~」と言われるほどににぎわいを見せた料亭。
多くの人・もの・出来事が行き交った、およそ80年の軌跡が、
この近代和風建築には記憶されています。
新型コロナウイルスの蔓延防止のため、長らく臨時休館している信玄ミュージアムですが、
特別展示室を少しリニューアルしたり、旧堀田古城園に残されたものを整理したり、
再びオープンする日を楽しみに準備を進めてきました。
そんな中で見つけたものが、1930年代製造のポータブルの蓄音機。
当初、「これで、もう一度レコードを聴くことは難しいのではないか。」と言われていましたが、
スタッフがきれいにメンテナンスして、再び音を楽しめるようになりました😂

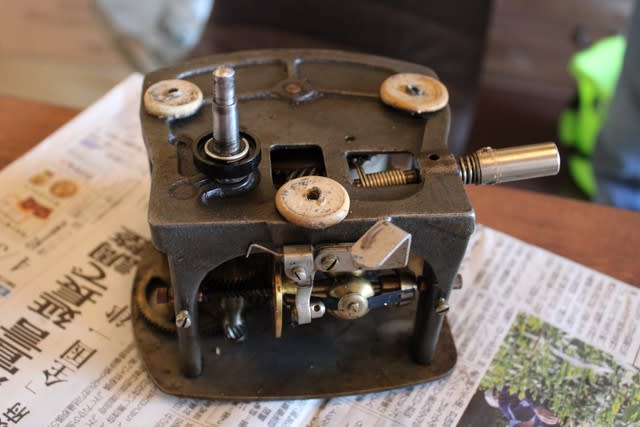
レバーを回せばレコードが回りだす♬
電気も使わないのに、驚くほどの大音量です📯

旧堀田古城園に残されていたレコードは、1970年代前後のものでしたが・・・
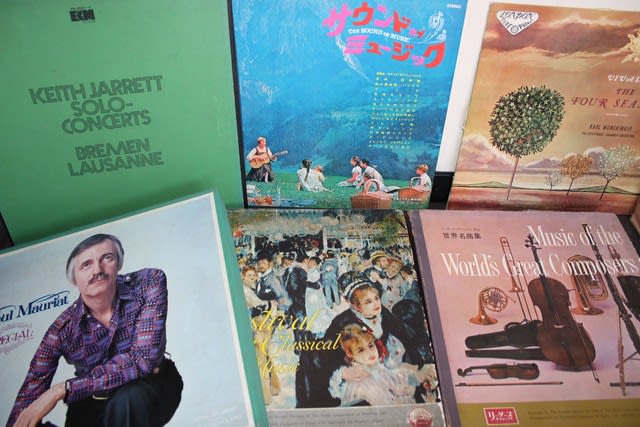
「サウンドオブミュージック」のサントラ、ジャズピアノに、クラシック・・・
料亭が開業したころの昭和初期は、どんな音楽が好まれたのでしょう。
「さくら音頭」などの盆踊り系。
社交ダンスも当時世界的に流行。甲府にもスクールがあったとか。
欧米の曲を日本語でカバーしたもの。
第二次世界大戦中の休業を経て、1946年(昭和21)に旅館として営業を再開。
1971年(昭和46)の閉館後は、堀田家の方々の住まいに。
そして、2015年(平成27)、甲府市に寄付されます。
開業当時は、「上府中名物の~」と言われるほどににぎわいを見せた料亭。
多くの人・もの・出来事が行き交った、およそ80年の軌跡が、
この近代和風建築には記憶されています。
新型コロナウイルスの蔓延防止のため、長らく臨時休館している信玄ミュージアムですが、
特別展示室を少しリニューアルしたり、旧堀田古城園に残されたものを整理したり、
再びオープンする日を楽しみに準備を進めてきました。
そんな中で見つけたものが、1930年代製造のポータブルの蓄音機。
当初、「これで、もう一度レコードを聴くことは難しいのではないか。」と言われていましたが、
スタッフがきれいにメンテナンスして、再び音を楽しめるようになりました😂

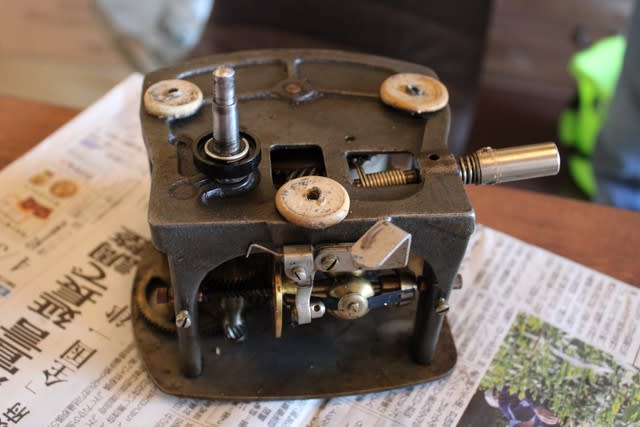
レバーを回せばレコードが回りだす♬
電気も使わないのに、驚くほどの大音量です📯

旧堀田古城園に残されていたレコードは、1970年代前後のものでしたが・・・
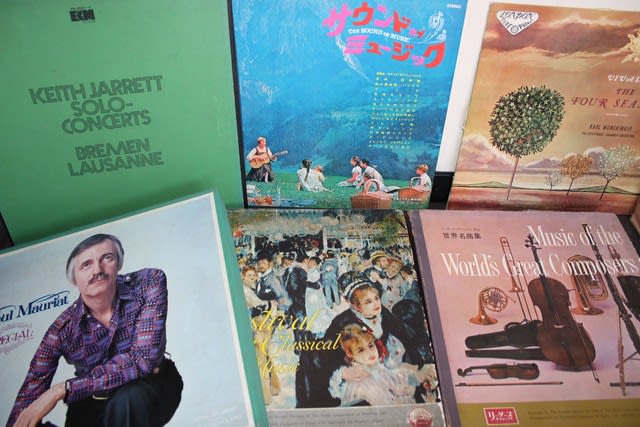
「サウンドオブミュージック」のサントラ、ジャズピアノに、クラシック・・・
料亭が開業したころの昭和初期は、どんな音楽が好まれたのでしょう。
「さくら音頭」などの盆踊り系。
社交ダンスも当時世界的に流行。甲府にもスクールがあったとか。
欧米の曲を日本語でカバーしたもの。
現在放映中の、NHK連続テレビ小説「エール」の主人公、
古関裕而さんの「阪神タイガースの歌(六甲おろし)」も、このころ人気だったようです。
そして、この蓄音機が製造された1930年代は、どんな時代だったかというと・・・
昭和という新たな時代を前に、1923年(大正12)に関東大震災が発生。
その再建で東京は一気に近代化し、欧米の消費文化が持ち込まれた時代。
そのさなかに花開いた、昭和モダン。和洋折衷の近代市民文化。
識字率の高さがベースとなって、
「文藝春秋」などの総合雑誌、川端康成や横光利一などの新感覚派、
江戸川乱歩などの怪奇幻想趣味、「のらくろ」などの児童向け娯楽作品など、
”教養の大衆化”が進みます。
宝塚大劇場、日比谷映画劇場などの大劇場が建設されたのもこのころ。
生活様式も、もちろん変わりました。
鉄道網の充実。地下鉄の開通。流通も発達。
甲府駅には富士身延鉄道線に続き、親しみ込めて「ボロ電」と呼ばれた山梨電気鉄道線も乗り入れます。
山梨県韮崎出身の小林一三は、自身が経営する阪急電鉄の梅田駅に阪急百貨店を開業。
「駅に着いたらお買い物♪」を実現するターミナルデパートの誕生です。
甲府の岡島百貨店も、1936年(昭和11)に開業しています。
ウエイトレスや「バスガール」とよばれたバスの女性車掌など、新しい職業の誕生が拍車をかけて、女性の洋装化も進みます。
ライスカレー、オムライスなどを出す洋食レストランに、カフェーが人気。
インスタントコーヒーやカルピスが開発されたのもこのころ。
モダニズムの楽し気な雰囲気の一方で、
1929年の世界恐慌に引っ張られ、1930・1931年(昭和5・6)に昭和恐慌、
1931年(昭和6)の満州事変、1937年(昭和12)の日中戦争。
時代は太平洋戦争へ確実に向かっていきました。
昭和モダンが、不安や動揺、懐疑などで表現されたモダニズム※と言われる所以です。
※「モダン層とモダン相」、大宅壮一、1930年(昭和5)
人がいて、ものがあってこその空間。
今の旧堀田古城園で、昭和モダンの雰囲気を感じ取るのはきっと難しい。
でも、レコードに録音された音楽が、何かヒントを与えてくれそうです。