(わかりやすく言えば、私たちの世界の変貌、旧世界と新世界)
高度経済成長期以後に生まれ育った若い世代は、生活に結びつく経済状況がひどく悪化してきたということはあったとしても、第三次産業が主流となり消費中心の経済社会やネット環境によるネットを介したつながりという社会環境を割と当たり前の、自然なものとして受けとめているだろうと推測される。
二昔前までは、この世界は割と小規模の閉じられた生活世界であった。食や必要な道具などまだ自給自足的な名残が生活世界には残っていた。わたしの小さい頃の話である。まだ60年代の高度経済成長直前の時期である。わたしの祖母の世代では、一生に二三度くらい大きな旅行ができるという認識だったと思う。その自覚はわたしの父母の世代にも受け継がれていたはずだが、60年代の高度経済成長以後の世界の変貌が、そのことをも解体して見せた。つまり、社会が経済的に豊かになったのである。しかし、それは同時にそれまでの割と牧歌的なのんびりした時間の中の生活という社会的な閉鎖系から消費の拡大を伴う活発な経済社会が人々に慌ただしい開放系に居続けることを強いるようになっていった。これと並行するように、第一次産業が急激に減少し、第三次産業が急激に増大していった。
二昔前まではまだ、わたしたちにとって世界(対象)は小さく割と具体的な手触り中心の世界であった。道具や物のイメージも、柱時計がそうであったようにそれらの内部の機構は歯車のイメージだった。もちろん、真空管を装備したラジオや蓄音機などの電化製品もあったが、生活の主流ではなかった。60年代の高度経済成長の過程で、電気洗濯機、電気冷蔵庫、テレビなどの電化製品や家庭の固定電話が普及し出した。これらの道具や物のイメージはもはや歯車のイメージではなかった。次第に内部はブラックボックス化していき複雑な電子部品の集積や構成のイメージとなっていった。
ここで、私が触れたいのは、次のことである。60年代の高度経済成長の過程では、私の両親もそうだったが、人々はほとんどが慌ただしい労働や生活の日々を送っていたように思う。しかし、現在から振り返ってみれば、二昔前とその60年代の高度経済成長以後では、世界が一変してしまったように見える。このことの意味を人とその人が関わり合ういろんな対象との関係で見てみる。
二昔前であれば、人と諸対象との関わり合いの主流は、まだ農業中心の社会の名残を持った、眼で見たり手で触ったりするというような〈直接性〉や〈具体性〉を持つものだった。ところが、60年代の高度経済成長以後では、人と諸対象との関わり合いの主流は、ちょうど中身はよくわからないブラックボックスだけど使いこなせればいいという関わり合いになった。そしてこのことはわたしたちの現在にまでさらに高度化しながら到達している。この人と諸対象との関わり合いは、〈間接性〉や〈抽象性〉を持つものになってきた。このことは社会のいろんな場面に敷衍できるだろう。例えば、テレビの日々大量に流す情報がある。テレビの番組や情報の扱い方にも作家が物語を作り上げていくように番組制作側の意図やあるいは局側の意向なども加わるということ、さらに悪く取れば人々の考えをある一定の方向へ導こうとする作為こめることができること(例えば、「地球温暖化」対策キャンペーンやわが国が膨大な借金を抱えているというキャンペーンなど)を、内省すればわたしたちは持つことができる。しかし、わたしたち普通の生活者は、実際には割と無自覚に自然な感情の状態でテレビを観ていることが多い。
そのテレビの情報も銀行あるいはコンビニのATM(現金自動預払機)お金の出し入れも、ネットショッピングやネット上での代金の決済も、あるいはさらに、遙かな遠い観測された銀河の振る舞いについても、現在の社会のあらゆるものが気づいたら(つまり、わたしたちは知らない間に徐々に慣れてきたのである)、中や中間の仕組みは分からなくても、ある対象のことをわかったり(わかったつもりになり)、それに基づいてある判断や行動を取るようになっている。わたしたちがあるものやある人に慣れるということは、日々の出会いと時間のくり返しの中にある。その過程を経て、わたしたちは対象に対して徐々に自然な受け止めや感情を持つようになるのである。もちろん、過敏な人で、その移行に敏感に反応して自然に慣れてしまうことができずに異和を持ち続ける人々も少数はいるかもしれない。
そして、それらの人と諸対象との関わり合いを支えているのは、〈信頼性というシステム〉である。現在のわたしたちの割とスムーズな日常生活はその〈信頼性というシステム〉に支えられていることは間違いない。時々食品偽装や手抜き建築、あるいは虚偽の情報が流されたなどが事件として浮上してくることもあるが、わたしたちの社会の主流はこの〈信頼性というシステム〉にあることは確かである。
二昔前と高度経済成長期以後との間には、この人と諸対象との関わり合いの構造的な変容が起こっていると言えるだろう。ここで「構造的な変容」というのは、新旧が次元や段階を異にするほどの大きな変貌という捉え方から来ている。それを人と自然との関わり合いでいえば、人 ― 一次的な自然という関係から、人 ― 二次的な自然(人工的な自然)という関係に構造的に変容してきたということができる。もちろん、時代の主流としてであり、両者ともにもう一方を部分的には内包したり残存させたりしているはずである。さらに、両者の中間の過程は、その主流の動的な移りゆきの過程と見なすことができる。そうして、これらの人と諸対象との関わり合いの高度化は避けることのできない世界の変貌である。

















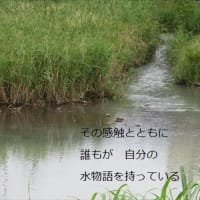
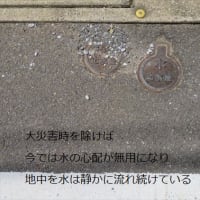

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます