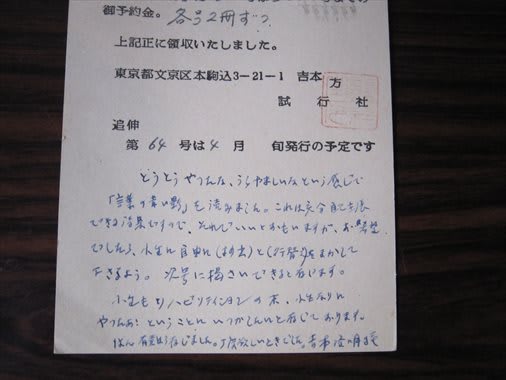自己表出と指示表出の関わりで、吉本さんの「拡張論」(『ハイ・イメージ論Ⅱ』ちくま学芸文庫 この単行本は、1990年4月刊)を見ていたら、その次の「幾何論」の中、ヘーゲルに触れた吉本さんの言葉や引用されたヘーゲルの言葉の中に、「Etwas」が使われていた。せっかくだから、吉本さんが取り上げている話のひとまとまりの部分として抜き書きしてみたい。
ヘーゲルの考え方では、ある物(体)(Etwas)がそこに(da)ある(sein)かぎり、他の物(Anderes)への関係をもっている。このばあいこのほかの物(Anderes)は、もとのある物(Etwas)からみれば非有(あらざるもの)としての一つの定有物(きまったもの)(ein Dasein endes)だということができる。したがってこのある物は限界や制限をもった有限のものだ。
いまある物(Etwas)がそのものとしてどういう本性をもつかということが、そのある物(Etwas)の規定だとすれば、この規定が関係をもっているほかの物(Anderes)によってどうなっているかということが、そのある物(Etwas)の性状だということになる。
このある物(Etwas)のなかで、それ自身からみられた規定と、関係するほかの物からみられた規定とが、どうなっているかがこのある物(Etwas)の質にあたっている。こうかんがえてくると、ある物(Etwas)が質であるかぎりは、かならずほかの物(Anderes)との関係によってみられた性状をふくんでいることになる。いいかえればじしんの存在する理由を他者にもっているから、かならず「変化」するということができる。「変化」によって性状は止揚されるし、「変化」そのものもまた止揚される。この止揚によって物(体)がどうなるか、ヘーゲルはつぎのようにいう。
この変化において或る物(Etwas)は自分を止揚し、他物(das Andere)になるが、同様に他物もまた消滅するものである。しかし、他物の他物〔他者の他者〕(das Andere des Andern)または可変体の変化〔変化の変化〕(die Veranderung des Veranderlichen)(引用者註.「a」は2つとも「¨a」)は恒常的なものの生成(Werden des Bleibenden)であり、即且向自〔それ自身で〕に存在するものの生成であり、内的(インネンス)なものの生成である。
(ヘーゲル『哲学入門』第二課程 第一篇 第一段B)
ここで「恒常的なものの生成」というのはすこし強勢で「不変のまま残留するものの生成」くらいにしておいた方がいいようにおもえる。ヘーゲルがいいたいことは、それほど難しくない。あるひとつの物(体)が存在していることのなかには、他者との関係によって存在している面がかならずある。いいかえれば他者があるからそのものとの関係で存立している部分をもつ。そうであればそのひとつの物(体)は、他者が変貌するにつれて外から変化するか、じぶんの変貌によって関係する他者を変化させることで、じぶんが内在的に「変化」することがおこりうる。この「変化」によってそのひとつの物はまたほかの物に変化し、ほかの物は消滅したり、ほかの物のほかの物に変化する。この後者の変化は、いわば止揚としての変化であり、生成したものは不変のままとどまったもの、つまりは内的なものだ、ということになる。もしこのある物(体)が、たくさんの特性によってほかの物と区別されているとすれば、この特性の「変化」によって解消したことになる。
幾何学的な認識が(たとえばスピノザが)、「変化」という概念をうみだそうとしなかったし、うみだすことができなかった理由は、概念を定在の点のようにかんがえて、その存在、定立の理由を自律的なものとみなしたからだとおもえる。ひとつの概念が現実にむすびついて存立するためには、ほかの概念との関係が必要だという観点はスピノザにはなかったし、またはじめから必要としなかった。これに反しヘーゲルの概念のつくり方は、はじめから関係なしには、成立しなかった。
まず対象との直接の関係を衝動とかんがえれば、衝動面にたいして任意の角度をもった志向性が、この面をつきぬけて直進して行為となるかわりに、行為とならずに衝動面で反射したとすれば、この反射を反省とみなすことができる。(引用者註.第2図は略)
そして反省を数かぎりなく繰り返すことで、対象との関係がじぶんとの関係に転化したものが、ヘーゲルでは自我とよばれている。そして自我と対象との関係が哲学のいちばんはじめにあり、これはヘーゲルについて最初にいわれるべきことのようにおもえる。このいちばんはじめの関係から、はじめに意志とか決意とか企画とかいった自我の内的な規定であったものが、対象へむかう過程でしだいに外的な規定に移ってゆく。それが行為(Handeln)とみなされている。
ヘーゲルの方法にとって「生命」の概念や「変化」の概念よりも、ある意味では自我と対象、有機的な自然と非有機的な自然、認識と行為といったような、事象を二項対立に分離したうえでそれを関係づけるほうが本来的なかんがえだといえばいえた。ここからヘーゲル哲学の流動的なもの(つまり概念を移行と消滅の相のもとでみること)がはじまったからだ。認識と行為のあいだで、あるいは自我とその対象とのあいだで、はじめに内的な規定であったものが、次第に外的な規定へとうつってゆき、そのうつり方の曲面は、曲率もちがえば、通過する過程もちがうが、内在から外在へとえがかれてゆく行為の曲面の変化こそが、ヘーゲル哲学の入口にひかえていたおおきな形象であった。(引用者註.第3図は略)
(『ハイ・イメージ論Ⅱ』「幾何論」 P105-P110)
関連ブログ記事
1.「エレヴァス」問題 2016年12月15日 | 吉本さんのこと
https://blog.goo.ne.jp/okdream01/e/0a645cd9fa29e45cb3093d273d5a5991
2.「エレヴァス」問題再び 2017年02月23日 | 吉本さんのこと
https://blog.goo.ne.jp/okdream01/e/09f08d935375ab5bedeafe351742cc59