知人に
「ソーシャル・スキル・アルバム」著ジェド・ベイガー 明石書店 2000円
という本をいただきました。
自閉症のある子に教えるコミュニケーション、遊び、感情表現について
写真つきで説明した本で、
子どもと写真どおり演じながら、
基本の対人関係のスキルが学べるようになっています。

227ページの大判で見やすくたくさん例が載っている本です。

「この女の子はジャンバーのチャックが閉められません。
先生達の話を中断させて、手伝いをお願いするつもりです。」
という写真と説明があると、

次のページには、
よいやりかた「この女の子は、先生たちのところに行き、
先生達が話をやめて、
自分の方を見てくれるのを待っています。」
という写真と説明
よくないやりかた
「この女の子は、話がとぎれるのを待ちませんでした。
先生の注意を引くために、うでを引っぱりました。」
という写真と説明が載っています。

次のページには、「すいません」と言ってから、
手伝いをお願いすることが、写真つきで説明してあります。

その次のページには、
相手の答えを待ってから、その場をはなれる前に「ありがとう」
と言うことが、写真つきで説明してあります。
このように、とてもていねいに、
自閉症スペクトラムの子どもが、
家庭や学校での、対人関係のスキルを身につける方法が
紹介されています。
紹介されているスキル
 スペースインベーダーにならないようにしよう
スペースインベーダーにならないようにしよう
(会話をする時、相手から適当にはなれる)
 聞くときの態度
聞くときの態度
 中断させる 1・2・3(友だちにおもちゃをかしてもらう)
中断させる 1・2・3(友だちにおもちゃをかしてもらう)
 あいさつ
あいさつ
 話を聞くこと
話を聞くこと
 会話を始め、会話をつづけること 1 2
会話を始め、会話をつづけること 1 2
 会話を終わらせること
会話を終わらせること
 自己紹介
自己紹介
 いつ話をやめるとよいかを知ること
いつ話をやめるとよいかを知ること
 遊びにくわわる方法
遊びにくわわる方法
 分け合うこと
分け合うこと
 ゆずりあうこと
ゆずりあうこと
 交代で遊ぶこと
交代で遊ぶこと
 ゲームで遊ぶ
ゲームで遊ぶ
 落ち着くこと
落ち着くこと
 人の気持ちがわかっていることをしめすこと
人の気持ちがわかっていることをしめすこと
(人が悲しんでいたり、おこっていたり、助けを求めていたりするときの
サインに気をつける)
 「だめ」という返答を受け入れること
「だめ」という返答を受け入れること
 まちがったときのこと
まちがったときのこと
 はじめてのことをしてみること
はじめてのことをしてみること
 からかわれたときのこと
からかわれたときのこと
 課題が難しくてもやってみること
課題が難しくてもやってみること

↑
いつもどうもありがとうございます。
「ソーシャル・スキル・アルバム」著ジェド・ベイガー 明石書店 2000円
という本をいただきました。
自閉症のある子に教えるコミュニケーション、遊び、感情表現について
写真つきで説明した本で、
子どもと写真どおり演じながら、
基本の対人関係のスキルが学べるようになっています。

227ページの大判で見やすくたくさん例が載っている本です。

「この女の子はジャンバーのチャックが閉められません。
先生達の話を中断させて、手伝いをお願いするつもりです。」
という写真と説明があると、

次のページには、
よいやりかた「この女の子は、先生たちのところに行き、
先生達が話をやめて、
自分の方を見てくれるのを待っています。」
という写真と説明
よくないやりかた
「この女の子は、話がとぎれるのを待ちませんでした。
先生の注意を引くために、うでを引っぱりました。」
という写真と説明が載っています。

次のページには、「すいません」と言ってから、
手伝いをお願いすることが、写真つきで説明してあります。

その次のページには、
相手の答えを待ってから、その場をはなれる前に「ありがとう」
と言うことが、写真つきで説明してあります。
このように、とてもていねいに、
自閉症スペクトラムの子どもが、
家庭や学校での、対人関係のスキルを身につける方法が
紹介されています。
紹介されているスキル
 スペースインベーダーにならないようにしよう
スペースインベーダーにならないようにしよう(会話をする時、相手から適当にはなれる)
 聞くときの態度
聞くときの態度 中断させる 1・2・3(友だちにおもちゃをかしてもらう)
中断させる 1・2・3(友だちにおもちゃをかしてもらう) あいさつ
あいさつ 話を聞くこと
話を聞くこと 会話を始め、会話をつづけること 1 2
会話を始め、会話をつづけること 1 2 会話を終わらせること
会話を終わらせること 自己紹介
自己紹介 いつ話をやめるとよいかを知ること
いつ話をやめるとよいかを知ること 遊びにくわわる方法
遊びにくわわる方法 分け合うこと
分け合うこと ゆずりあうこと
ゆずりあうこと 交代で遊ぶこと
交代で遊ぶこと ゲームで遊ぶ
ゲームで遊ぶ 落ち着くこと
落ち着くこと 人の気持ちがわかっていることをしめすこと
人の気持ちがわかっていることをしめすこと(人が悲しんでいたり、おこっていたり、助けを求めていたりするときの
サインに気をつける)
 「だめ」という返答を受け入れること
「だめ」という返答を受け入れること まちがったときのこと
まちがったときのこと はじめてのことをしてみること
はじめてのことをしてみること からかわれたときのこと
からかわれたときのこと 課題が難しくてもやってみること
課題が難しくてもやってみること
↑
いつもどうもありがとうございます。















 自閉症(言語障害。他人に興味をしるさない)
自閉症(言語障害。他人に興味をしるさない)
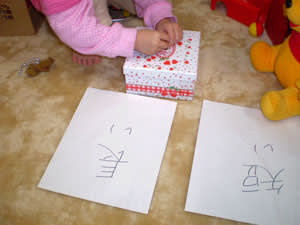




 「自閉的」といわれる子どもたち 石井 葉 著 すずき出版
「自閉的」といわれる子どもたち 石井 葉 著 すずき出版


 。
。









 ?
? ?
?

 数の大小(1から5まで)が長い間わからず困っています.
数の大小(1から5まで)が長い間わからず困っています.





















 引用は「問題行動と子どもの脳」浅野幸恵 築地書館より
引用は「問題行動と子どもの脳」浅野幸恵 築地書館より