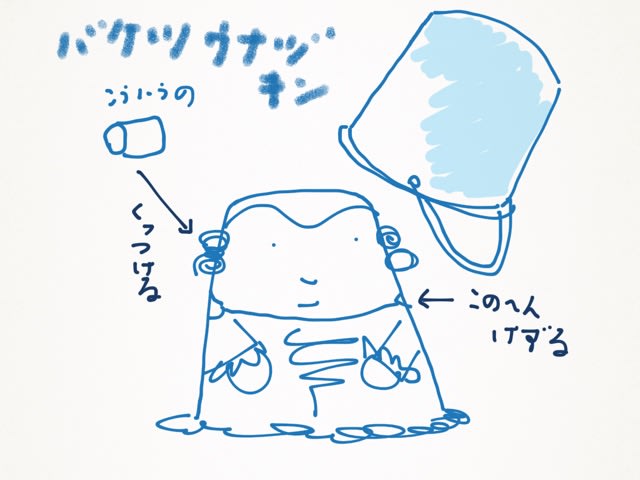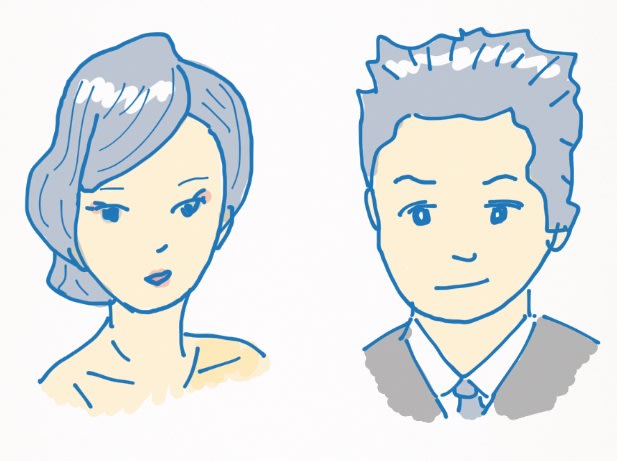明日は、セレネ美術館の展示室で行われるコンサートは、ちょっと興味深いものなんです。
「フーガとの出会い」「歌い継がれる旋律」というタイトルがついていて、ただ美術館の中で生演奏するというだけでないテーマがあるんです。
第1部は、「フーガとの出会い」と名付けられ、J.S.バッハの「フーガの技法BWV1080よりに続いて、モーツァルトの「ヴァイオリンとヴィオラのための二重奏曲変ロ長調K.424が演奏されます。
チラシの解説には、モーツァルトmeetsJ.S.バッハと書かれています。モーツァルト音楽祭にも深い関わりがありそうなので、要約します。
1782年、アマデウスはウィーンであるコンサートに招待されたそうです。プログラムはバロックの巨匠バッハとヘンデルの作品のみだったそうですが、アマデウスはこの時初めてバッハの音楽に触れます。
アマデウスの時代には、バッハの作曲法(対位法)はあまり受け入れられていなかったのですが、アマデウスはバッハの素晴らしさに目覚め、フーガの研究に没頭し始めるそうです。
アマデウスは、音楽通にも、一般の人にも、だれが聴いても満足できる曲作りを目指し、バッハから学んだフーガの技法と、彼自身の豊かな完成を融合させることで数々の傑作を生み、今も多くの人に親しまれています。
今回は、こうしたことに注目して、バッハ晩年の傑作と、アマデウスがバッハ研究を行った翌年の作品が演奏されます。
と、いうことなんです。
興味深いですね。
先日、ある番組で音楽の歴史について解説していましたが、ジャズなどはだれの音楽に近いかと言われると、バッハなんだと説明していました。そういえば、ジャズ・ピアニストでバッハを弾く人もいらっしゃいます。
音楽は、どこかの1点で現れるわけではなく、必ず何かとつながって流れとして登場するわけですから、今回の演奏会はそうした部分をよく感じられるものになりそうです。
第2部は、西欧音楽とロシア民謡がゆうごうして発展したロシアのクラシック音楽を描きます。ロシア民謡の響きは、哀切を感じさせ、日本でも多くのファンを持っていますよね。グラズノフ、リムスキー=コルサコフら10人が合作した「ろしあ民謡による変奏曲」とトルストイが涙を流したという「アンダンテ・カンタービレ」が演奏されます。
演奏者のうち、内山さんと渋谷さんの似顔絵を描いてみました。よけいだったかな(笑)
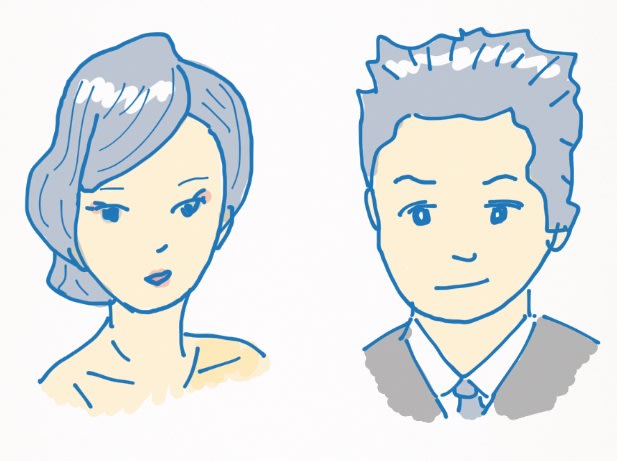
お二人とも、モーツァルト音楽祭にも何度もご出演いただいています。