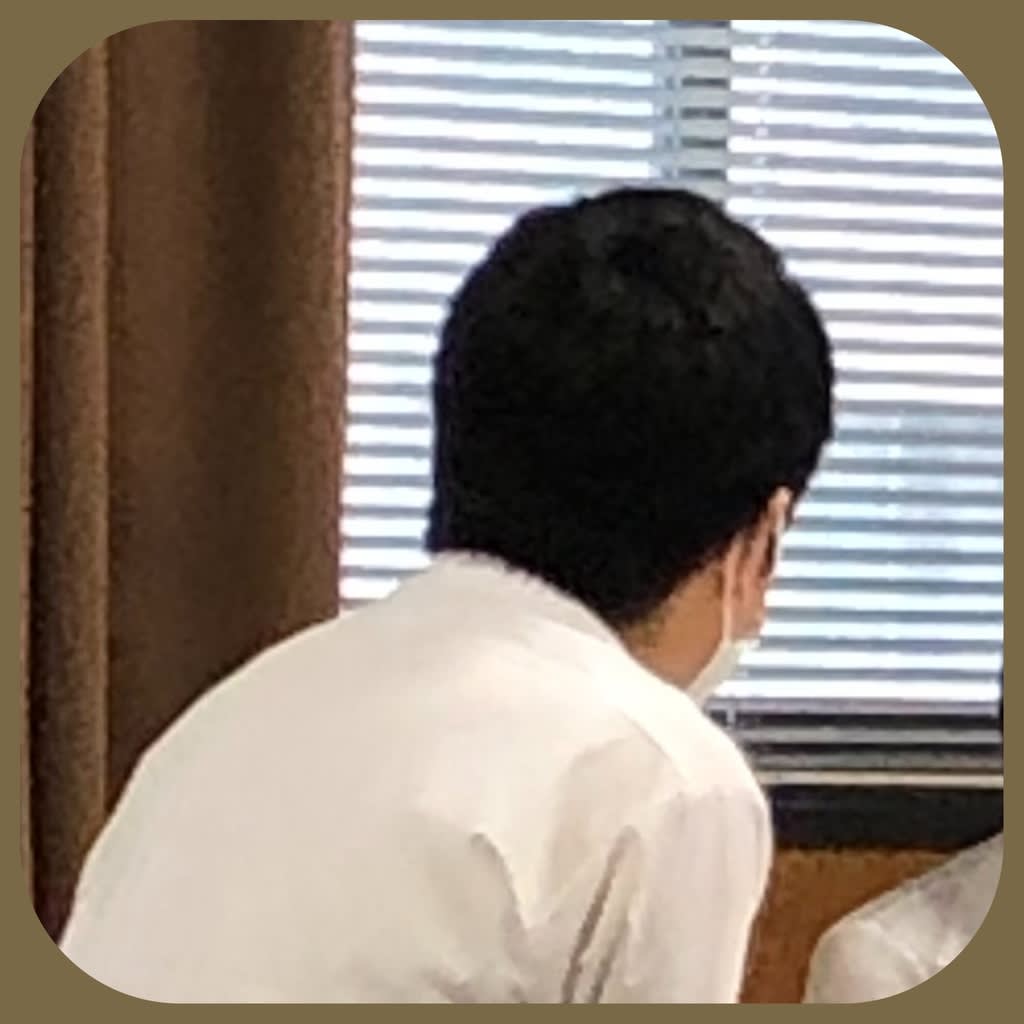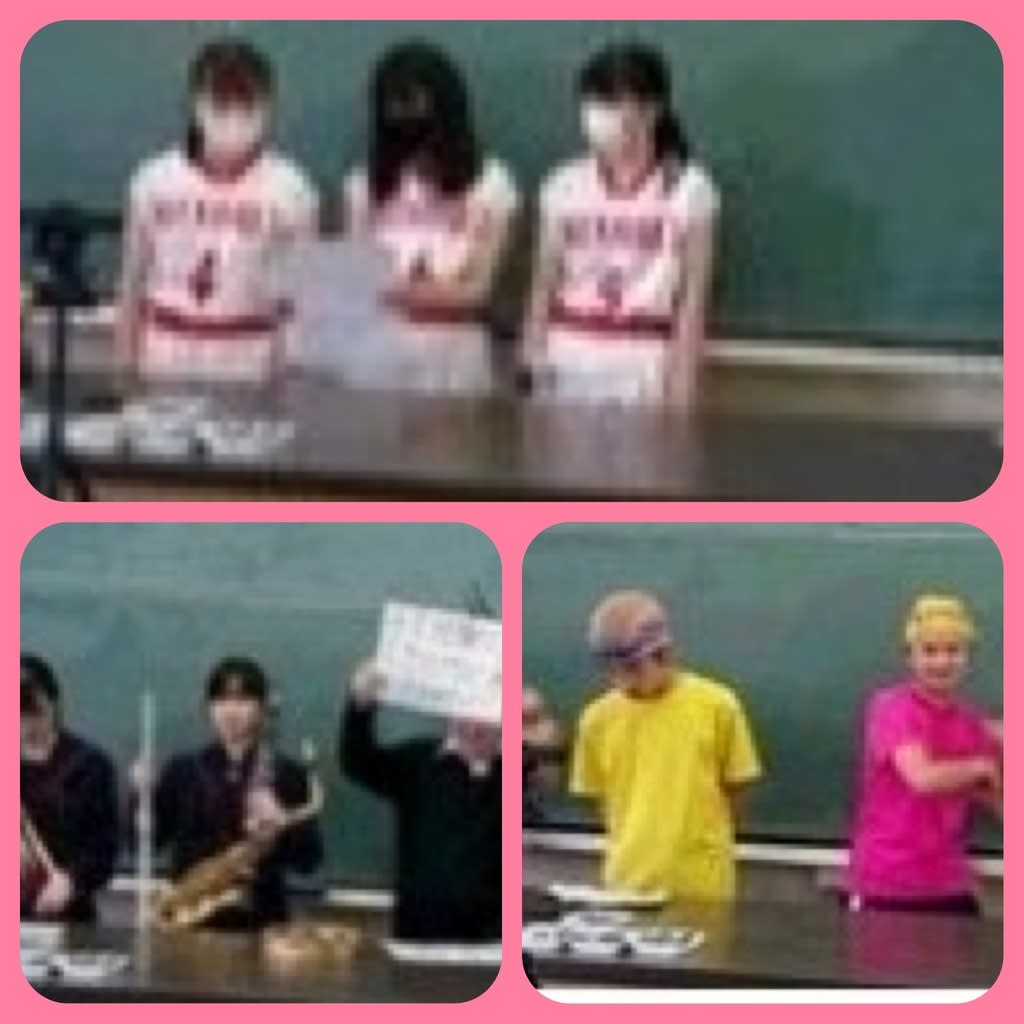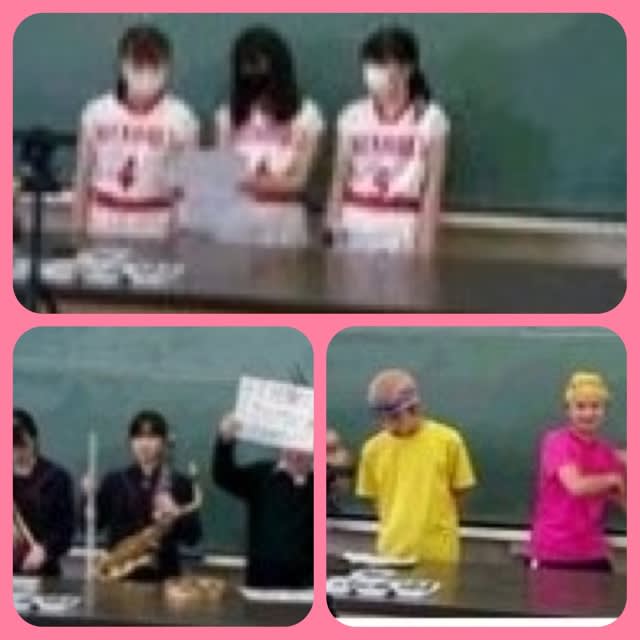学校では近頃、メンタル面での病休をとる教員が増えています。
病休の理由は様々ですが、独身の若手教員が多いようです。
その理由として、児童生徒への指導につまずいている、保護者とのコミュニケーションがうまくいかない、職場の人間関係の問題などを、おそらく思いつく人が多いでしょう。
もちろん、それらもありますが、教員の仕事は授業準備に加え、学校行事の準備や部活の事務的な仕事、校務を担うなど、複数の業務にまたがっています。
そういう場合は、傍からみているとなんとなく労働意欲が下がっているように見えます。
こうなると、管理職は要注意です。日頃の小さな困難がいくつも積み重なり、「大きく厚い壁」として、本人の前にそびえ立っているようなものです。
その前で、立ちすくんでいる教員は、相談するのが苦手で、相談できる人が少なく、かつ責任感の強い人が多いようです。
「この先どうなっていくか不安である」という気持ちでいっぱいになって、「もう、ダメだ」となって学校を休み始めるのではないかと、私は考えています。
くわえて、昨年は新型コロナウイルス感染防止のための臨時休校が続きました。
登校が始まってからでも、つねに感染防止に傾注した授業や活動を行い、消毒作業もありました。
いまや、教員にとって学校現場は、ストレスフルな労働の場になっています。
ストレスを少なくするには、職員同士の雑談やコミュニケーションがじつは効果があるのですが、メンタルヘルス対策が十分できるような余裕がおたがいにありません。
心を病む教員が出ても無理のないことだと思います。
とくに、若年層の教員が相談できる相手としての同僚や上司がそばにいることが極めて重要になります。
コロナ禍でストレスを抱えているのは児童生徒だけではなく、教員も同様です。