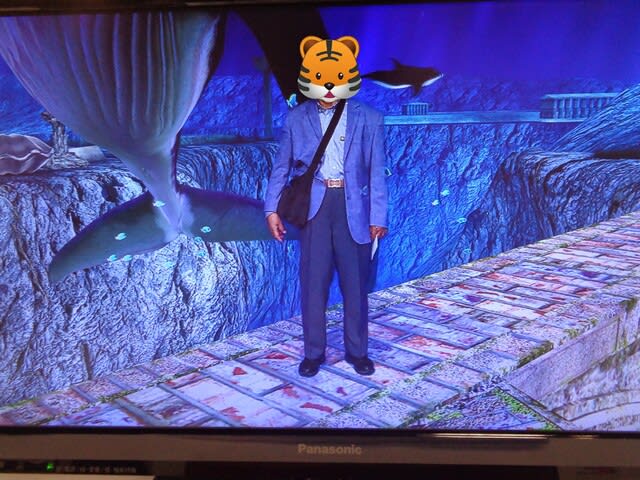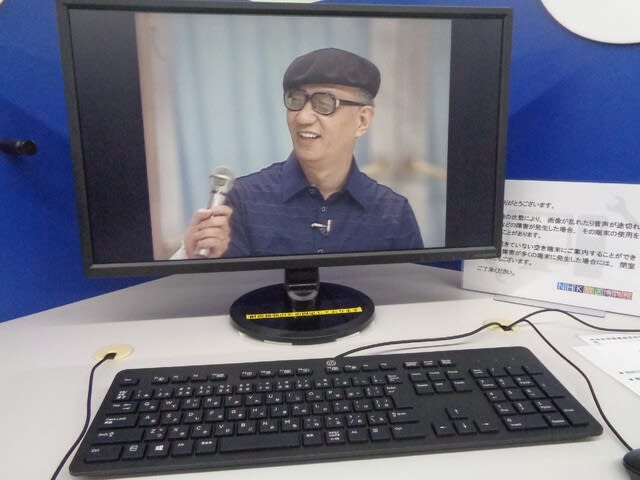[書籍紹介]

副題に「小説 小泉八雲」とあるように、
小泉八雲=ラフカディオ・ハーン(1850-1904)についての伝記小説。

宣伝文句が内容をよく表しているので、掲載する。
『怪談』『知られぬ日本の面影』『日本――一つの試論』。
日本人も気づいていなかった日本文化の魅力・価値に気づき、
世界に広めた人物、小泉八雲。
自身の生い立ちに由来するコンプレックス、
葛藤にもがいていたかつての彼、
「ラフカディオ・ハーン」はいかにして
「日本人・小泉八雲」となったのか。
日本へ渡り、日本人の生き方や文化、
そして妻となる女性、小泉セツに出会い、
彼の人生はヤゴがトンボとなって飛び立つがごとく変わっていく――。
アイルランド出身の著者が描く、
空想と史実が織りなす魂の伝記小説。
日本人とは何かという問いを、現代の私たちに投げかける。
他に、次のような紹介文も。
出生によるコンプレックスと孤独を抱えていた
ラフカディオ・ハーン(のちの小泉八雲)。
その人生は、日本との出会いによって
大きく変わっていく。
横浜から松江への旅、武家の娘セツとの結婚、
息子の誕生、日本への帰化、
霊峰・富士山への登頂。
彼が日本人よりも日本を愛した男、
「小泉八雲」となるまでをあざやかにえがく。
略歴も引用。
パトリック・ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)は、
1850年6月27日に
ギリシャ西部のレフカダ島で生まれました。
父チャールズはアイルランド出身の軍医、
母ローザはギリシャ・キシラ島の出身です。
アイルランドは当時まだ独立国ではなかったので、
ハーンはイギリス国籍を保有していました。
2歳の時にアイルランドに移り、
その後イギリスとフランスでカトリックの教育を受け、
それに疑念を抱きます。
16歳の時、遊戯中に左目を失明。
19歳の時、父母に代わって八雲を養育した大叔母が破産したことから、
単身、アメリカに移民。
赤貧の生活を体験した後、
シンシナティでジャーナリストとして文筆が認められようになります。
その後、ルイジアナ州ニューオーリンズ、
さらにカリブ海のマルティニーク島へ移り住み、
文化の多様性に魅了されつつ、
旺盛な取材、執筆活動を続けます。
ニューオーリンズ時代に万博で出会った日本文化、
ニューヨークで読んだ英訳『古事記』などの影響で来日を決意し、
1890年4月に日本の土を踏みます。
同年8月には松江にある島根県尋常中学校に赴任し英語教師に。
さらに熊本第五高等中学校、神戸クロニクル社の勤務を経て、
1896年9月から帝国大学文科大学講師として英文学を講じます。
1903年には帝大を解雇され、
後任を夏目漱石に譲り、
さらに早稲田大学で教鞭を執ります。

この間、1896年には松江の士族の娘、
小泉セツと正式に結婚し、日本に帰化。
三男一女に恵まれます。
著作家としては、翻訳・紀行文・再話文学のジャンルを中心に
生涯で約30の著作を遺しました。
1904年9月26日、心臓発作で54歳の生涯を閉じます。
日本での生活は14年でした。
筆者のジーン・パスリーは脚本家。
長年日本で暮らしていた時、
アイルランド出身だと言うと、
「ああ、ラフカディオ・ハーンですね」
と度々言われて、知るようになる。
アイルランドに帰国すると、
ダブリンで、ラフカディオ・ハーンが幼少期に暮らしていた家の近くに
たまたま住み、興味を抱き、
それが本書に結実した。

本書は小泉八雲の生涯を辿るが、
評伝ではなくフィクション(小説)の形を取っている。
しかし、小泉八雲の著作からの文章を
注釈の形ではなく引用することで、
その姿に真実味を与え、
息づいた生身の人間として描いている。
小泉八雲と言えば、
「日本の伝説を収集して『怪談』を表した帰化人」
くらいの知識しかなかったが、
本書によって、
外国人から見た日本と日本人と日本文化の特質が
見事に解明されている。
小泉八雲が来日した1890年は明治23年で、
文明開化の真っ最中。
西洋文化の浸食で、
日本文化が失われつつある時で、
小泉八雲は特に東京や横浜の西洋化を憎んだ。
最初の赴任先が松江という、
都会から離れ、西洋文化に犯されていない場所だったことで、
小泉八雲の日本愛が育まれた。
ハーンは空高く舞う鷹のような気分で、
まだ西洋の手が及んでいない
未開の地をじっと見つめながらつぶやいた。
「ああ、ここだ! 私が求めていた場所はここなのだ。
この地なら、きっとすべてがうまくいく!」
来日した西洋人の誰もが
必ずしも日本文化を愛するわけではないが、
小泉八雲自身の感性が日本文化と共鳴したようだ。
特にそのことが顕著に現れるのは、
知事の令嬢からいただいた
虫駕籠の中の虫(クサヒバリ)の鳴き声を
こよなく愛したという点だ。
普通、西洋人は虫の音を聞いても騒音としか思わず、
虫の声にもののあわれを感ずるのは、
日本人特有のものと言われている。
それを小泉八雲は感ずることができたのだ。
八雲は、虫の鳴き声が日本人の暮らしのなかだけでなく、
詩歌などの文学でも履く別なものとして扱われていることを知り、
日本人の美の感受性は突出てして発達していること、
そして、西洋人において、その分野は、
まだほとんど未開発のままだと感じていた。
コオロギ一匹の素朴な鳴き声で、
これほどまでに豊かな空想を呼び起こす民族から、
西洋人は多くのことを学ばねばならない。
たしかに産業技術に関しては、
西洋の方が進んでいる。
だが、自然に対する真摯な姿勢は、
日本の方が何千年も進んでいるのだ。
日本人の自然と共存する姿を、こう書く。
日本では、川や岩、山や木や井戸など、
生物であろうとなかろうと、
あらゆるものに神がいると信じられている。
稀に、岩や木にしめ縄がかけられていることもあるが、
それはその岩や木が神聖なものであることを意味しており、
ハーンは、これほどまで自然に対して
敬意の念を払っている人種を見たことがなかった。
神社仏閣の静謐さへの感性も同様。
特に、日本人が先祖を大切にすることに
感銘を受けているのも、
並の西洋人とは違う。
お盆の行事を見て、
日本人が霊と共に生活していることを感ずる。
日本にはどの家にも先祖を偲ぶ仏壇というものがあり、
家族は毎日、食事の一部と水をそこに供えるとのことだった。
日本における先祖とは、
死んだらいなくなるものではなく、
その後も家族とともにに存在しつづけるものであり、
そのため生きている家族は、
死んだ者に対して、
いつも身近にいる存在のように見守り、
語りかけるらしかった。
それを聞いたハーンは感動した。
ハーンの知る、死者どころか
生きている者にさえ礼節を欠く西洋の家庭とは、
なんとちがっていることだろう。
行方不明で亡くなった船乗りの墓に供えたある食事を見て、
ハーンは激しく心を揺さぶられた。
生きている間はもちろんのこと、
死んだ後でさえも面倒をみてくれる家族がいる。
それほどまでに人から愛されるとは、
どういう感覚なのだろう?
(盆の最終日、精霊舟で先祖の霊を送り出すのを見て)
その穏やかな儀式を浜辺に立って見つめていたハーンは、
ある神秘的なことに気づき、感動に包まれた。
それはハーンがこれまで見聞きしてきたこと、
すなわち、神々とは亡くなった愛しい人たちであるとする
神道の世界観が、
いま、目の前の状況とピタリと合致したことだった。
また、日本人特有の「全体主義」も驚きの対象だった。
個人主義の西洋人から見ると、
公を重んじ、社会に奉仕する日本人の価値観に驚嘆する。
日清戦争に赴く教え子の
国の為に命を捧げる覚悟を見せられた時、涙する。
日本では、他人を犠牲にしてまで、
己の目標や幸福を追求すると
非難されるのだと、
その時、ハーンは学んだ。
個人の欲望は、集団の要求のなかで見出さなければならず、
離反者は、その集団から排斥されてしまう。
ハーンは問う。
「個人の幸福は、重要ではないと?」
友の答えはこうだった。
「そのとおりです。
人間はだれしも、生まれながらにして利己的です。
ですから、それをそのまま放任するということは、
物言えぬ動物にも劣るということなのです」
ハーンは思う。
「結局は動機のちがいなのだ。
西洋人における物事の動機は利己的であり、
日本人のそれは利他的なのだ。
前者は、私利を追求するのだから、
必然的に無秩序や混乱を招くが、
後者は公益を追求するのだから、
平和と繁栄をもたらす」
セツのような先祖への感謝や畏敬の念こそが、
日本人が最も深く尊ぶもので、
それが民族の生活と精神のよりどころであり、
且つ、国民性そのものなのだろう。
そうであるが故に、
親孝行は当然の義務であり、
家族愛はそこに根を生やし、
忠義心はその上に構築されているのである。
八雲はキセルをふかすうちに、
日本人の義務感は両親や血縁者だけでなく、
祖父母や曽祖父母、
さらにもっと前に亡くなった
すべての者にまで及ぶのだと悟った。
そして、いざ、国家に危機が迫れば、
その義務感は国民全体を
まるでひとつの大きな家族のように連帯させるのだ。
それは八雲の理解していた愛国心という概念を
はるかに上まわる深くて強い感情だった。
だからこそ、日本の軍隊は非常に手ごわいのだ。
この家族愛と忠義と感謝の心が一体となった感覚は、
いくぶん曖昧ではあるものの、
生きている親族と同じくらい
現実的に過去の者たちへの広がっているのだ。
日本=理想郷について、こう考える。
その理想郷とは、
古くからの神道の理念が最高点に達するということだ。
つまり、無意識の無私無欲の精神とか、
人の幸せを己の喜びとする願望とか、
万人が普遍的な道徳心を持つこととか、
己の良心の声に耳を傾け、
それに基づいて行動すれば、
いかなる宗教の法典も不要になるということであり、
それらが叶うほど人類が進歩すれば、
より高い次元の世界が実現するのではないか
ラフィカディオはミドルネームで、
ファーストネームはパトリックという。
キリスト教的、アイルランド的な名前なので、
パトリックは使われなかったらしい。
「小泉」は妻のセツの名字。
「八雲」は、松江の八重垣神社に伝わる
スサノオノミコトが稲田姫を娶った時の喜びの歌
八雲立 出雲八重垣 妻込めに 八重垣造 その八重垣を
から取っている。
黒い蜻蛉とは、
人間の魂を示す。

「人間の魂も、トンボも、
最初は地上に縛られていますが、
いずれ羽を広げ、自由になるからです」
小泉八雲の死去の時、
黒い蜻蛉が八雲の胸に止まる。

訳者あとがきに、こうある。
著者のジーン・パスリー氏が
これほどまでの多大な愛と畏敬の念をもって、
八雲の魅力を描いてくれたおかげで、
「小泉八雲=怪談を再話した人」だけの認識から、
私たち読者をもう一歩、
八雲の世界へ引きこんでくれたのではないでしょうか。
その一歩とは「日本人とは何か?」という
問いを投げかけてくれたことです。
まさに本書は「日本人とは何か」に対して
新発見させてくれる良書である。

なお、小泉八雲の写真がことごとく右側からなのは、
失明した左目を隠すため、右側からの撮影を求めたから。